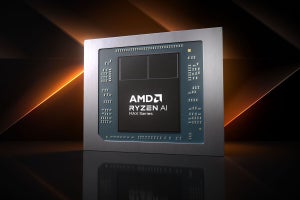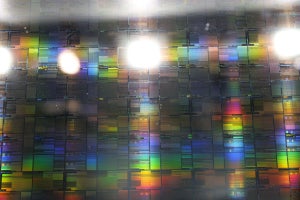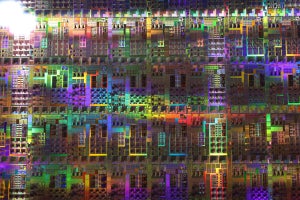原告、被告双方の会社のメールがそっくり持って行かれる
前回は私のロスアンゼルスでの2日半にわたる拷問のような供述記録(デポジション)の話をした。日本の訴訟手続きと米国のそれとはかなり異なる点があるので、この章ではその違いについて少々説明しておきたい。今ではビジネスは完全にグローバル化しているので、日本の企業であっても米国での訴訟に巻き込まれるのは日常茶飯になってきている。その場合には米国の手続きにのっとって行われるのだから、ちょっとは参考になるかもしれない。
2005年6月9日、AMDはインテルを相手に"インテルによる独占禁止法違反行為の結果AMDが被った損害賠償請求"について、デラウェア州地方裁判所に民事訴訟を起こした。米国でのこの種の訴訟の手続きで日本と決定的に違う点は、日本では原告側に立証責任があるので、訴訟を起こす前に訴える側の弁護士はあらゆる手を使って裁判で有効と思われる証拠を集めなければならない。最近はやりの弁護士ドラマでは、弁護士たちが聞き込みを行って情報を集め、有利になる証言をしてくれる人を探して説得したり、ごみ箱をあさったりして証拠品を集めるようなシーンが出てくるが、それは原告側が一方的に立証責任を負っているからである。
その点、米国の民事訴訟は非常に合理的な方法を使ってこのプロセスを進める。それが「ディスカバリー」である。宇宙探査機の話ではない。日本語では「証拠開示手続き」と訳されている。
裁判が始まる前に、双方にとっての有力な証拠を集めるために原告、被告双方が関連文書を全て裁判所に包み隠さず提出する手続きである。仕事上のやり取りのほとんどがメールで行われる昨今ではEメールの吸い上げが典型的な方法である。原告、被告双方の会社のメールサーバーのメモリ・ディスクを裁判所がそのままコピーして、双方の弁護士がお互いのメール内容を吟味して法廷で有力証拠として提出するものを抽出する。その後、その抽出したものに基づいて関係者を尋問して供述記録を作成するのである。双方"包み隠さず"提出することが義務付けられていて、後に違反行為がわかると罰金が科せられるし、裁判では不利になる。AMDとインテルの訴訟ではインテル側が"間違って"Eメールの重要な部分の本社サーバーの記憶を消してしまったという事件もあった。しかしこの手は今では多分通用しないであろう、というのもメールの記録などはクラウドに置かれているので裁判当事者が消してしまう場合は足がつくことが考えられるからだ。最近、大きなスキャンダルとなった「パナマ文書」の裁判のために集められた膨大なEメールの容量は2.6TBであったと報道されている。
私の供述記録のプロセスでは、私自身でも忘れていたようなかなり古いメールのコピーを目の前に突き付けられ、「このメールの内容はどういうことなのか」、「ここで言っているXX社のミスターKとは誰の事か?」、「ここであなたはAMDの製品について工場側に文句を言っているが、それはAMDの製品が劣っていたことをあなた自身が認めていることにならないか?」、などの質問が矢継ぎ早になされるのである。AMDのインテルに対する訴訟では当時としてはずば抜けて膨大な量のEメールを双方の弁護士たちが吟味した。キーワードの検索エンジンなどのIT技術を駆使した、シリコンバレー企業どうしのハイテク・ケースであったと報道されていた。昨年の米国大統領選挙ではヒラリー・クリントンのメール問題が話題になったが、現在では検索の効率を上げるためにAIの技術も使われているらしい。
米国の裁判制度
最近、トランプ大統領の発出した大統領令をめぐって大統領府と司法部門が真っ向からぶつかり合い、世界的なニュースになった。起こったことは以下のとおりである。
- トランプ大統領が中東・アフリカなど7カ国の国民の入国を禁止する大統領令を発出
- 各航空会社・移民当局は大統領令に従って対象国民の搭乗・入国を拒否
- ワシントン州司法長官がこれに異議を唱え訴え、地方裁判所が大統領令の一時停止を決定
- 各航空会社・移民当局は裁判所の決定通りすぐさま対象国民の搭乗・入国手続きを再開
- 大統領府はこれを不服としてカリフォルニア州控訴裁判所に上告
- 控訴裁判所はワシントン州裁判所の決定を支持、入国手続きは継続
- 大統領府はこれを不服として最高裁判所に上告の予定
と、まあ、世界を揺るがす大事件となったわけだが、今回の裁判プロセスで驚いたのはその内容もさることながら、そのスピードである。特に、大統領令が出てからの地裁と控訴裁判所審理のスピードの速さには驚かされた。通常の裁判プロセスに例を見ない超高速審理であった。
内容が内容だけに、各々の裁判官がほかの案件そっちのけでスピード審理した結果と考えられる。この超高速審理の理由の1つに、これらの裁判は全て裁判官による審理であったことがあげられると思う。冒頭の図式で示したように米国の裁判審理は、一般市民から選ばれた陪審員が審理するものと、プロの判事が裁判官となって審理するものの2種類に分かれる。私はどのようなケースが陪審員あるいは判事による審理になるのかのルールについてはよく理解していないが、一般的に、陪審員による審理のほうが時間がかかり、審理内容が技術的なものにはあまり適していないと言われている。陪審員裁判の場合は、時として意外な判決が出るケースもあるようである。ちなみに、前回のAMDとインテルのライセンス契約に関する裁判審理は陪審員による審理であった。一般市民から選ばれた陪審員に対し、「マイクロプロセッサのマイクロコードについて著作権が成立するか」、などと聞いてもピンとくるはずはない。事実、一時AMDにとって不利な評決となったが、その後の控訴審で決定が翻った経緯がある。
裁判というプロセスは民主主義の三権分立を担保するうえでの肝とも言うべき非常に重要なものであるが、その結果はとかく予想が難しい。
著者プロフィール
吉川明日論(よしかわあすろん)
1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、今年(2016年)還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。
・連載「巨人Intelに挑め!」を含む吉川明日論の記事一覧へ