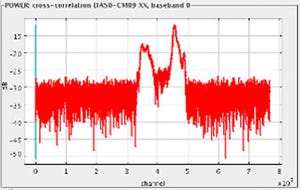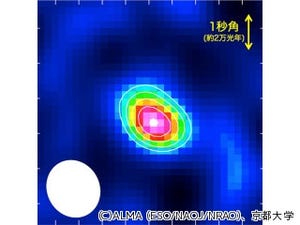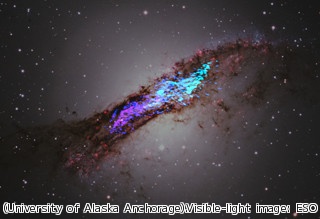日米欧が協力してアンテナを製造
ALMAの直径12mのパラボラアンテナは、50台の12mアレイのものは米国製とフランス・ドイツ・イタリア製、そしてACAの4基は日本製とメーカーは違っているが、これらは共通の仕様で作られている。また、ACAの12台の7mパラボラアンテナは日本製である。
上記の写真に見られるように、パラボラアンテナは12mの主鏡を持ち、集めた電波を4本の支柱で支えられた副鏡で反射させて、主鏡の中央に見える穴に電波を集める。10個の各バンドに対応する受信機は直径1m程度の円筒形のクライオスタットに納められており、この穴の奥に設置されている。
ALMAは最短では0.3mmという短い波長の電波を扱う。このため、パラボラの鏡面には高い精度が要求され、理想的な回転放物面からの誤差が12mパラボラでは2乗平均値で25μm、7mパラボラでは20μm以下という仕様となっている。この誤差は、食品用のラップの厚みより薄く、パラボラを東京ドーム大に拡大したときに0.5mmの誤差に相当するという超高精度である。
このため、パラボラ面のアルミパネルはスムーズに磨き上げられているが、ピカピカに磨き上げてしまうと、先日の金星の太陽面通過の観測などの場合において、アンテナを太陽の方向に向けると焦点にある受信機が太陽熱でダメージを受けてしまう。このため、鏡面を梨地加工して細かい凹凸を作って、サブミリ波は集めるが、数μmより波長の短い赤外線や可視光はぼかして拡散してしまうという絶妙のバランスを保っている。
そして、この精度をアンテナの向きの違い、温度や風の影響を含めて、あらゆる条件で維持しなければならないという厳しい仕様となっている。アンテナの向きが変わるとパラボラは重力で変形するが、コンピュータを駆使した徹底的な構造解析で、変形後も主鏡は回転放物面となる構造を実現している。変形した回転放物面は焦点位置などが変わるが、副鏡の位置を微調整して補正し、常に受信機に電波が集められるようになっている。
また、副鏡を動かして、クライオスタットに入った10バンドの受信機のうちのどの受信機のフィードホーン(電波を受けるラッパ状の部品)に焦点を合わせて電波を送り込むかを選択している。
温度による変形を抑えるためにカーボンファイバなどを活用
超精密なアンテナの大敵は温度である。現地は平均気温は-2.5℃であるが、砂漠であり-20℃から+20℃と温度変化が激しい。このため、12mパラボラでは、温度による変形がほとんど無いカーボンファイバのパイプとインバール合金の継手でアンテナを支える構造を作っている。一方、7mパラボラではコストダウンの点から鋼鉄製のフレームを使っているが、ファンを使ってフレームに外気を循環させて温度を均等にして、一様に膨張、収縮して放物面を保つようにしている。
また、アンテナの裏側などの電波反射面以外の部分は、20~30cmの厚みで発泡ウレタンを吹き付けて断熱し、その外側を金属パネルで覆っている。それでも、日中は太陽のあたる方では温度があがり、アンテナ全体が不均等に伸び縮みする。このため、必要に応じて、当初の設計には無かった日よけのパネルを増設しているという。これにより、アンテナの裏側がゴテゴテしてくるので、アンテナを開発した稲谷教授によると、関係者はこの日よけの追加を"ガンダム化"と呼んでいるという。
また、アンテナの方向精度は0.6秒角(分度器の1°の1/6000。12mパラボラの縁で20μmのブレ)と規定されている。風を遮るものが無い高原では、強い風が吹き、パラボラアンテナは強い力を受ける。しかし、9m/秒の風を受けても0.6秒角の方向精度を維持することが要求される。さらに、現地は水蒸気は少ないのであるが、稀に激しい雨や雪が降ることもある。雪は細かいパウダースノーでアンテナのわずかな隙間からも入り込む。豪雨の時は雨漏りがすることもあり、アンテナの耐環境性を改善する設計変更は今でも続けられているという。
アンテナには向きや角度を変えるリニアモータを使った駆動系と、10バンド分の受信機、A/D変換回路などが収容されており、受信機のフロントエンドを4K以下に冷却するための機械式冷凍機なども入っている。このため、アンテナの重量は約100tで、消費電力は75KVAという仕様になっている。
(次回は9月19日に掲載予定です)