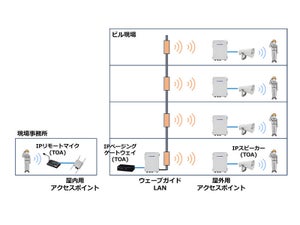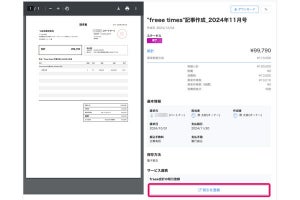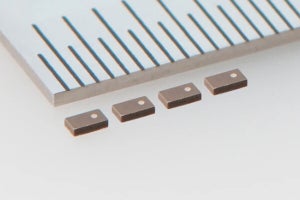御多分に漏れず、筆者も幼少の頃はプラモデル作りに手を出してみたことがあるのだが、手先の不器用さが祟ったのか、単に根気が足りなかったのか、あまりうまくはできなかった。それもあってか、プラモデル作りからは足を洗って長い期間が経っている。
操縦席から張線が1本
そのプラモデルの中でも、第二次世界大戦中に活躍した戦闘機のモデルを作った経験がある方は多いと思う。そしてこの手の機体は、モデルでも実機でも、コックピットを覆っているキャノピーのあたりから垂直尾翼に向けて、あるいは胴体側面から水平尾翼に向けて、細い張線が付いていることが多い。
プラモデルだと、これを伸ばしランナー(部品を取り付けてあるランナーを火で炙って柔らかくして、それを引っ張って細く延ばしたもの)を使ったり、細い銅線か何かを使ったりする。実機でこれは何かといえば、無線機のアンテナ(空中線)である。
無線通信に関わった経験がある方ならお分かりの通り、使用する電波の波長が長いほど、アンテナのサイズが大きくなる。では、第二次世界大戦中に使われていた無線機の、電波の周波数はいかほどだったのだろうか。そこで、たまたま手元に資料があるという理由で、米陸軍航空軍(当時のアメリカでは、まだ空軍は独立していなかった)の無線機を見てみる。
航空機同士、あるいは航空機と管制塔の間の通信で使用していたのは、SCR-274-N。送信機と受信機が別々になっていて、送信機はBC~457~A、BC~458~A、BC~459~Aの3種類があり、周波数はそれぞれ4.0~5.3Mcs、5.3~7.0Mcs、7.0~9.1Mcs。受信機はBC~453~A、BC~454~A、BC~455~Aの3種類があり、周波数はそれぞれ100~650Kcs、3.0~6.0Mcs、6.0~9.1Mcs。
McsあるいはKcsといった書き方をされると面食らうが、それぞれ「メガサイクル」「キロサイクル」である。今の周波数の単位は「ヘルツ」だが、サイクルもヘルツも同じ数字で、1Mcs=1MHzとなる。だから前述の数字は、そのまま単位をHz単位に置き換えてもらってかまわない。そして、1,000kHz=1MHzである。
さて。先のデータからすると、送信機3機種が使用する周波数の範囲は4.0~9.1MHz、受信機3機種が使用する周波数の範囲は0.1~9.1MHzということになる。これは、いわゆる長波(LF : Low Frequency。30~300KHz)から短波(HF : High Frequency。3~30MHz)にまたがる範囲である。波長は、長波が1~10km、短波が10~100mとなる。
この長い波長に合わせた空中線を用意しようとすると、必然的に大きなものになってしまう。ところが、重量も空気抵抗も増えてしまうから、そんな大きなダイポール・アンテナを立てるわけにも行かない。そこで、重量や空気抵抗を増やさずにアンテナの長さを確保しようとすると、張線という話になってしまったのだろう。
ちなみに、いまどきの航空機用無線機が一般的に使用する電波は、超短波(VHF : Very High Frequency。30~300MHz、波長は1~10m)、あるいは極超短波(UHF : Ultra High Frequency。300MHz~3GHz、波長は10cm~1m)だから、波長が短くなり、アンテナも小さなブレード・アンテナで済ませている。
その他のアンテナなど、いろいろ
実は、第二次世界大戦の頃からすでに、現代の電波兵器や電子戦につながる萌芽となる機器が、いろいろ存在していた。つまり、飛行機にアンテナなどの「ひっつきもの」が不可欠なものになったのが、第二次世界大戦の頃からという話になる。
通信機やレーダーに限った話ではない。電波を用いた航法・誘導システムも、着陸進入誘導装置も、電波高度計も、迷子にならないように陸上の基地や洋上の空母が電波を出して誘導するビーコン装置もあった。レーダーは対空用だけではなくて、洋上の艦船を捜索するレーダーも、眼下の地形を表示するレーダーもあった。
この中でも特に、レーダーのアンテナは目立つ「ひっつきもの」を生み出す原因になっている。眼下の地形を表示するレーダーとして有名なのは、H2SやH2X、それとAN/APQ-7イーグルだが、H2SやH2Xが胴体下面に付けたアンテナを半球型のフェアリングで覆っていたのに対して、イーグルのアンテナは直線翼みたいな形をしていて、これを胴体下面にむき出しで取り付けていた。
また、レーダーや無線通信を対象とする電波妨害も、すでにこの時代から行われていた。だから、そのための機器とアンテナも、当然ながら載っていたことになる。
一方で、この頃には当たり前だったものが、今では当たり前でなくなった。そんな「ひっつきもの」の事例がある。それが天測用のドーム。昔は大型機だとみんな航法士が乗っていたが、今みたいに航法システムや測位システムが充実していなかった。だから、船乗りと同様に六分儀を使って星の位置を測り、それに基づいて機位を出す、いわゆる天測も必要だった。
それをやるには頭上に視界が開けた場所が必要だから、航法士席があるあたりの胴体上面に、透明な半球型のドームを取り付けてあって、そこに頭を突っ込んで六分儀を使う。
「そんなものが写った写真が手元にあっただろうか?」と思ったら、あった。ワシントン・ダレス空港に隣接する、スミソニアン航空宇宙博物館の別館、ウドバー・ヘイジー・センターに展示されているB-29「エノラ・ゲイ」がそれである。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。