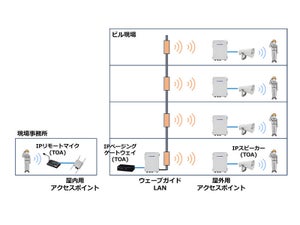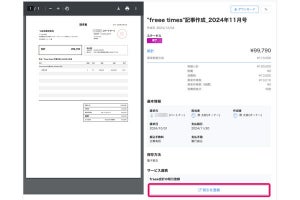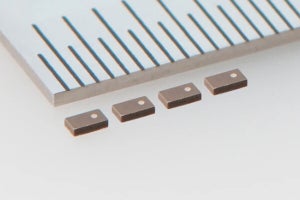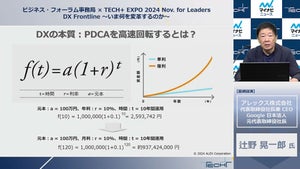デジタル化とDXは同じではない
IPA(独立行政法人情報処理推進機)発行の『DX動向2024』によると、日本企業の多くがすでにデジタル化によって業務プロセスの効率化や自動化を進める傾向にありますが、これはDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けたプロセスの一部に過ぎません。
アナログ・物理データを単に電子化することを「デジタイゼーション」と呼び、デジタル技術を用いて業務を効率化し生産性を向上させたり、製品・サービスの付加価値を上げたりすることを「デジタライゼーション」と呼びます。
しかし、DXが最終的に目指すものは、単なる業務効率の向上などではなく、デジタル技術の活用による新しい価値の創出や、ビジネスモデルそのものの変革です。いくら業務効率化が進んでも、抜本的なモダナイゼーションが進まない企業では、「レガシーシステムの温存」に陥ってしまうケースも少なくありません。
低位安定に陥る企業の課題、変革の足かせとなる相互依存関係
経済産業省によるDXレポートの最新版『DXレポート2.2』では、企業が変革に踏み出せない理由の一つとして、ユーザー企業とITベンダーの関係が「低位安定」の状態にあるという問題点を指摘しています。
まず、ユーザー企業は現行システムの大きな変革に伴うリスクを避け、現状維持を選択しがちです。一方、ベンダー企業も同様に、顧客の変革支援よりも既存システムのメンテナンス契約を維持する方が安定した収益を見込めるため、積極的な変革支援を行いません。
この相互依存関係が、DXの進展を阻む大きな要因となっています。よって、ユーザー企業とベンダー企業が共に新たなビジネスモデルを構築する「共創」が進まず、レガシーな企業文化が維持されるという悪循環に陥りがちです。実際、私たちが支援してきた企業でも、このようなケースを目の当たりにしてきました。
モダナイゼーションの失敗事例
この「低位安定」という状態によりモダナイゼーションが妨げられている事例をいくつか紹介しましょう。
あるサービス企業では、ITシステム刷新に向けた投資を行わず、特定ベンダー企業が提供するレガシーシステムを低価格で利用し続けていました。この企業ではベンダー企業と安定的な関係を築き、コスト抑制を実現していましたが、時代の変化に伴いレガシーシステムがベンダー企業から供給停止される事態に陥り、まさに2025年の崖に直面しています。
また、自社のシステムをパッケージソフトに依存していた小売企業では、パッケージソフトの保守期限切れに伴い、システムモダナイゼーションの必要性に迫られていました。パッケージの保守を委託していたベンダー企業には顧客の業務知識はあるものの、モダナイゼーションのノウハウがないために新たな提案ができず、この小売企業は今後のビジネス継続の危機に迫られています。
ある金融サービス企業では、システム更改を控えてクラウド移行を企画しましたが、ベンダー企業は既存システムの要件を前提とした現行踏襲でコストを見積もり、受注しました。しかし、当然ながらオンプレミスで行っていたことを、移行コストを含めてクラウドで同じように再現できるとは限りません。その結果、クラウド移行に伴うライセンスコストの高騰、本来クラウドで担保される範囲にまで及ぶ過剰なバックアップコストといった想定外のコスト高の課題に設計工程で直面することになりました。
これら3つの事例はいずれもユーザー企業側でシステムのグランドデザインを実施せず、ベンダー企業へ「お任せ」「丸投げ」という依存関係が続いたことが原因で起きたことと言えます。ベンダー企業側も旧来の低リスクの人月ビジネスから脱却できず、双方とも現状から抜け出すことできない硬直状態に陥ったケースと言えるでしょう。
DX推進でユーザー企業が陥りがちな「3つの落とし穴」
こうした課題を踏まえると、今後ユーザー企業には主体的な姿勢が求められます。『DXレポート2.2』では、ベンダー企業との単なる契約維持にとどまらず、共に新たなビジネスモデルを構築する「共創」を促進することが重要であると述べられています。
ユーザー企業は、自らの業務やビジネスモデルの見直しを行い、ベンダーと共に新たなグランドデザイン創出に取り組む姿勢を持つことで、初めてDXが実現可能となるのです。もっとも、ここでもユーザー企業が陥りがちな「落とし穴」があります。
1つ目は現行踏襲の落とし穴です。現行システムと変わらない前提でシステムアーキテクチャやシステム構成を考えてしまい、経営戦略・DX戦略との整合性が取れていないということです。つまり「ビジョン」に照らした要件ではなく、現行システムに照らした要件になっているのです。経営戦略とDX戦略の整合性を確保することが非常に重要です。
2つ目は情報投資における意思決定プロセスの落とし穴です。これは自社の情報システム部門だけでモダナイゼーション構想や「ありたい姿」を策定した結果、業務側など他のステークホルダーの投資効果を見落としてしまい、結果として意思決定に至ることができなかったケースです。すべてのステークホルダーの意向を踏まえて意思決定のプロセスを整備しなければ、DXを進めることは困難です。
3つ目は投資対効果への固執という落とし穴です。これは定量的な効果だけでなく、目に見えづらい定性的な効果をどう捉えて判断するかという視点が欠けている状況です。この場合、既存システムをそのままクラウドに持ち込むという、短期的に見れば安価で単純な延命措置を選択しがちになります。「投資対効果」から「ビジネス継続・発展性」という視点の変換を行うことが不可欠です。
こうした「落とし穴」に陥らないために、ユーザー企業はベンダー企業に丸投げすることなく、かつ経営層が積極的に関与して、自社のビジョンに即したIT全体のグランドデザインを策定することが求められます。
DXを成功に導く経営層の役割、リーダーシップが握る変革の鍵
最終的に、DXの実現においては経営層のリーダーシップが不可欠です。CDO(Chief Digital Officer)を含むCXOといった経営層のリーダーシップの下、変革への投資とリスクを受け入れ、企業全体でDXを推進する体制を整えることが求められます。
経営層は自社の外に目を向けて、テクノロジーのトレンドやベストプラクティスを知り、それらがどのように経営に寄与するかを理解する必要があります。
昨今では、「クラウドネイティブ」「マイクロサービス」「Fit to Standard」といった概念や技術の重要性が叫ばれていますが、これらをグランドデザインに取り込む際にも、その本質をしっかり理解したうえで行っていかなければなりません。こうした取り組みにより、ユーザー企業がベンダー企業を低位から引き上げて牽引することになり、これがユーザー企業とベンダー企業による共創の推進につながっていくでしょう。
とはいえ、まだまだIT部門はコストセンターと捉えられがちで、その価値を経営者が理解できないという段階にある企業も少なくないでしょう。このようなケースでは、各ステークホルダーの立場を踏まえて客観的な立場である第三者が示唆を与えるという手法も効果的です。
DXを推進するうえではレガシー化したシステムだけでなく、古くから続く企業文化こそが障害であり落とし穴となっているケースが見られます。
次回以降では、これからDXに取り組む企業や、まだ進んでいない企業が取り組むべきことについて、より具体的に紹介していきます。
著者:篠田 尚宏
Ridgelinez株式会社 Director Technology Group
著者:藤井 崇志
Ridgelinez株式会社 Senior Manager Technology Group