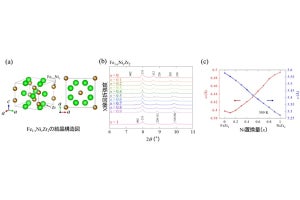光合成する葉緑体を藻類から取り出してハムスターの培養細胞に移植することに、東京大学などのグループが成功した。分解されるまで2日間ほど光合成の初期反応が起きていることが確認できた。光合成機能を持つ動物細胞の作製へ道を切り開く成果で、将来的には医療分野における組織やオルガノイド、食糧問題で注目を集める人工肉の培養といった応用が期待できる。
光合成によって二酸化炭素を吸収して酸素と糖を作り出す葉緑体は、植物細胞や藻類にはあるが動物細胞や菌類にはない。もし、動物細胞内で葉緑体が光合成するようになれば、細胞を培養する時に外から与える養分を減らせるうえ、呼吸で出る二酸化炭素の排出を削減できる。
東京大学大学院新領域創成科学研究科の松永幸大教授(細胞生物学)によると、植物や藻類から葉緑体を単離し、人工的に動物細胞や菌類に移植する試みは50年以上前からあったが、葉緑体が光合成することはなかった。
動物細胞に移植した葉緑体が働かなかった理由として、まず、身近な植物や藻類から取り出した、外気温や水温で働く葉緑体を用いていたことがある。摂氏20度や10度程度で培養する葉緑体が、ヒトを含めた哺乳類の動物細胞に適した37度程度の環境では光合成が起きなかった。
そこで松永教授は、イタリアの温泉で見つかった、42度で培養する紅藻のシゾンに目を付け、シゾンから単離した葉緑体なら動物細胞に移植しても生存できると着想。シゾンの葉緑体は、光合成細菌が宿主細胞に取り込まれて共生する進化の早い段階のものであることから原始的な特徴を持ち、取り出して別の細胞に移植しても自立的に光合成する能力(光合成能)が残っていると考えた。
従来の研究では、動物細胞への葉緑体の移植方法にも問題があった。ガラス管で刺したり、電圧をかけたりすることで細胞に穴をあけ、そこから葉緑体を入れようと試みていたが、細胞へ与えるダメージによって、細胞は異物が侵入したときのように反応し、入れた葉緑体がすぐ分解された。
松永教授は、細胞へのダメージがない方法として、マクロファージに代表されるような細胞の「貪食作用」に注目。マクロファージでは貪食してから数十分で取り込んだものの分解を始めてしまうが、分解までに時間がかかる細胞であれば、葉緑体を長く働かせることができると予想した。
抗体生産に用いられるハムスターの卵巣由来の培養細胞「CHO細胞」で分解時間が長かったことから、培養条件を操作して異物を取り込む貪食作用だけを高めることに成功。分解までにかかる時間が長い動物細胞を作り出し、シゾンから取り出した葉緑体を移植した。
シゾンの葉緑体を加えた液でCHO細胞を培養すると、貪食作用によって細胞が最大45個の葉緑体を取り込んだ。取り込まれた葉緑体を電子顕微鏡でみると、チラコイド膜の層状構造が2日間ほどは保たれており、光合成能があると判断できた。4日目になると層状構造が崩れていた。
葉緑体が見た目だけでなく光合成反応をしていることを確認するため、葉緑体のクロロフィルで水が分解されて生じる電子が移動する際のエネルギーギャップを蛍光として測定。層状構造が見えていた2日目まで蛍光を観察できた。4日目になると蛍光は著しく減って反応は止まっていた。
松永教授は今後、「光合成によって生じる酸素や糖などを計測し、光合成が起きていることを証明していきたい」と話す。
研究は、理化学研究所や東京理科大学、早稲田大学と、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業などの支援を受けて行い、10月31日付けの日本学士院発行の国際科学雑誌「PJA-B」電子版に掲載された。
|
関連記事 |