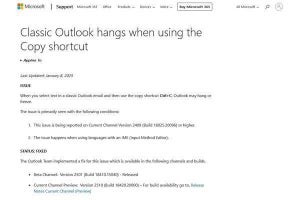「アニメやゲームなどのエンタテインメント産業は輸出に向いている」─。こう強調するのは今年4月にセガ社長COOに就任した内海州史氏だ。日本全体の国際収支においてデジタル赤字が課題となる中で、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』や『龍が如く』などの豊富なIP(知的財産)をグローバルに広げ、「セガのブランド価値を上げる」と意気込む。ソニー(現ソニーグループ)在籍時には、家庭用ゲーム機「プレイステーション」の立ち上げに携わり、様々な著名経営者の決断と覚悟を垣間見てきた。日本のゲーム産業の可能性とは?
ゲームの地位が変わった!
─ ゲーム産業は好調です。現状認識を聞かせてください。
内海 とうとうゲームの地位が世界のエンタテインメントの中心に、つまりは文化(カルチャー)のレベルにまで上がったなと感じます。私がソニーに在籍して家庭用ゲーム機「プレイステーション」の立ち上げに携わっていた1990年代前半の頃は、ゲームを玩具からエンタテインメントに変えようと一生懸命に頑張っていました。
ソニーが「ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時=SCE、現ソニー・インタラクティブエンタテインメント=SIE)」を設立したのも、そういった流れを意識してのことでした。しかし今はモバイルも含めて、老若男女がゲームをプレイするようになりました。ようやくゲームがアニメや音楽、映画などと同じレベルで語られるようになってきたわけです。その意味で、文化的なレベルにまで上がって来たということだと思います。
─ 約30年前は今のような地位ではなかったのですね。
内海 はい。30年前、映画業界の方々にゲームのIP(知的財産)に関する営業に行っても、門前払いとは言わないまでも、ハリウッドではよく使われる用語の「エレベーターピッチ(15~30秒というエレベーターに乗っているほどの短い時間に、自分自身やビジネスについてアピールする手法)」でなければ話を聞いてもらえませんでした。
しかし今は違います。「このような素晴らしいゲームをよくぞ作りましたね。私も、セガのゲームをよくプレイをしていました」とか、「あなた方のゲームのファンです」などと言われるのです。今の映画監督やプロデューサーは皆、もともとはゲーマーです。ゲームのことをよく知っている人たちなのです。
『スーパーマリオブラザーズ』や『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』などで遊んでいた人たちが監督やプロデューサーになっているのです。ですから、環境は以前とは全く違ってきています。
─ ゲームの世界に身を置くとは思っていなかった?
内海 思っていなかったのですが、自然な流れでゲームの世界に入りました。ソニーが音楽や映画の会社を買収した頃、私がいた経営企画ではエンタテインメント部門を作らないと、新たな事業に対応できないという議論が交わされていました。
なぜなら、ハードウェアの世界では、コストでは1円でも安く、1銭でも安くするというコストダウンの世界観が強かったのに対し、エンタテインメント産業では、タレントやクリエイティブといった人間関係が重要で、かつ固定費はかかっても変動費がほとんどかからないというビジネス構造が全く違う世界でした。当時のソニーは、その現実的で難しい対応を迫られていました。私は、そういった場面に偶然居合わせて、会社からエンタテインメント部門に行くように言われました。
当時、ソニーが買収した映画スタジオはハリウッド(ロサンゼルス)にあり、ハリウッドが世界の中心でした。また、音楽の中心はニューヨークでした。そういう世界をソニーのヘッドクオーターから見ていましたので、プレイステーションのプロジェクトに参加したことで、もしかしたらゲームでは日本、ひいては日本人が世界の中心となってビジネスが広がるかもしれないという感触は持っていました。
もう1つの動機は、ゼロからの立ち上げだったので面白そうだと。上の人間は、自分を音楽ビジネス要員に考えていたようですが、流れの中で自ら志願してゲーム業界に飛び込みました。まさかゲームがこんなに大きい事業、更には文化にまでなるとは思っていませんでしたね。
「プレイステーション」の立ち上げ
─ そのときのソニー社長が大賀典雄さんでした。どんなことを学びましたか。
内海 私の人生にとって大変大きな影響を与えてくれました。ソニーに入社し、最初の配属先は経営企画部門で計数管理や連結会計などを担当していました。入社3年目に米ペンシルバニア大学ウォートン校のビジネススクールへの企業派遣留学が叶い、MBA(経営学修士)を取得して帰国。そのときにエンタテインメント経営企画部門への配属となりました。
毎月のようにエンタテインメントの環境に関する資料をまとめて大賀さんや後の社長となる出井伸之さんも含めた役員の方々へのレポートを作っていました。当時の会議ではよく大賀さんより金言をいただいていたのですが、今でも覚えているのは、ソニーピクチャーズを買収したときに、多くの社員は「クリエイティブな会社を買った」と思っていた中、大賀さんはそうではなく、「ディストリビューション(コンテンツの流通)の会社を買ったんだよ」とおっしゃっていました。
クリエイティブな製品を作ることができても、メジャーと呼ばれるエンタテインメント企業というのは、結局そのようなコンテンツを流通できる力を持っていることが強みなのだと。それを聞いて私も「なるほどな」と思いましたね。エンタテインメントを本当に理解している人だと思ったことを覚えています。
─ 物事の本質を理解した経営者だったわけですね。
内海 ええ。しかも、生意気なことに私が「大賀さん、社長として最終的に目標にしていることは何ですか?」と尋ねたことがありました。すると大賀さんは「SONYのブランド価値を上げることだ」と答えられた。ブランドに対する意識が非常に高い方だったのです。安売りをとても嫌がる人でした。
─ 価格を安くして売上高を上げようとするケースが多い。
内海 ブランドを利用して品質の劣るものを安売りして、短期的に売上を上げても、ブランドの価値を棄損してしまえば中長期的には得をしない。ですから私もブランド価値を維持することをとても意識して今も経営に当たっています。
実はセガでも品質を意識せずに安売りをするケースがかなりありました。私はそれを絶対にやりたくないと。「SONY」は4文字ですが、「SEGA」も4文字。大賀さんの言葉を借りれば、SEGAのブランド価値を上げることが私の使命です。
大賀典雄氏と久夛良木健氏の一言
─ 大賀さんがプレイステーションの開発を決断したとき、開発者だった久夛良木健さんの役職とは。
内海 確か、まだ部長ぐらいで、大きい部署を持っているわけでもありませんでした。1992年頃、ソニーと任天堂はゲームプラットフォームの共同開発をする予定でした。久夛良木さんはCD-ROMも含めた、音源チップなどゲーム機のかなりの主要デバイスを任天堂に納入し、当時人気だった家庭用ゲーム機「スーパーファミコン」の拡張機としてローンチする約束を取り付けていました。
ところがこの件は任天堂の都合で取り止めになった。それを受けてソニーとして、どうすべきかという大賀社長を含めた御前会議に私は経営企画側の人間として参加したのです。そこで事業の可能性のスタディをさせてくれるよう、久夛良木さんを中心とした20人くらいのワーキンググループで大賀社長を説得。いろいろと調査し、セガを含めた企業をパートナーとしてあたりましたが、結局断られ、ソニー単独で挑戦するストーリーを組み立てていきました。
そこで久夛良木さんが残した名言があります。「我々の競争相手はゲーム企業の任天堂やセガではない。プレイステーションはリビングルームのプラットフォームになる。このビジネスでの競争相手は将来的には、マイクロソフトといった企業になってくる」と。まだマイクロソフトが全くゲーム業界に参入していない頃です。
─ 単なるゲーム業界の中でのシェア争いではないと。
内海 はい。プレイステーションは家庭の中でのワークステーション(業務用の高性能なコンピュータ)を作る事業であって、単なるゲームビジネスではないという形で構想を一段上げたのです。そうした構想を説明する資料を私が用意しました。
事業に参入するには巨額の投資がかかりますし、流通経路も確保しなければなりません。3Dの描画が可能となるハードのスペックをはじめ、事業を成り立たせるためのサードパーティー戦略やCD-ROMの利便性を生かした生産の仕組み、定価の引き下げなど業界のイノベーションにつながる計画を用意していきました。ゲーム業界の構造を一変させるような改革ができる可能性を提案資料としてまとめていきました。
それを、久夛良木さんを中心としたメンバーで、大賀さんにピッチしました。当時、ソニーミュージック副社長だった丸山茂雄さん、後のSCEの社長となる徳中暉久さんなども参加していましたが、出席者は7~8人の小さな会議でした。1時間くらいのミーティングだったでしょうか、質疑応答を重ねたあと大賀さんが最後に「DO it」と言い放ちました。その一言には、本当にしびれましたね。
─ 経営者としての大きな決断の場に居合わせた貴重な経験でしたね。さて、国際収支で見ると、日本は約5.6兆円のデジタル赤字。ITを含めたソフトの領域でゲームは日本の強さになり得るのでしょうか。
内海 IT業界では、全世界でデジタルのインフラやSaaS領域での戦いになってきています。BtoBでは業者へのニーズが似たようなものになります。日本はまだ独自マーケットで守られているかもしれませんが、日本の外にでると、基本言語が英語でしかも競合相手が世界の超有力企業になると差別化やコストメリットをとることが難しいのではないでしょうか?
ところがエンタテインメントのような文化的要素の強いものは、その時点で差別化されています。しかもゲームやアニメはグローバルの消費者にとっても日本が文化発祥の地ですから、世界への輸出に向いているといえます。ITの優れたサービスは外に出た途端にGAFAM(グーグル=現アルファベット、アマゾン、フェイスブック=現メタ、アップル、マイクロソフト)が競合になる可能性が高い。しかし、ゲーム会社はGAFAMのサービスを補完するパートナーになる場合が多いのです。
「ソニック」などの独自IPを世界に
─ ゲームにはそれだけの魅力があるということですか。
内海 ゲーム産業とは面白いもので、技術の進化と一緒に進化していきます。半導体の能力が上がると描画能力も上がり、ネットが登場するとオンラインゲームという新しいジャンルとビジネスモデルができた。スマホが普及すると、ユーザーベースが一気に爆発し、あらゆるジャンルのゲームが世界の隅々まで浸透していきました。
今後はAIが普及してきます。AIが広がれば、まずは生産性が大きく上がる可能性が高いことと同時に、AIの機能を使った新しい遊び方とビジネスモデルができてくると思います。そのときに、CGキャラクターに親しみを持つことに抵抗感の低い、AIに寛容かつ前向きな感性を持つ日本で作品を作ってみたら面白いのではないかと思います。最先端の技術に触れながらも、日本独自の文化的な要素も含むことによって、日本が世界の有力プレイヤーになれるかもしれないと思います。
─ 今後のセガが進む方向性を聞かせてください。
内海 先ほども述べましたが、セガをグローバルブランドにすることです。今回我々が中期で掲げたミッションは〝Empower the Gamers〟です。セガはゲーム業界にロックンロールを持ち込んだような存在であると思っています。
このようなコンテクストやファンの期待を背負い、素晴らしい作品を作ること、そしてそのIPを映画やアニメ、またマーチャンダイズなどを通じて展開していくこと、自分はそれを「トランスメディア」と呼んでいますが、ゲームが文化的地位を得た現在、このような展開がもっとグローバルで展開できるのではないかと思っているのです。世界を見ても、欧米は当然のこと、中国や東南アジア、中東、中南米にもセガのファンが大勢いることを、特にアフターコロナの昨今、強く実感しています。
このような実感を持つことは、実は年を取ると難しいと思うのですが、自分は多くの海外出張を通じて感じることができているのだと思います。もしかすると自分の数少ない取り柄の一つが、海外に出ることが好きなことかもしれません。私自身、大学時代にバックパッカーを経験していました。新しいものを見ること聞くことで、クリエイティブ、ビジネスのいろいろなプラスの刺激を受けるんです。そういう感覚が好きなのですね。