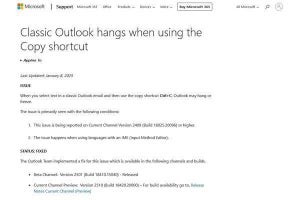「危機の時に連絡があるかないかで、お客様からの信用が全く違ってくる」─みずほ証券社長の浜本吉郎氏はこう話す。2024年8月5日の日経平均株価の暴落は、新NISAで市場に参入してきた投資家を青ざめさせた。その後、株価が回復したため、結果的には「買い場」だったが、その危機の時に顧客にいかに寄り添えたかで、その後が変わる。個人向け営業をいかに強化するか、強みを持つ債券引き受け、米国事業をさらに成長させるための方策は─。
海外投資家から日本市場が注目される理由
「世界経済の行方を決めるのは、やはり米国経済であり、それを基にした米株式市場。米国のファンダメンタルズには強さがある」と話すのは、みずほ証券社長の浜本吉郎氏。
「世界経済の行方はロシア・ウクライナや中東での紛争など地政学リスクもあり混沌としている。それを左右する米国経済はインフレ懸念は完全には払拭されてはいないが、FED(米連邦準備制度)は利下げのコンフィデンス(確信)を持っている」(浜本氏)
市場では、米国の利下げについて年内3回、来年4回という見通しもあるが、これには「やや楽観的過ぎるのではないか。こうした見方は要注意」と浜本氏。ただ、米国経済の底堅さはあり、大きく需要が喪失する、景気の〝クラッシュ〟のような事態は考えにくいと指摘する。
米国株は今後も堅調だというのがメインシナリオだと見る。そのため、グローバル投資家のリスク許容度はあり、米国に次ぐ資産の振り向け先として、株価にまだ割安感のある日本が注目されている。
ただ、日本では2024年8月5日、日経平均株価が暴落、前週末比4451円安の3万1458円を付けた。この下落幅は、1987年に起きた世界的株価暴落「ブラックマンデー」を超えた。
7月の雇用統計で米国の失業率が市場の事前予想よりも大きく悪化、利上げを見送ると見られていた日銀が短期の政策金利を0.25%に引き上げる追加利上げを行った上、総裁の植田和男氏がさらなる利上げを示唆する「タカ派」発言をしたこと、市場で超低金利の円を借りて高金利のドル資産に投資する「円キャリー取引」の急速な巻き戻しが起きたことが要因。
それでも、その後、日経平均株価は回復。浜本氏は、日本株が世界の投資家から注目される理由を3つ挙げる。
第1に、日本が30年続いたデフレから、持続的なインフレに向かっていると見ているから。その表れとして24年9月の1週間、欧米、中東、アジアの約300社の投資家が来日し、200社以上の日本の上場企業、20社程度のスタートアップとミーティングを行った。過去に例を見ないくらいの海外投資家の参加だったという。
第2に、そうした日本の変化を裏書きするように、日銀が金融の正常化に向けて踏み出したこと。8月5日の暴落で痛手を被った投資家もいたが、長期投資家はむしろ、値下がりのタイミングで買いに入ることができた。この時、みずほ証券のコールセンターでも7割が買い注文、3割が売り注文だった。
第3に、日本企業がPBR(株価純資産倍率)やガバナンスの改善、「モノ言う株主」を始めとする投資家との対話に力を入れ、企業価値向上に注力していること。そのためにM&A(企業の合併・買収)、MBO(経営陣による買収)など、様々な手法を駆使している。
「海外の投資家から見て、日本市場が欧米のような『普通の資本市場』になってきたという期待感がある」(浜本氏)
今後為替が140円台、多くの上場企業が想定する145円前後で推移して、利益を上方修正する企業が相次げば、再びの日経平均4万円が見えてくる。みずほ証券では24年10―12月に4万円、25年1―3月に4万1000円という見通しを持つ。
【関連記事】みずほFGが楽天カード出資へ協議 「楽天経済圏」との距離をさらに縮める?
暴落時に顧客にどう対応したか?
24年は日本で新NISA(少額投資非課税制度)がスタートし、多くの初心者投資家が誕生した年。その中には8月5日の暴落で冷や汗をかいた人もいたはず。みずほ証券では、どのように対応してきたのか?
浜本氏は、前週からの為替の動きを、危機感を持って見ていた。加えて日経平均も下げ、米国の雇用統計も悪い数字が出る可能性が指摘されていた。
実際に8月5日には日経平均は暴落。浜本氏は出張先から国内外の全社員に「お客様に寄り添おう。今何が起きていて、ポートフォリオがどうなっているか、ファクトをお伝えしよう」というメールを発信した。
普段から社内では「2倍通って、2倍話す」を合言葉に顧客接点を強める活動を進めていたが、暴落後の1週間は顧客を訪問するのをやめ、営業は担当している顧客全員に電話するという活動に切り替えた。「危機の時に連絡があるかないかで、信用が全く違ってくる」(浜本氏)
電話対応もコールセンターだけに任せると回線がパンクする恐れがあるため、全支店でも受けられる体制にした。
そして、単に連絡を入れるだけでなく、こうした暴落時だからこそ、顧客が何のために投資をしているかという「目的」を再確認し、そのゴールを見た時に今、どう行動するかを話し合った。例えば長期投資の人であれば、その1日の暴落で保有している株式や投資信託を売却するのではなく様子見を勧めたり、投資余力があれば下げ局面で買いに入ることを勧めるといったことができた。
件数は多くなかったが、中には信用取引をしていて、暴落によって追証(追加保証金)を支払わなければいけない投資家もいた。その際には、より少ないコストで損切りするための手法をアドバイスするなどした。
みずほ証券が株式を49%保有し、提携関係にある楽天証券に対しては、みずほ証券のリサーチや、暴落をどう見るかという内容の動画コンテンツを提供。それを楽天証券が運営するサイトで流すなどしたところ、多くのアクセスがあった。
みずほ証券と楽天証券は24年4月、共同出資で資産運用に関する相談業務を手掛ける「MiRaIウェルス・パートナーズ」を設立している。楽天証券という「非対面」のサービスの中で、ある程度資産を形成してきた顧客に対し、「対面」のコンサルティングを提供する。
さらに今後は「みずほ銀行から楽天証券への送客を強めることも視野に入れている。目指すのは1人でも多くの家計にアクセスして、資産形成のお手伝いをしたいということ。数千万の会員がいる楽天経済圏と、2000万口座を持つみずほグループとの提携をグループベースで深めていく」と浜本氏。
競争の激しい富裕層向けビジネス
今、大手証券各社は「富裕層向けビジネス」の強化にカジを切っている。野村證券と大和証券がリテール(個人向け営業)部門を「ウェルスマネジメント部門」と名称変更し、体制を整えるなどしている。みずほ証券はどう対応していくのか。
「拡散していた富裕層向けビジネスのリソースを、本部のプライベートバンキング(PB)部署に集約した」(浜本氏)。富裕層は証券会社の担当者に、例えばレベルの高いリサーチレポート、相場分析、プライベートアセットの商品、事業承継やM&A(企業の合併・買収)の相談など、「付加価値の高い」提案を求めている。
PB部署に人員を集約した他、外部採用を含めて、人数を25%増加させた。また、資産承継など専門分野について、みずほ信託銀行の知見を生かすなど、グループ力も投入。
さらにはスイスに本社を置くPBの老舗・ロンバー・オディエ・グループと包括提携。みずほの顧客にロンバー・オディエの投資一任運用サービスの提供などを始めている。
「(富裕層向けビジネスは)レッドオーシャンだと思うが、預金口座を持ち、貸出をし、投資銀行でのお付き合いがありという形で、総合金融グループとして、お客様とのお付き合いがあることは強み。グループの総力を結集してやっていく」
法人向け業務の強化も課題。みずほ証券は、旧日本興業銀行以来の伝統もあり、社債の引き受け実績は日本でナンバーワン、グローバルでも存在感を示すが、「他の大手も各法人とのつながりは強い。そのためリテール、マーケット(市場部門)との一体化をさらに進め、法人向け事業は強化していかなければいけない」と危機感を持っている。
強化に向けては、PBと同様に他社からの人材を迎え入れたり、こちらもリソースが拡散していたものを東名阪の主要都市に機能を集約していく他、各都市の大型店の法人向けビジネス機能を強めていく。
「この分野はもっと伸ばせる。そのためのビジネスプランの構築は、さらに磨きをかけていく必要がある」
みずほ証券は早くから、営業や業務効率向上に向けてAI(人工知能)の活用を進めてきたが、強みを持つ債券取引にも応用している。債券投資家の顧客情報をAIに読み込ませて、投資家の次の行動予測に磨きをかけている。
投資銀行の世界でも、様々なマクロトレンドの中で、次に企業はどういう行動に出るかを分析、M&Aの予測モデルの開発も進めている。
日常業務では、これまでは例えばメールのチェックや電話のモニタリングは人海戦術でやっていたが、人口減少に伴う社員数の減少や、働き方改革の流れ、人間の注意力の限界などもあり、AIにまずチェックしてもらい、そこから浮かび上がってきた問題点を人間がチェックするという形を取る。「ある部分はAIに任せ、人間は余裕を持って、より注意深く、本来見極めるべきケースを見に行く」
AIとの共存で、より人間が力を発揮できる仕事のやり方を模索している。
米グリーンヒル買収で「グローバルCIB」強化
海外事業のさらなる成長も求められる。これまで、みずほ証券は成長のドライバーとして「グローバルCIB(Corporate and Investment Bank、銀行、証券の一体化)ビジネス」を掲げ、様々な手を打ってきた。
中でも重要だったのが、23年5月に米投資銀行のグリーンヒルを約760億円で買収したこと。現在は米国みずほ証券と一体運営している。
グリーンヒル買収前は企業がM&Aなど、行動を起こすと決めた後にブリッジファイナンスなど資金面の支援に入るのが「入口」だった。ファイナンスを起点に株式を引き受けるECM、債券を引き受けるDCM、デリバティブ(金融派生商品)などの取引につなげてきた。
それでも一定の成果を上げてきたが、M&Aを実行するか否かという重要な意思決定や、会社の成長戦略をどうしていくかといった時の相談相手として、「十分に入り切れていなかった」という課題感があった。
みずほにとって「ミッシングピース」(足りない部分)だったM&A助言業務を、グリーンヒルを買収することで手掛けることができるようになった。
グリーンヒルの視点から見てもファイナンスなど、みずほのプロダクトとつながることで助言に「迫力」を持たせることができたという成果があった他、みずほの欧米ビジネスとの連携、さらには日本の主要企業との接点を持つことができ、ビジネスチャンスが広がったという。
23年12月に合併が完了して9カ月ほど経つが、みずほとグリーンヒルの連携で、すでに800件を超える企業との対話が行われている。今後は両社のさらなる一体化を図りながら、米国だけでなく欧州、アジアでの事業を強化することを目指す。
みずほ証券が強みを持つ米国事業だが、米国みずほ証券の業績は、みずほFGの連結決算の対象となっており、これまでみずほ証券の実力が世間からわかりづらいという課題があった。
それを今は、決算数字を国内と米国事業の合算で示すようになった。米モルガン・スタンレーと合弁を組む三菱UFJモルガン・スタンレー証券も同様の措置を取り、実力値を示そうとしている。
その結果、24年3月期の業績では、売上高に相当する純営業収益、純利益で、みずほ証券(純利益1627億円)は野村ホールディングス(純利益1658億円)に次ぐ2位に位置する。
「自主開示の数字だが、このスケールをさらに大きくしていきたい。今期、証券各社は好調で、特にリテールがいい。我々も悪くはないが、他社との差はある。銀・証連携でリテールをいかにスケールアップするかが、我々の最大の課題。リテールの課題をグローバル事業で打ち返して、5大証券会社の中で数字的にも存在感を示していきたい」
株式市場は乱高下もあるが、新NISAのスタートなどもあり、徐々に投資家の裾野は広がりつつある。また、法人向け分野でも、日本に「金利のつく世界」が戻る中で企業が様々な打ち手を模索している。個人、企業どちらにも選ばれる存在になることができるか。みずほ証券の地力が問われる局面である。