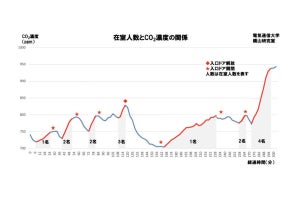工学院大学は10月10日、半導体薄膜の極性表面を活用することで、従来品よりも低温での動作も可能な薄膜トランジスタ型二酸化炭素(CO2)センサを考案したことを発表した。
また、今回のCO2センサに用いられたメカニズムが、メタン(CH4)など、CO2以外の温室効果ガスの検知にも適用可能であり、薄膜の特徴の1つである集積化によって、1つのセンサで複数種の温室効果ガスを同時にセンシングすることも理論上可能であることも併せて発表された。
同成果は、工学院大 電気電子工学科の相川慎也教授らの研究チームによるもの。詳細は、10月15~18日に幕張メッセで開催されるデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2024」にて公開される予定だという。
現在、地球は温暖化を超えて、「地球沸騰化」とまでいわれるようになっており、気温上昇がここで止められるのか、それとも気温上昇が続いて止められなくなるのか、その分岐点まで残された時間は少ないとされている。実際、日本でも真夏の最高気温の上昇や台風の激甚化など、気候変動の影響を多くの人が感じられるようになってきている。
そうした気温上昇の主要因とされるのが、CO2を代表とする温室効果ガスであり、気温上昇を食い止めるためには、そうした温室効果ガスの排出を減らし、大気中から削減する必要があるとされる。しかし、それを実行するには排出の現状を把握する高度なモニタリング技術が必要であり、しかもネットワーク化により分散配置可能なIoTガスセンサの開発が必要と考えられている。IoT化することで、空間カバレッジの向上が期待できると共に、迅速かつ高感度な検出が可能となるが、そのためには、センサデバイス自体の小型かつ低消費電力が必須で、さらに安価に作成できることも重要となることから、そうした考えに基づき研究チームは今回、そうしたニーズに合致するCO2センサの開発を試みることにしたという。
具体的には、薄膜トランジスタを用いたCO2センサが開発された。低コスト化と小型化が可能であると同時に、半導体薄膜の極性表面を活用することで、従来品よりも低温動作における高感度化も実証されたとしており、これらの結果は、センサの消費電力抑制につながる成果だと研究チームは説明している。
また今回のCO2センサのメカニズムは、CO2よりも温室効果が高いといわれるメタン(CH4)など、ほかの温室効果ガスの検知にも適用可能とする。薄膜の特徴の1つである集積化を用いることで、1つのセンサで複数種の温室効果ガスを同時にセンシングすることも理論上は可能としている。
なお、研究チームを率いる相川教授は今回の成果に対し、「査読付き論文を始め、学術面では実績と根拠がありますが、産業界でこの技術を利活用するのはこれからです。まずは共同研究などでラボレベルから社会実装レベルに近づけ、技術で社会貢献できると幸いです。薄膜に関する現場での課題や悩みも伺い、引き続き、SDGsの実現など社会課題解決をゴールとする研究に取り組みたいと考えています」とコメントしている。