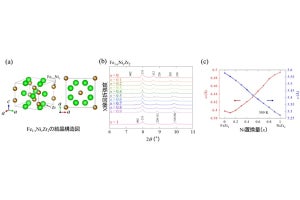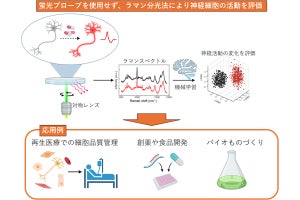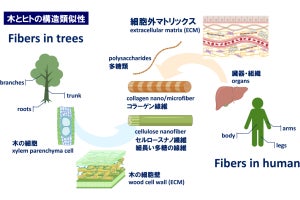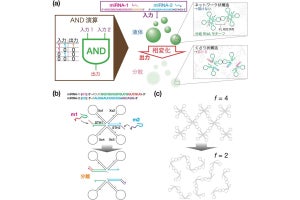量子科学技術研究開発機構(QST)は9月3日、iPS細胞における課題となっていた「点突然変異」は、iPS細胞株の樹立に伴って生じたものであることや、iPS細胞種間でその変異数に大きな差があることなどを解明したと発表した。
同成果は、QST 放射線医学研究所 放射線規制科学研究部の荒木良子シニアスタッフ、同・菅智技術員、同・法喜ゆう子研究員、QST 量子医科学研究所の安倍真澄上席研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
再生医療の要として期待されるiPS細胞だが、まだ課題も多く、その1つに同細胞のゲノム中に存在する点突然変異の問題がある。これらは移植の際の免疫原性や造腫瘍性の原因となりうるため、慎重に取り扱うべき課題だとする。なお、これまで、iPS細胞株のゲノムあたり300~1000か所(遺伝子のタンパク質コード領域あたりにすると平均6か所)の点突然変異が報告されている。
点突然変異の原因は不明だったが、近年、その主な原因がゲノム初期化に伴うDNA損傷チェックポイント機能の低下と、さらには、DNA損傷の要因となる活性酸素がその時期に一致して発生することにあることが、研究チームによって究明された。さらに、活性酸素が少ない臍帯血由来赤芽球をiPS細胞樹立の親体細胞とすることで、変異数を劇的に抑制できることも解明。
しかし、これまでのところ、点突然変異はiPS細胞樹立に伴う現象ではなく、もともと親体細胞に存在していたものとする考えが支配的であるという。そこで今回の研究では、100種を超えるiPS細胞株を用いて全ゲノムシーケンシング解析によりゲノムに存在する変異を明らかにし、その起源と発生機構の解明を試みることにしたとする。
今回の研究による以下の3つの解析結果から、点突然変異はiPS細胞樹立に伴うものであることが示されたとした。
1個人の皮膚線維芽細胞から異なる2つの方法でiPS細胞株が樹立され、全ゲノムを対象に点突然変異が解析された結果、変異数が樹立法に依存することが明確に示された。
同一マウス個体から調製した体細胞から33種のiPS細胞株および2株の核移植ES細胞が樹立され、各株の全ゲノムの点突然変異が解析された。その結果、親体細胞株にすでに存在していた変異として株間で共通に存在する変異はほとんど観察されず、検出された変異の大部分はそれぞれの株に特有の変異だった。
同じ個体から樹立されたヒトiPS細胞姉妹株に関しても親体細胞株と、5株のiPS細胞姉妹株に含まれる点突然変異の詳細な比較解析から、iPS細胞の変異が元の親体細胞株に存在した変異ではないことが強く示唆された。
これらの3つの独立した実験は、どれもiPS細胞で検出される点突然変異の大半が、iPS細胞樹立に伴って新規に生じた変異であることを示していたという。
次に、上述の結果を受け、75種のヒトiPS細胞株の全ゲノム解析が行われると、点突然変異数が従来考えられていたよりもはるかに多い、数千から1万以上のiPS細胞が発見されたとした。その一方で、臍帯血由来赤芽球を親体細胞としたiPS細胞では、タンパク質をコードする遺伝子領域に変異を持たない株も存在し、その他のゲノム領域にも変異が極めて少ないなど、全ゲノムで見ても変異数が極めて少ないことが改めて確認できたとする。
また、通常は極めて効率的に修復される、DNAの塩基のシトシン(C)からチミン(T)への「C>T変異」が多くのiPS細胞で見られ、総変異数を押し上げる主因となっていたという。それに加え、遺伝子発現調節に重要なシトシンにグアニン(G)が続く「CG配列」でのC>T変異を、通常の「生殖細胞系列変異」とiPS細胞とで比べたところ、後者でより多く生じていた。
さらに特定の「レトロトランスポゾン」配列のCG配列で、より高頻度に変異が生じることも示されたとした。ある種のレトロトランスポゾンは遺伝子の近傍に存在し、その発現制御に関与することが最近になって議論されており、注意深い解析の必要性が示唆されたとした。
iPS細胞樹立時に変異を生じる機構の解明をさらに進めることで、変異の抑制技術の開発などにつながることが期待されるとしている。