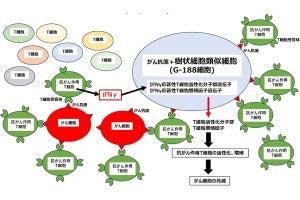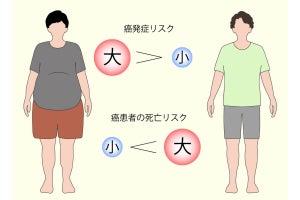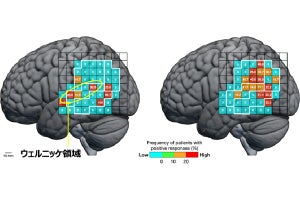大阪公立大学(大阪公大)は8月7日、日本における機能性消化管疾患である「げっぷ障害」の割合と疾患や生活習慣との関連などを検証するため、一般成人1万人を対象にWeb調査を実施した結果、151人(1.5%)がげっぷ障害であることがわかり、消化器疾患の有無(胃食道逆流症、機能性ディスペプシア、甲状腺疾患)や、満腹まで食べること、咀嚼回数が極端に少ないまたは多いことが、げっぷ障害の発症に大きく関連し、炭酸飲料水の摂取頻度は関連がないことも明らかになったと発表した。
同成果は、大阪公大大学院 医学研究科 消化器内科学の藤原靖弘教授、同・小林由美恵病院講師、同・沢田明也病院講師らの研究チームによるもの。詳細は、米国消化器病学会の刊行する消化器病学と肝臓病学に関する全般を扱う学術誌「The American Journal of Gastroenterology」に掲載された。
-
一般成人1万人を対象にWeb調査の結果、151人(1.5%)がげっぷ障害であることが判明。消化器疾患の有無(胃食道逆流症、機能性ディスペプシア、甲状腺疾患)や、満腹まで食べること、咀嚼回数が極端に少ないまたは多いことが、げっぷ障害の発症に大きく関連することが明らかにされた(出所:大阪公大プレスリリースPDF)
げっぷ(おくび)は、胃または食道から空気が逆流して口から吐き出される症状であり、誰もが日常的に経験する生理現象の1つだ。その一方で、「胃食道逆流症」(胃酸が食道に逆流することにより胸やけを訴え、胃カメラで食道に傷(逆流性食道炎)が観察される疾患)や「機能性ディスペプシア」(胃カメラでは潰瘍などの病変が認められないにもかかわらず、胃痛、食後のおなかの張り、すぐにおなかがいっぱいになり食べられないなどの症状を訴える機能性消化管疾患/腸脳相関障害の1つ)など、さまざまな消化器疾患の症状としても重要とされている。
日常生活において支障を来すほどのげっぷは、本人にとって深刻な症状であり、QOLの低下を招いてしまう。国際的な基準(ローマIV分類)でも、機能性消化管疾患/腸脳相関障害の1つとしてげっぷ障害が掲げられており、グローバルな調査では、げっぷ障害の頻度は全世界において成人の約1%と報告されている。しかし、日本における頻度や発症に関与する因子は明らかになっていなかったという。そこで研究チームは今回、一般成人1万人を対象にWeb調査を実施し、げっぷ障害の頻度と疾患や生活習慣(食べる速度、咀嚼回数、炭酸飲料水の摂取頻度、満腹まで食事をとるかなど)との関連、さらに「SF-8質問紙票」を用いて、健康関連QOLに与える影響を調査することにしたとする。
-
げっぷ障害が健康関連QOLに与える影響。SF-8質問紙票にて評価が行われ、身体的サマリースコアと精神的サマリースコアが算出された。スコアが低いとQOL低下を示す。グラフ中の*は、統計学的に有意差ありを表す(出所:大阪公大プレスリリースPDF)
その結果、ローマIV基準による「週に4日以上煩わしいげっぷを訴えるげっぷ障害」は151人(1.5%)に認められたという。また、げっぷ障害がない人と比較して、胃食道逆流症(オッズ比4.35倍)、機能性ディスペプシア(1.93倍)、甲状腺疾患(3.64倍)を抱えている人が多いことも明らかにされた。さらに、食べる速度が速い(1.54倍)または極端に遅いこと(1.85倍)、満腹まで食べること(1.54倍)、咀嚼回数が極端に少ない(1.44倍)または極端に多い(2.43倍)ことが、げっぷ障害の発症と関連することも確認された。
そこで、さらに詳しく関連を調べるため、多変量解析が実施されると、胃食道逆流症、機能性ディスペプシア、甲状腺疾患の有無、満腹まで食べること、咀嚼回数が極端に少ないまたは多いことが、特にげっぷ障害の発症に関連することが突き止められた。その一方で、炭酸飲料水の摂取頻度との関連は認められなかったという。他にも、げっぷ障害は身体的・精神的健康関連QOLを低下させることも改めてわかったとした。
今回の研究により、日本でのげっぷ障害の頻度が明らかになった。有病率が成人の1.5%だったという事実は、実際に症状に困っているが医療機関を受診していない人が多いことも考えられるとする。
げっぷ障害では「認知行動療法」(げっぷ障害の病気の成り立ちを理解させること(認知パート)と、主に腹式呼吸により訓練すること(行動パート)を実施する療法)を行うことが多いが、治療は容易ではなく、しかもそれを実施している医療機関も限られているのが現状。今後、げっぷ障害の患者において、咀嚼回数の評価や食生活習慣改善による効果を確認することで、将来的に患者自身で行う治療方法の選択肢となることが期待されるとしている。