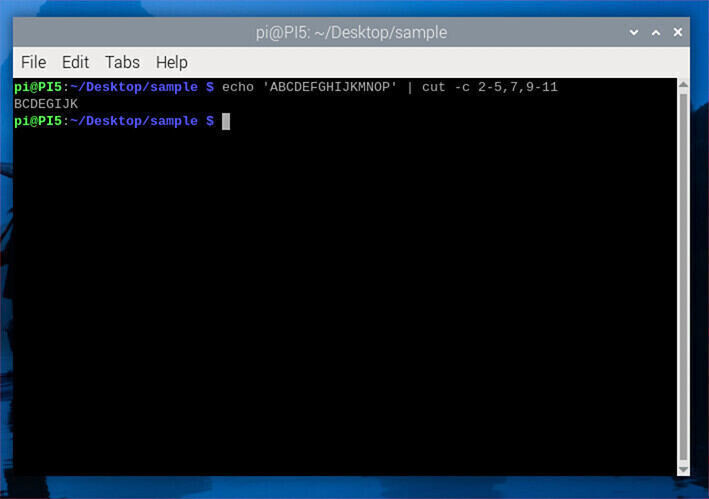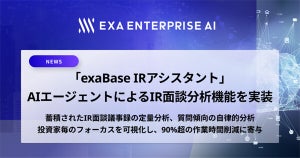「日本の農産物は世界一の美味しさです。その魅力を世界に伝えたい」こう語るのは、Oishii Farm(オイシイファーム)社長の古賀大貴氏。米国・ニューヨーク近郊で、日本品種のイチゴを最先端技術の植物工場で栽培。その美味しさに魅了され、発売当初NYでは1パック50ドルのイチゴが飛ぶように売れた。現在は量産化に成功し10ドル前後まで価格を落とし、アメリカの一般家庭にも普及が進む。「日本の農作物はもの凄く大きなチャンスがある」と語る古賀氏の周りには、大手企業の出資も集まる。植物工場でつくる日本の農産物は将来的には世界をリードできるのか─?
米国高級スーパー・ホールフーズで日本産イチゴが大人気
─ 古賀さんが米国で起業され米国で販売している日本産のイチゴが話題になっていますね。古賀さんの起業の志と目的から聞かせてください。
古賀 いま農業を取り巻く環境はこの10年ぐらいで激変しています。このままいけば現在の農業はみんなが思っている以上に早く崩壊し、持続可能ではなくなります。既存農業で重要なことは5つあります。1つ目は安定した気候です。2つ目は労働力、3つ目は水。4つ目に土地、最後に農薬です。この5つが大前提の条件になります。
実は先進国の中で日本はこれがほとんど揃っています。賃金の高騰は緩やかで、水も豊富にあり、農薬もたくさん使える。日本人が食べていく分に必要な農地も十分に確保できます。
一方で世界的に見ると、特にアメリカのような先進国ではこれらはほとんど揃わないのです。水は毎年大干ばつですし、不法滞在者に下支えされていた時給も以前は500円ほどでしたが、移民政策によりいまは時給3000円払っても誰も農地では働いてくれないのです。農薬もどんどん使えなくなっています。こうして既存農業のコストがもの凄いペースで上がっているのが現状です。
─ なぜ植物工場でやろうと思ったのですか。
古賀 日本では一昔前に、植物工場は通常の倍程度のコストがかかると言われていたのですが、気付いたら世界的に見ると既存農業のコストが2倍になってしまったということがあります。一方で、植物工場は先ほど挙げた5つがほぼ全部必要ないのです。それから農地でなくてもどこでもできるので、われわれのいまの農場も元々プラスチック工場だったところです。完全無農薬で、機械による自動化で人も少なくて済みますし、水もリサイクルできています。
これから植物工場のコストはどんどん下がっていきますので、自動車がガソリン車から電気自動車に移行していったように、不可逆的な大きな流れが農業で起きるというのはほぼ決まっています。ですから植物工場に取り組むスタートアップ企業たちがたくさん出てきました。他の人たちがみんなレタスをやっていた中で、われわれはまず短期的により収益化ができて、技術優位性があり、ブランドを作る事ができる作物にしようと考えました。
つまり、儲かるかどうか、他の人ができなさそうなもので、ブランドが作れるかどうか、という3つの観点で最初にイチゴを選びました。〝イチゴを制するものが植物工場を制する〟というのがスローガンです。
─ 日本品種の農作物はもっと海外で勝負できると。
古賀 はい。ただ単に高級イチゴをアメリカで売って儲けようということではありません。われわれはあくまで農業がこれから植物工場という新しい形の産業に生まれ変わっていく中で、世界最大の農業生産者を目指しています。それを日本の品種で日本の技術を使い実行していくときに、どういう作物を、どこで販売すればいいのかをたくさん考えました。その結果、新鮮なイチゴが物理的に手に入りにくく、日本の高級イチゴをブランディングしやすい富裕層がいるニューヨークをファーストステップとして選びました。
しかしわれわれのゴールはその先にある、植物工場を農業の新たなスタンダードにしていくということです。子どもや孫の世代が大人になった時に「野菜や果物って外で育てていたの?」という時代が必ず来ます。それを早期にサスティナブルに取り組むということを直近のゴール設定にしています。
─ その高級イチゴがニューヨークで1パック5000円でも売れていると。
古賀 はい。もともと50ドルで販売していましたが、今は10ドルまで落として販売できるようコストを下げることに成功しました。ホールフーズという高級スーパーを中心に販売しています。
小さな市場で高く売って儲けようということではなく、われわれのミッションというのは、できるだけ早くいろいろな人に届けるというのがゴールです。
─ 創業者として市場の反応をどう受け止めていますか。
古賀 実際に事業を始める前にリサーチの観点で日本のイチゴを輸入して、市場調査をしています。こういう品質のものが食べられたら、いくらぐらいで買いますか、というようなことを事前に現地でやったのです。その段階で確実に売れるというのはほぼ分かっていました。自分たちの手で作ったものが、「こんなイチゴ食べたことない」と皆さんに言っていただけるのが非常に嬉しいです。
─ イチゴ以外の日本の野菜や果物で、まだまだアメリカ市場で勝負できるなと感じるものはありますか。
古賀 たくさんあります。基本的に大半の作物において、日本の品種は他国と比べ圧倒的に美味しいです。日本で育てられているような作物の大半は、日本の品種が世界一美味しいと言っても過言ではありません。
─ まだまだやるべき作物がたくさんあると。
古賀 ええ。日本は消費者のレベルが世界一高いので、その消費者を満足させるために研ぎ澄まされた品種がたくさんあります。本来日本の気候でしか育てられなかった作物を植物工場でやることによって、世界中どこでも育てられてこれまで手に入らなかった場所で販売できる。これが、われわれの圧倒的な強みだと考えています。
─ 日本政府や農業関係者とは現在どのような対話をされていますか。
古賀 われわれがやっている技術は、従来日本で育て、日本にしか市場がなかったものを、日本の特許で世界中どこでも作って販売できるというものですから、市場拡大が一気に50倍、100倍見込めます。どうやってこれを日本のIPとして世界に輸出していくかという話を政府関係者としています。
より長期的視点で考えると、日本は2050年までに農家さんが8割いなくなってしまうのです。イチゴでいえば、あんなに人気のあまおうですら、作り手は2030年までに半分になる。なんらかの生産性の高い形で代替していかないと、ただでさえ食糧自給率が低い中、さらに日本は輸入頼みの国になっていってしまいます。
海外から見た日本の存在感
─ アメリカから世界を眺めておられる古賀さんですが、現在の日本は世界からどう見られていますか。
古賀 日本全体の存在感でいくと、当然、ジャパン・アズ・ナンバーワンであった頃に比べると低下していますし、アジアのニュースと言ったら日本より中国の名前が先に出てきます。
でも日本の外にいて感じるのは、日本のブランドにはソニーやトヨタを始め、揺るがないものがあるということです。アニメ、カルチャー、食文化ももの凄くユニークで、世界一といっても過言でないと思います。フランスか日本か、というレベルで、海外からはリスペクトを受けている国だと思います。
日本国内ではお先真っ暗だというようなイメージがありますが、世界からの評価はまだまだ先人たちが築いて来てくれたブランドで維持されていると思います。ですから本当はもっとポジティブに攻められるのにというのがわたしの感覚です。
─ 掘り起こしていけば元来いいものを持っていると。
古賀 はい。農業に関していうと、日本の農業の存在感は欧米ではまだゼロに近いです。日本の農作物が凄いというのは、一部の東南アジアと中国ぐらいでしか恐らく知られておらず、欧米では知名度がまだまだ低いのです。日本のイチゴと言ったときに中国ではみんな高級イチゴだと認識しているのですが、アメリカではまだまだ何それ? という温度感です。
─ 日本の場合、農業関係のニュービジネスは非常に少ないですよね。
古賀 日本ではすでに農業が突き詰められているので、新しいことを試みても、ほとんどビジネスになり得ないのです。ですから世界に市場を移さない限り、あまり大きなビジネスになりにくいんですよね。既得権益も法律の問題もあり、乗り越えるべき壁が多いのです。
さらにいえば、日本は既存品の品質が良すぎるので、これ以上何か改良してより美味しく安くするのがもの凄く難しい市場になっています。日本を起業の場に選ばず、アメリカ・ニューヨークを選んでいるのはその理由です。日本は競合が圧倒的に多い市場なのです。
─ しかし日本の潜在力、世界に目を転じると、そういった日本の魅力を発揮できるのだということですね。今後ターゲットになる品種はどういったものですか。
古賀 われわれの技術の特異なところは蜂を飛ばすことです。いままで植物工場はレタスなどの葉物しか安定的に量産できなかったんですね。葉物以外の作物はほとんど全部受粉が必要で、蜂を飛ばさなければいけないのです。しかし蜂は完全人工環境下だと飛びませんでした。だからこそ逆に蜂を飛ばすことに成功すれば、他のどんな作物も育てることができます。
─ 現地での知名度は上がってきていますか。
古賀 おかげ様で普段ホールフーズで買い物するお客様の中では3割ぐらいまで来ています。これがどれぐらいかというと、ホールフーズ内では5万品目販売している中で、上位0.1%ぐらいのブランドになったということですので、相当ブランド認知は進んでいるかなと。ニューヨークでしか売っていないにもかかわらず、全米でのブランド認知が8%まできています。
全米で8%以上の認知度がある日本の食のブランドは非常に少ないです。CNNなど全世界のニュースでいま配信されていますので、今年を機に認知度がさらに増えるのではないかなと思っています。
─ 今後も活動の拠点はアメリカに置くつもりですか。
古賀 本社は恐らくアメリカになるかと。グローバルで戦えるチームを作るとすると、どうしても必然的に東京にはならずアメリカだと思っています。農場自体はアメリカだけではなく、世界中に展開していきたいと考えています。
─ NTTを始めとした日本の大企業とも資本提携が進んでいますね。
古賀 われわれがやろうとしていることは、グローバルで植物工場を新たな農業のスタンダードにするということではありますが、そこに行く手段としての技術というのは、本来日本のお家芸なのです。サスティナビリティなど言われる前から、シャープさんやパナソニックさんは植物工場を地道にやってこられたわけなんですね。なぜ日本で生まれたかというと、植物工場は2つの産業の掛け合わせです。施設園芸、要はビニールハウス農業と工業の組み合わせなんです。
施設園芸は世界的にいうと日本とオランダにしかなく、アメリカやフランスではありませんでした。工業は、当然日本、アメリカ、ドイツが強い。この両方を併せ持つ国というのは地球上に日本しかありません。
ですから植物工場は生まれるべくして日本で生まれているのです。われわれが戦う場所は日本以外のより良い市場を選んでいますが、技術の源泉はやはり日本にいいものがたくさんある。そういった意味で、日本のメーカーと組みながら、植物工場を日本の新たな基幹産業にしていきましょうということを画策している背景があります。
─ 今後、市場拡大の見込みがあると。
古賀 ええ。産業の大きさでいくと、植物工場で作れる野菜は100兆円規模の市場規模になってきます。遅かれ早かれ、農業のほとんどが植物工場に置き換わっていくと考えると、自動車産業クラスの市場が立ち上がって来るのです。
この分野で日本として覇権が取れれば、これだけで国が立国できるほどの大きさの産業になっていきますから、ここをみんなで全面的に押さえにいきましょうということを提唱させていただいています。それで今回、日本を代表する各インダストリーが一緒にやろうと言ってくださっています。
嬉しいのは、提携した企業は植物工場を10年、20年やってきた会社が多くいらっしゃることです。このビジネスについて既に経験のある企業の会長や社長が実際われわれの農場まで来られて、これならいけるんじゃないかとおっしゃってくださることが、われわれの自信にも大きく繋がっています。みなさんの知識や経験も生かしながら、日本企業連合として日本の植物工場が世界をリードできるようにしていきたいと思っています。