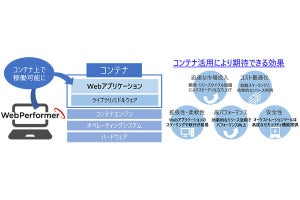「食の喜びを地球全体で満たしていこう」─。しょう油最大手・キッコーマンが『グローバルビジョン2030』で掲げる経営理念。1973年(昭和48年)米国ウィスコンシン州に初の海外工場をつくり、以来50年余、海外の生産拠点は8カ所に増え、100カ国以上に商品供給を行うグローバル経営。今や全売上高の75%を海外市場で賄い、全利益の8割を海外であげるという態勢。コロナ禍が明けた今、”人の交流”と同時に”食の交流”が進む。そうした状況下で、同社社長・中野祥三郎氏は、「特徴を持った商品開発」に注力。顧客との対話の中でも、「今までとは違った商品に強い手応えを感じます」と語る。1917年(大正6年)千葉・野田に産声をあげて以来100年余。『世界のKIKKOMAN』に成長・発展した要因とは何か? 各国で食文化は異なるものの、その国の食材を生かすのは”しょう油”だという位置付けで、新しいレシピを提案し続けたという開拓者精神。根底にあるのは、国と国をつなぎ、人と人をつなぐという経営理念である。
付加価値の高い経営をどう実現するか
付加価値の高い商品をいかにして創り上げていくか─。
コロナ禍の間、キッコーマンのように、しょう油など調味料の製造・販売を手がける業界も多大な影響を受けた。
しかし、今は事情が一変。外食産業もインバウンド需要もあって一気に活性化。業務用の需要が高まり、そこに人手不足も加わって、いかに迅速においしい料理を提供するかという課題が出てきた。
「それで、しょう油でもちょっと濃縮したようなタイプが求められたりします。うちは、バラエティがあるので、特徴のあるしょう油の開発にも注力しています。通常の昔ながらのしょう油ももちろんありますけれども、そういうちょっと特徴のあるもの。要するに、短時間でおいしい料理ができるような調味料の開発ですね。ワインにしても同じで、濃縮タイプが人気です」
中野祥三郎氏(1957年=昭和32年生まれ)がキッコーマン社長に就任したのは2021年(令和3年)6月で、コロナ禍の真っ只中。世界の食文化にも欠かせないものになったしょう油に対する消費者のニーズについて、中野氏は、「特徴のあるしょう油への需要が高まっている」と語る。
キッコーマンは同じしょう油でも、業務用と家庭用の2つを手がける。国内では3割のシェアを持ち、業界トップ。海外市場にもいち早く進出し、1973年(昭和48年)、米国中西部のウィスコンシン州に生産工場を建設。以来、グローバル経営に取り組み、しょう油を世界の人々に受け入れられる商品に育ててきた実績を持つ。
グローバル化も当初、現地で工場建設反対に遭遇するなど、幾多の試練を経験。それは後述するとして、業務用と家庭用を手がける二本立て構造は、時代の変化、環境の変化に柔軟に対応できる仕組みでもある。
コロナ禍の時は、外食が避けられ、調味料の需要は家庭用に殺到。いわゆる〝巣ごもり需要〟というもので、当時、「小型で簡便系の調味料の人気が一気に高まった」(中野氏)という。
スーパーマーケットの食料品棚から、家庭用しょう油などが一時期品薄になるという場面もあった。このように、時代や環境の変化で自分たちが取り扱う商品へのニーズも移り変わる。
コロナ禍が明けた今、そうした変化を中野氏はどう捉えるのか。
「例えば、今は人手不足が深刻。食の分野でいえば、人手がないので、簡単においしいものができるニーズが高まっています」
中野氏は、人手不足から来る食の課題についての認識をこう示し、さらに、商品の付加価値をどう高めていくかについて、次のように語る。
「もう1つは、物価高の影響もあって、レストランもなるべく単価を上げる料理をつくりたいと。そのためには、同じものをただ値上げするのではなくて、業界では少しリッチ化と言っていますけど、高級食材を使ったリッチ化商品を出すという大きな流れが出てきています。そういったニーズに応えて、例えば『サクサクしょうゆ』というフリーズドライ醤油を使用した商品を家庭用・業務用で販売していて結構引き合いが強いですね」
原材料価格が上昇し、製造コストが高くなる中で、収益を確保しなければならない。つまり付加価値の高い商品を開発していかなくてはならない時代。
「やはり、今までと違うもの、他社さんではあまりやっていないようなものを手がけていかないと、コストが上がっていく中では経営は難しくなる」という認識を示す中野氏。
商品価値の追求、そして値付けのあるべき姿は?
商品の値付けをどう進めるか─。今、全産業界がこの命題に直面。〝失われた30年〟の間に賃金は上がらず、物価全体が低迷。いわゆるデフレ経済に陥り、経済は萎縮を続けた。
これではいけないと、脱デフレが合言葉となり、日本銀行も物価上昇率の目標を『2%』に置き、金融政策を運営してきた。
GDP(国内総生産)で見ると、日本は昨年ドイツに抜かれて3位から4位に転落。近くインドにも抜かれそうだとして、今、官民一体で、物価上昇2%程度で「安定成長を図る」という機運は高まる。
賃上げも昨年は平均で3.6%上昇、今年度は5%程度のアップで推移。賃上げで国民の所得アップを図り、個人消費増で経済全体の成長につなぐという好循環論の実践だ。
しかし、一筋縄ではいかないのが現実。企業は、従業員の賃上げの原資を確保するために、製品価格改定(値上げ)に動いてきた。
コロナ禍が明けて活況が戻る外食産業を見ると、原材料や人件費上昇が続く中、インバウンド(訪日外国人)客向けに、高単価なメニューを開発する例が相次ぐ。国内の既存客には従来の価格か、それなりの価格引き上げを行うにしても、インバウンド客向けよりは安い価格という二重価格制を導入する所もある。
一部のインバウンド客からは、「フェアではない」との反発もあるが、欧州などでも先行例があり、この二重価格制導入に前向きな外食産業関係者は少なくない。最近の円安もこうした流れを加速させる。
このような動きは、ホテルや旅館など宿泊関係にも広がりそうな気配だ。
キッコーマン社長・中野氏はこの値付け問題をどう捉えているのか?
「値付けに関しては2年前(2022)に、当社も14年ぶりに価格改定をしました。コロナ禍に海外でやはり需要が高まって、逆に供給がなかなか上手くいかないということもあって、いろいろなものが値上がりした。穀物も上がったし、それからロシアの話でエネルギー価格も上がった。さらに日本は円安が追い打ちになった。だからメーカーとしては価格改定しないと事業が継続できない状況になりましたので、価格改定を実施したという経緯です」。
先述のように、〝失われた30年〟の間は、値上げなどはとてもできず、原材料価格アップ分を、商品の中身を〝減量〟するなど、いろいろな手を打って何とかしのいできたのが現実。
価格に敏感な消費者と毎日接するスーパーマーケットなど小売り関係者は、一連の価格改定に当初、相当な抵抗感を示した。しかし、コロナ禍という非常事態の中での世界規模での原材料価格の上昇であり、関係者と何度も対話を積み重ね、価格改定を実現した。
さらに、ウクライナ戦争などがエネルギーや原材料価格の上昇に追い打ちをかけた。そのあおりを受けて、キッコーマンの価格改定交渉もこの2年間で10回程度にも及んだ。それほど原材料価格が上昇したということである。
円安にはどう対応?
今、値付けが日本企業の重要な経営課題になっているということだが、これは賃上げ問題にも直結するテーマだ。特に、個人消費はGDPの51%強を占め、その動向は日本経済の成長の可否を左右する(ちなみに民間の設備投資の対GDP比率は約17%)。
マクロ的に見ても、賃上げをして個人の消費を増やすことで好循環をつくり、経済を成長させていくことが重要。
「やはり賃金が上がっていかないと、経済が回っていかないというのはありますね」と中野氏も語り、「それで、今がまさに正念場だと思います」という現状認識を示す。
原材料価格の動向についてはどうみているのか?
「今年は原材料の相場自体は比較的高い所まで来て、安定している感じですね。ただ、為替がまた動いていますので、これがなかなか見通せない」と中野氏。
1ドル約160円という為替水準(6月末現在)。37年半ぶりの円安水準ということだが、これも日本の国力低下を示す現象だ。つい12年ほど前、安倍晋三政権の経済政策・アベノミクスがスタートする直前は、1ドル79円台の円高水準で、「円高による不況を食い止めねば」という声が高まっていた頃とは天地をひっくり返した位の環境変化である。
かつては、円安は輸出で稼げるということで歓迎されていたが、今は日本企業のグローバル化や海外での生産拠点強化が進行するなど、産業構造・経済構造の変化が進み、そう単純ではなくなった。国際収支でいえば、貿易収支で稼ぐ時代から、所得収支(海外活動で得られる利子や配当収入など)で成長する時代へと移り変わっている。
「米国での商売には為替はあまり影響ない」
キッコーマンはこの10年で海外での売り上げを2倍に拡大。今、全売上高の75%は海外であり、全利益の80%を海外事業が占めるという経営構造だ。
ちなみに、2024年3月期の売上高は約6608億円、経常利益は約667億円、税引前利益は約756億円という実績。『食の喜びを地球全体で』という命題を実践しての結果である。
中野氏がグローバル経営の仕組みについて語る。
「海外は基本的には現地の原料で、現地で作って、現地で売ると。ですから、海外の事業は為替の影響をあまり受けません。ただし、ドルやユーロなどを連結決算時に円に換算するので、円安の場合(利益の数字が)膨らみます。そういう影響はあるが、商売自体にはあまり影響はない」。
中野氏は円安が事業そのものにマイナス影響を及ぼすことがない経営の仕組みを構築していると説明しつつ、ただし、「日本は輸入原料を使っています」と次のように続ける。
「日本は、輸入原料が多いので国内の事業には影響があります。直接輸入する原料もあるし、包装材料にしても基本的には石油ですから、包装材料メーカーからは値上げさせてほしいと要望がきます」
「今まで我慢してきた資材メーカーさんも我慢できなくなって、みんなジワジワと上がってきたということですね。取引価格改定は大体、一巡したところと今は受け止めています」
同社の株価は1863円強(6月28日現在)。市場での時価総額は1兆8065億円強。市場の評価はPER(株価収益率)で30.78倍、ROE(自己資本利益率)は12.52%と高い。市場で高評価を受ける水準は、PERで約18倍、ROEは8%~10%とされる。いずれも高い数値をあげている。
また、資産の有効活用度を見るPBR(株価純資産倍率、1倍以上の数値が高評価とされる)は3.61倍と、これもまた高い。
今は、経営を取り巻く環境がまさに千変万化する時代。その中をどう生き抜くかという命題を経営者は背負う。現在の混沌とした状況に、どう対応するかということについての市場の一定の評価である。
米国で3番目の工場新設
海外展開をさらに力強く
市場との対話─。しょう油は日本の風土から生まれた調味料。また、しょう油は地域の文化や風土と深く関係しており、例えば九州では甘口のしょう油が好まれる。
「はい、日本各地にしょう油屋さんがあって1千軒を数えます」
しょう油が全世界に広がった現在、キッコーマンは100カ国以上でしょう油を販売している。日本生まれのしょう油がなぜ、ここまでグローバルに展開できるようになったのか?
「基本的にうちがやってきたのは、その国の地元の方が日常召し上がる料理に、うちのしょう油を使っていただこうと。現地の方と料理の研究家の方たちと一緒にメニューを作って、それを提案してきたという歴史です。それがうまくいった」
海外で日本食を普及させようとしても、現地では日本食の食材を揃えるのは難しく、作り方も分からない。それならばと、現地の人が普段やるバーベキューで、しょう油を使ってみませんかと勧めたり、肉の照り焼きはどうかと提案した。
「照り焼きでいうと、昔は日本では魚の照り焼きでした。それが米国では魚を売ってないので肉の照り焼きになって、これが非常に受けた。それが日本に逆輸入されたと。食が交流して、新たな形になって、また戻ってくる。面白いですよね」
海外での売り上げはまだまだ伸びるということで、同社は米国で3番目の工場を建設中。
欧州、アジアも積極開拓
海外市場でのしょう油・調味料の販売はまだまだ伸びるという同社の見通し。欧州市場向けに『KIKKOMAN』ブランドのしょう油を販売しようと、オランダ・サッペメアに本格工場を建設、1997年から生産・販売を開始して27年が経つ。
近隣のロッテルダムは、有力な物流・輸送拠点であり、ここから英国、ドイツ、フランスなどをはじめ、中・東欧や北欧、さらには中東地区を視野に事業を展開。
この欧州全般と中東地区の市場としてのポテンシャル(可能性)について、中野氏が語る。
「この地域は、まだ米国の4分の1位の実績。ですが、ポテンシャルとしては米国と同じ位まで行くだろうということなので、10年20年先にはきっと同じ位に成長すると期待しています。伸び率は米国が5%なら、欧州地域は10%で、倍の伸びです」
そして、近年成長が著しいASEAN(東南アジア諸国連合)地域。インドネシア、タイ国をはじめ、人口が多く、成長し続けている国が地域には多い。
「はい、これらの国々は所得水準も上がって、スーパーマーケットなども整備されると、新鮮な食材が地元の方々に行き渡り、われわれのしょう油がマッチしてきます」
中野氏は、「本当のしょう油って、新鮮な食材と相性がいいんです」と語る。
個々の成長が会社の成長につながる!
中野氏が社長に就任したのは、2021年6月。それから3年が経つ。コロナ禍の3年と重なるが、この間、内外への出張ができなかった。その代わりに、「社内のミーティングを積極的にやろう」と、月に2回各部門の所属長クラス約15人を集めて、徹底したディスカッションを行ってきた。
会社の方向性は、『グローバルビジョン2030』に示されている通り、「地球を食の喜びで満たす」ということ。「そのわれわれの目指す方向に向かって、それぞれの部門が自分たちはどんな役割を担い、どういう事をやっていくか、自分たちのビジョンをつくってくれということです」と中野氏は語る。
昨今、会社と個人の関係において、エンゲージメント(Engagement)という言葉がよく使われる。
〝誓約〟、〝約束〟、〝婚約〟などの意味を持つエンゲージメントという言葉だが、企業経営では従業員の会社に対する〝愛着心〟、〝愛社精神〟、〝思い入れ〟といった意味で使われる。
「はい、個々の思いと会社の進む方向が重なる所にやり甲斐というものが出てくるんだろうなと。個人が成長して、その力を発揮できるようにして、会社全体も成長していくと。社会に貢献できるという所に、やり甲斐を感じてほしいと。やはり1人ひとりが当事者意識を持って考えていくことが大事」
個人の成長が会社の成長につながる経営にしていきたいという考えを中野氏は示す。
思えば、キッコーマンの歴史は古く、千葉県野田市に地元のしょう油、味噌などの醸造家8家が集まり、1917年(大正6年)に野田醤油を設立したのが会社の始まり。茂木家(6家)、高梨家、堀切家の計8家が大同団結して醸造会社を設立。淵源をたどれば、高梨兵左衛門と茂木七左衛門が寛文年間(1660年前後)に千葉・野田の地でしょう油や味噌をつくり始めたといわれる。天下分け目の関ヶ原の戦いから約60年後、今から360余年前のことである。
会社組織としてスタートして107年。この間、第1次世界大戦終了後の大正年間には、各地で労働争議が起き、同社でもストライキが起きた。そうした試練の中で、当時の経営陣は、「時運に竿さす者は栄え、逆らう者は亡ぶ」という言葉を掲げ、企業の社会性(パブリック精神)を追求した。
何より、創業家8家の各家が、己を律する家訓を持っていた。例えば、茂木家は『徳義は本なり、財は末なり、本末を忘れてはいけない』といった家訓。規律を厳しくし、『使用人を優遇せよ』といった文言もあった。
そして戦後は1957年(昭和32年)に米国市場での販売に乗り出し、以来、グローバル化戦略を推進。先進的な経営を取り入れるDNA(遺伝子)が今も受け継がれている。
国と国、人と人をつなぐ
国全体の生産性をいかに高めていくか─。これは今の日本の最大課題。同社名誉会長(取締役会議長)である茂木友三郎氏(1935年生まれ)は現在、日本生産性本部会長も務める。
資本の蓄積、労働量の拡大、最先端技術の投入などの全要素生産性の乗数で生産性は決まる。人口減、少子化・高齢化という逆風の中で、生産性をいかに上げ、グローバル競争を生き抜くかという今日的命題である。
茂木友三郎氏は、日本生産性本部会長として、経済人として、「リスクを取らなければ、新しい価値は生まれない」と叱咤激励してきた。
米国進出から50年余。世界中が分断・分裂の方向に向かう中で、国と国をつなぎ、人と人をつなぐのも、経済リーダーの使命であり役割である。
「わたしたちは平和産業です」─。中野氏は力強く、自分たちの仕事の役割を語る。
日々の食生活に欠かせないしょう油・調味料の領域で、世界中をつなぐ仕事は今日も続く。