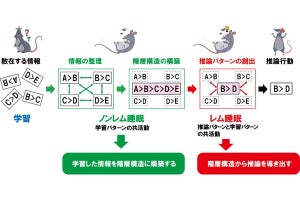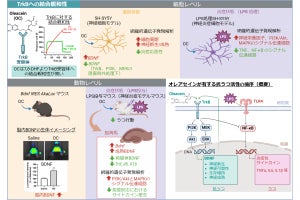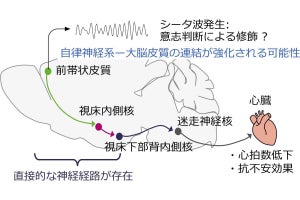九州大学(九大)は6月26日、ヒトの脳における複雑な神経細胞の配線を解析するため、神経細胞を7種類の蛍光タンパク質の組み合わせによって多色標識し、大半のヒトの目では識別不可能な4原色以上の世界も識別できるAIを用いて、神経回路のつながりを自動解析する手法を開発したと発表した。
同成果は、九大大学院 医学研究院の今井猛教授、同・マーカス・ルーウィ助教(研究当時)、同・藤本聡志助教、同・馬場俊和大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
脳の膨大な数の神経細胞は、多くの軸索や樹状突起を伸ばしてネットワークを形成し、それぞれが数千から数万に及ぶ神経細胞と情報のやり取りをして演算を行っている。つまり、脳の情報処理について理解するには、多数の神経突起がどのように配線しているのかを明らかにする必要がある。
複雑に絡まり合った神経細胞の配線の様子を識別しやすくするため、3種類の蛍光タンパク質の組み合わせを用いて、神経回路の多色かつ高輝度で標識できる「Tetbow法」を開発したのが研究チームだ。しかし同手法では、中間色を含めてもせいぜい数十色までしか生み出せないため、複雑な神経回路を識別するためには不十分だったという。
そこで今回の研究では、蛍光タンパク質の種類を増やすことで、もっと多くの神経細胞を識別することが検討された。しかし、大半の人は3色色覚であり(極めて希に4色色覚の人もいる)、3原色の世界までしか識別できないことから、今回の研究では4原色以上の世界も識別できるプログラム(AI)も併せて開発することにしたとする。
まず多色標識については、Tetbow法が拡張され、7種類の蛍光タンパク質の組み合わせで神経細胞の突起が標識された。蛍光の波長が近い色素同士では、しばしば蛍光の漏れ込みが問題となるが、今回は数学的手法の「リニアアンミキシング」を用いて、漏れ込みを限りなくゼロにすることが実現されたとした。
-
Tetbow法が拡張され、7種類の蛍光タンパク質を用いた超多色標識が実現された。個々の蛍光タンパク質のシグナルは、リニアアンミキシングで分離可能。個々の神経細胞はこれらの蛍光タンパク質をランダムに発現するため、理論上は127色、中間色も考慮すれば数百から1000通りの色の組み合わせを作り出せる。ただし、人間は3色色覚であるため(さらにモニタや印刷物も3原色で表現されていることから)、7色の重ね合わせ画像はカラフルには見えない(出所:九大プレスリリースPDF)
次に、色の似ている・似ていないを数学的に表現し、コンピュータに解析させるための手法が検討された。さまざまな色について、赤、緑、青のそれぞれに分解して輝度を測定し、全体の輝度を揃えてやると、色情報は平面上に展開することが可能だ。数学的に「色が似ている」とは、この平面上での距離が近い、「似ていない」とは、この平面上での距離が一定の距離(閾値)以上であると言い換えることができ、同様の解析は4原色以上でも行えるという。
そこで、コンピュータシミュレーションと実際のTetbow標識法を用いて、標識する蛍光タンパク質の種類が3種類(3原色)と、7種類(7原色)の比較が行われた。その結果、シミュレーションでも実験データでも、7種類の方が、識別能が飛躍的に向上することが確認された。たとえば、3種類の蛍光タンパク質で標識した神経細胞同士の識別能は64.5%だったのに対し、7種類の蛍光タンパク質で標識した神経細胞同士の識別能は99.7%だったとする(閾値0.2の場合)。
-
色の類似度の数学的な定義(例は3原色)。色について評価する上では、輝度情報を揃える必要があるため、赤・緑・青を合わせた輝度を1にそろえる(規格化)。すると、すべての色は球の表面に展開される。ここで、色が近いとは、平面上の距離が近いということになる。この表面上で一定の距離以上に離れている色同士は別の色であると判断する。同じ神経細胞に由来する神経突起断片は、同じ色の組み合わせで標識されているため、それぞれの色情報は、この表面上で近くにまとまって分布すると推測される。dCrawler法を用いると、距離が一定の閾値未満のものをグループ化できる。QDyeFinderでは7原色で表現された神経突起の色情報を同様の手順でグループ化し、同じ神経細胞由来の神経突起同士をクラスター(1つの神経細胞)としてまとめることが可能(出所:九大プレスリリースPDF)
続いて、色情報に基づいて神経突起の自動同定を行うプログラムの開発が行われた。まずそのために、色情報などの多次元データを閾値に応じて分類できる新たなプログラム「dCrawler」が開発された。これは、機械学習の一種の「教師なし学習」であり、今後さまざまな応用が期待されるという。
-
QDyeFinderによる神経突起の自動同定。QDyeFinderにおいては、7種類の蛍光タンパク質の組み合わせによって標識された神経細胞の蛍光画像(画像1)から神経突起を同定し、色情報だけを使って同じ種類の神経細胞由来の神経突起がグループ化された。ここでは4例のみ示されている。ヒトが手動で同定した結果との比較では、おおむね同程度の精度で同じ神経細胞由来の神経突起を同定できることが確かめられた(出所:九大プレスリリースPDF)
そして、神経突起の色情報を取得した上で、dCrawlerによる分類が実施された。そこからさらに、同種の神経細胞の神経突起を自動同定するプログラム「QDyeFinder」が開発された。従来、神経細胞の配線の様子を解明するには、人間が神経突起を1本1本手動でトレース(追跡)する必要があったが、同プログラムではすべてのステップの自動化に成功したとする。神経突起を手動でトレースした結果と、QDyeFinderが自動同定した結果の比較が行われた。すると、おおむね同程度の精度であることが明らかにされた。機械学習を駆使した既存の神経突起トレースソフトと比較しても、QDyeFinderの方が遙かに高い精度で神経突起の同定ができることも確認されたとした。
QDyeFinderを用いて、大脳皮質や嗅皮質など、いくつかの脳領域の標本を使って神経配線の自動解析が試みられた。その結果、たとえば大脳皮質では、色識別によって、ヒトの目では不可能な300種類もの神経突起を自動識別できたという。
-
高密度標識した神経回路における神経突起の自動同定。7種類の蛍光タンパク質を用いて大脳皮質を高密度かつ超多色に標識した脳標本を用いて蛍光画像を撮像し、QDyeFinderによって神経突起の自動同定が行われた。この例では、302種類の神経突起が自動同定されている(出所:九大プレスリリースPDF)
QDyeFinderを用いることで、神経回路の複雑な配線を効率良く解析できるようになった。発達・学習過程で神経回路がどのように変化するのか、脳の疾患で神経回路の配線にどのような異常が生じるのかなどの研究が発展することが期待されるとしている。