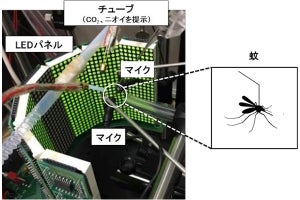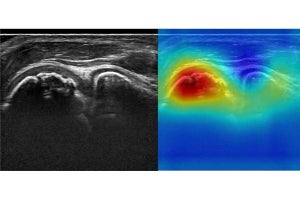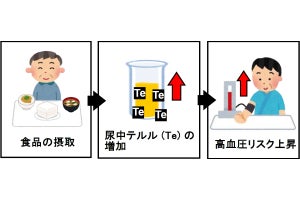豊橋技術科学大学(豊橋技科大)は6月6日、表情と「記憶色効果」(特定の物体に関する典型的な色の知識(記憶色)が実際の色の認識に影響を与える現象のこと)の関係を解明し、表情が顔に対する記憶色のレベルにまで影響を与えることを突き止めたと発表した。
同成果は、豊橋技科大 情報・知能工学系 認知神経工学研究室の長谷川友哉大学院生、同・田村秀希助教、豊橋技科大 情報・知能工学系 視覚認知情報学研究室の中内茂樹教授、豊橋技科大 情報・知能工学系 認知神経工学研究室の南哲人教授の共同研究チームによるもの。詳細は、ヒトをはじめとする生物の視覚機能に関する全般を扱う学術誌「Journal of Vision」に掲載された。
顔の作りは、個人を識別するための非常に重要な特徴であり、今やスマートフォンにもユーザー認証のために顔認証の仕組みが搭載されている。顔が見えなくても電話などで音声が伝われば、家族や友人・知人など、既知の人物について判別がつくことは多い。しかし、画像や音声データのない映像で、個人の顔に加工がほどこされていたり、後ろ姿だったりすると、個人を特定することは容易ではない。
そのヒトの顔面は、毛が生えている部分も少ないため(男性は髭を生やすことができるが)、肌の色味の変化がわかりやすい。ヒトの画面の血液流量は感情(や体調など)の影響を受けやすく、怒ったり恥ずかしい思いしたりをすれば赤くなるし、恐怖を感じたり緊張したりすれば血の気の引いた印象になる。相手の心の動きや機嫌を量る意味合いの「顔色をうかがう」という慣用句があるように、顔の色(の変化)は他者の感情を読み取る上で重要な役割を果たしている。
しかも近年の研究から、ヒトは、同一人物の同じ表情の画像を2つ並べたとしても、より赤っぽい顔色をしている方を紅潮している怒り顔として捉えやすいなど、顔の色が表情判断に影響を与えることがわかってきている。
しかし、日常的な顔色の記憶や、特定の物体に関する典型的な色の知識によって形成される記憶色(この場合は顔の肌の色)までもが表情によって異なるのかは、よくわかっていなかったという。そこで研究チームは今回、記憶色によって色の認識が変化する現象である“記憶色効果”に着目し、表情や顔色の異なる顔画像を使用して、心理物理実験を実施したとする。
今回の実験内容は、実験対象者が、呈示された顔画像がどちらの顔色に見えたか、「典型色」と「反対色」の2つから選択するというもの。典型色とは、観測者が物体に対する知識として所持する色のことであり、日本人の顔の場合は、もちろん個人差はあるものの基本的には肌色を中心とした色を指す一方、反対色とは、色相的に典型色の反対に位置する色のことである。実験には異なる顔色を持つ怒り顔・中立顔・恐怖顔の3つの表情画像が使用され、周囲の明るさによる色の見え方への影響を受けないように、実験は一定の明るさにコントロールされた暗室内で行われた。
そして実験の結果、実際には無彩色(灰色)の状態である怒り顔や恐怖顔が、無彩色な中立顔よりも、典型色である赤黄色に色付いて見えやすいことがわかったという。研究チームによると、怒り顔と恐怖顔の記憶色が、中立顔よりも赤黄色が高彩度な顔色であるため、無彩色な顔色が典型色に色付いて見えやすかった可能性が考えられるとのこと。これは表情が記憶する顔色を偏らせ、想起する顔色が実際に目にしたときよりも赤黄色が高彩度な顔色だったという先行研究の報告と似ていたという。
今回の研究成果は、表情が顔に対する記憶色のレベルにまで影響を与えることを初めて明らかにした。記憶と注意は密接な関係にあることから、研究チームは今後“赤い怒り顔”に対し、通常の怒り顔や赤い中立顔よりも注意が向きやすいのかを検証し、なぜ表情によって記憶する顔色が異なるのかという仕組みを、より深く理解することを検討していくとしている。