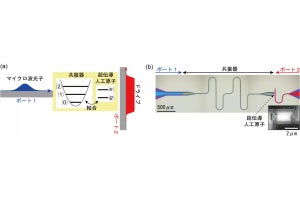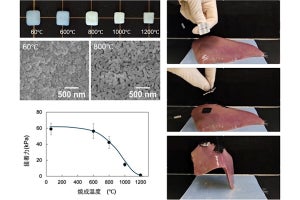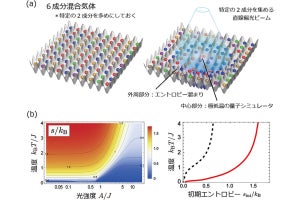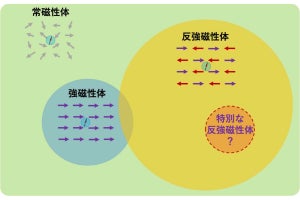北海道大学(北大)は5月24日、酵素の加水分解作用を制御することで、性質とサイズ(約10~1000nm)の揃ったナノ材料「メゾスコピック粒子」を簡便に作成する新規手法「生体触媒ナノ粒子成形(BNS)法」を開発したことを発表した。
同成果は、北大 電子科学研究所の高野勇太准教授(同・大学大学院 環境科学院兼任)、同・ヴァスデヴァン・ビジュ教授、同・大学大学院 環境科学院のルマナ・アクター大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行するナノサイエンスとナノテクノロジーに関する全般を扱う学術誌「Nanoscale Horizons」に掲載された。
メゾスコピック粒子は原子よりは大きいが、一般的な物質よりは遥かに小さい、特定の大きさの範囲にある粒子や集合体のことを指す。具体的なそのサイズは、10~1000nmほどだ。同粒子はその特殊なサイズのため、今までの材料とは異なり、粒子の大きさによって光や熱、電気の伝導性、化学反応の速度などが変わるなど、ユニークな性質を有していることがあるという。医療応用においても、同粒子は血中滞留性が良いことが知られており、効果的な薬の開発基盤技術として注目されている。
しかし、従来のメゾスコピック粒子作成法は、高い技術力が必要な精密ポリマー合成やリソグラフィ法、あるいは均質な粒子サイズの制御が難しい物理破砕法(ボールミリング法など)が主流だった。そこで研究チームは今回、粒子サイズの揃った同粒子を簡便に作成する方法として、有機分子から無機材料まで多種多様な物質を原料として利用可能なことから、酵素の分解作用を活用した手法を開発することにしたという。
まず、量子ドットまたは有機分子同士をコア部分とし、酵素での分解が可能なペプチド「オリゴリシン」を連結部位として連結させたマイクロメートルサイズの構造体が作製された。この構造体は溶液にほとんど溶けずに沈んでしまうが、ここに酵素を加えることで連結部位が分解され、小さな粒子になるのである。
一般的に、酵素分解反応は分解可能な部位がなくなるまで終わらないので、研究チームでは当初、構造体が極めて小さくなることを予想していたとする。しかし、連結部位の酵素分解反応が途中で止まり、粒子サイズの揃ったメゾスコピック粒子が得られたという。これは、コア部分の量子ドットまたは有機分子が酵素による分解作用を物理的に阻害し、反応が途中で止まってしまうためと推測された。
今回の研究で連結部位に用いられたオリゴリシンは、アミノ酸の「リシン」が多数連結したものであり、生物実験で最も多用されているタンパク質分解酵素の1つである「トリプシン」によって分解される。BNS法による粒子生成のメカニズムを解明するため、オリゴリシンを連結部位、コア部位に周辺環境に応じて光吸収特性などが変化する「ポルフィリン分子」としたメゾスコピック粒子が合成され、その光応答などが調べられた。その結果、同手法を適用するのに必要な連結部位の長さや、連結部位の長さの調整によってコア部位の光吸収能力や光をトリガーとした活性酸素発生能力の制御が可能であることが突き止められたとした。
さらに、BNS法はオリゴリシンとトリプシンの組み合わせだけでなく、「ヒアルロン酸」とその分解酵素「ヒアルロニダーゼ」の組み合わせなど、多様な酵素分解性基質と分解酵素の組み合わせに幅広く応用できることも確認された。
また、オリゴリシンが連結部位に、発光性量子ドットがコア部位に用いられたところ、生体内での血中滞留性が良いとされる約80nmサイズの量子ドット集合体によるメゾスコピック粒子「ms-QD」の合成に成功したという。同粒子は、光照射により自身の居場所を知らせる光ラベルとして機能する上、オリゴリシンは細胞に取り込まれやすいという性質を持つ。研究チームでは、それらの性質を利用することで薬物キャリアとして機能することを期待し、同粒子に光がん治療薬候補の「rTPA」を載せて、生体組織モデル(スフェロイド)内における性能を調べることにしたとする。その結果、同粒子は効果的に光ラベルとして機能した上で、rTPAの光殺がん細胞効果を発揮させる薬物キャリアとしても働くことが実証されたとした。
このようにBNS法は、さまざまな酵素分解性基質と有機分子あるいは無機材料との組み合わせに応用できることから、ナノ材料開発に膨大な数の選択肢を提供することができるという。さらに、同手法は主に水中で作用する酵素を使うので、工業化において有機溶媒の利用を抑えたサステイナブルなナノ材料作成方法となり得るとしている。