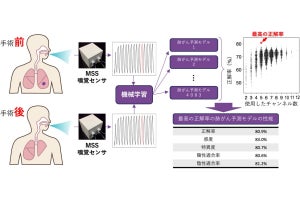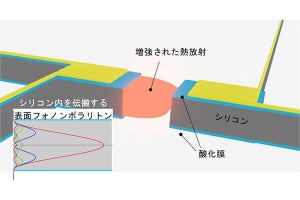筑波大学は5月10日、走査電子顕微鏡(SEM)とフェムト秒レーザーを組み合わせ、デバイス材料内の電位変化を高い時間分解能で計測する新手法を開発し、それを用いて、半導体「ガリウムヒ素」(GaAs)基板上に形成した光伝導アンテナデバイス上の金属電極周囲の電位変化を計測、43ピコ秒の時間分解能でSEM画像として観察することに成功したと発表した。
同成果は、筑波大 数理物質系の藤田淳一教授、同・嵐田 雄介助教らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するフォトニクスに関する全般を扱う学術誌「ACS photonics」に掲載された。
現在、次世代携帯電話のBeyond 5Gや6Gに向けての研究が進められている。その実現には、デバイスの情報処理に要する時間をより短くし、なおかつ低消費電力化することが強く望まれている。その方法の1つがデバイスサイズの小型化だが、微細化・高速化が進展した結果、従来の電気的な測定方法では、デバイスの動的特性を精密に測定することが困難な状況になりつつある。そのため、高速で動作する電子デバイスの局所電位を、より正確かつ直接的に観察できるような新手法の開発が求められていた。
ナノスケールの材料などの撮影手段であるSEMは、対象試料に電子線を照射した際に放出される二次電子の計測を行い、電子線の照射位置を走査した時の二次電子の強度分布から、試料の形状や電位分布の画像が得られる仕組みだ。これまで研究チームでは、数10ピコ秒という極短時間だけ照射電子線に多数の電子を含むようにパルス化し、瞬間的な試料の状態を反映したSEM画像を取得する「走査型超高速電子顕微鏡法」(SUEM)を開発済み。そこで今回の研究では、SUEMを電子デバイスの性能評価に用いることを試みることにしたという。
SUEMの鍵は、電子線を極短時間だけ生じさせることであるため、フェムト秒レーザーとして、時間幅300フェムト秒の近赤外線パルスが用いられた。同光をビームスプリッターで分割し、片方を非線形光学結晶を用いて紫外線パルスへと波長変換し、SEMの電子源へと照射すると、紫外線によって電子源の先端で光電効果により電子パルスが発生する。同パルスが、電子源の下方に設置された直径0.7mmの穴が開いたミラーを通過して試料まで到達し、瞬間的なSEM像を取得することができるという。
また、試料に変化を引き起こすための光として、非線形光学結晶による波長変換により試料が吸収しやすい可視光パルスが用いられた。同光にはあらかじめ光学遅延「t」が付与され、電子パルスより早く試料に入射させたとする。これにより、光励起からtだけ時間が経過した後のSEM像を取得することができるとした。
-
(a)開発された実験装置の概要図。レーザー装置、波長変換を行う光学系、SEMで構成。(b)SEM装置内に置かれた穴開きミラー(穴の直径0.7mm)。紫外線パルスを電子源の方向に反射させ、電子源で生じた電子パルスを中央部の穴に透過させる。(c)時間分解SUEMの概念図。電圧(Vb)が印加された光伝導アンテナデバイスの状態を可視光パルス(緑色矢印)で変化させ、tだけ時間が経過した後に光電子パルス(黄色矢印)を照射し、二次電子の量を計測することで、瞬間的に変化するSEM画像を取得する仕組みだ(出所:筑波大プレスリリースPDF)
まず、試料として光伝導アンテナデバイスが作製された。GaAs基板上に金のクシ型電極が対向して配線されており、左側を陰極、右側を陽極として通常のSEM観察を実施。同デバイスは光の照射によって導通するスイッチとして知られており、電気的な操作によるスイッチよりも高速に動作する。両極が同電位の場合、電位が等価なので陽極も陰極も同じ明るさに見えるが、3Vの電位差を印加すると、陽極に対して陰極が明るくなっている様子が観察された。つまり、陽極と陰極の電位が異なることを反映して二次電子の測定量が変化していたという。
-
(a)試料に用いられた光伝導アンテナデバイスの画像。GaAs基板上に金できたクシ型の陽極と陰極が配置されている。(b)陽極と陰極を同電位(Vb=0V)に置いて測定されたSEM画像。(c)Vb=3Vとして測定されたSEM画像。陰極から多くの信号が得られているため明るく見える(出所:筑波大プレスリリースPDF)
次に、同デバイスに対し、SUEMによる時間分解観察が行われた。可視光パルスが照射されると、半導体基板が光を吸収し、電気抵抗が減少する。すると、電極間に充電されていた電荷が流れ、陽極と陰極は短い時間の間だけ同じ電位になる。この時の様子が、可視光パルスの照射からの経過時間ごとに観察が行われた。すると、可視光パルスの照射前(t=ピコ秒)では、まだ充電された状態であるため陰極が明るく見えるが、照射した瞬間から充電が減り、50ピコ秒経過後には両極が同じ信号強度を示し、充電が完全に解消したことが確認された。
-
光パルスと電子パルスの遅延時間を(a)-50ps(ピコ秒)、(b)0ps、(c)50ps、(d)625psと変化させた際の時間分解SUEM画像。(a)の黄色の範囲の断面図が(e)であり、同様にに、(b)と(f)、(c)と(g)、(d)と(h)が、それぞれ対応。(i)陰極の電位の遅延時間依存性の結果(出所:筑波大プレスリリースPDF)
また、光照射から625ピコ秒が経過すると陰極がわずかに明るくなったという。これは、基板が電気を流さない半導体に戻り、再充電が始まったことを意味しているとした。陰極部分の電位の時間変化がプロットされたところ、光照射から43ピコ秒で充電が解消され、その状態が500ピコ秒ほど継続した後に、再充電が始まる様子を連続的に捉えることに成功したとする。
SUEMを用いることで、電子デバイスの電位分布の超高速変化を可視化し、従来の測定方法よりも直接的に、デバイスの動作を理解することが可能となる。今後、電子デバイス開発のさらなる加速や、新しい原理のデバイスの創出などへの応用が期待されるとしている。