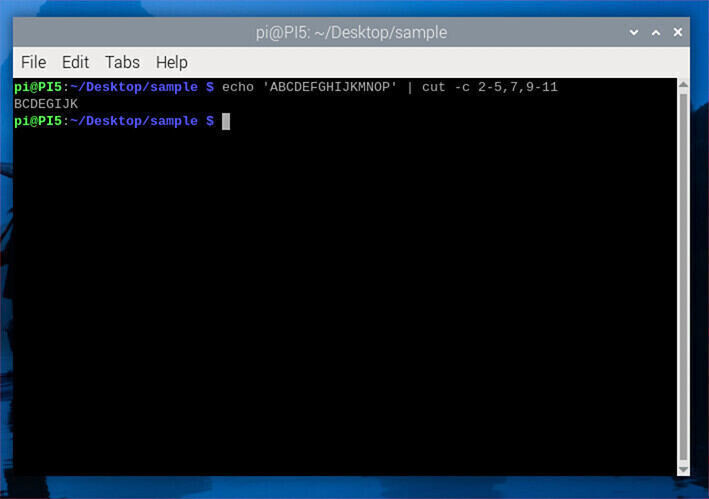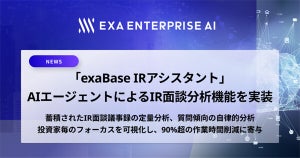自動車業界を巡るCASE(つながる・自動運転・共有・電動化)の波。中長期的にはガソリン車がなくなり、電気自動車(EV)が主流になると見られている。そこに危機感を抱くのは部品メーカーだ。その1社がオイルシールで国内シェア7割を占めるNOK。普段は目にすることのない同社の製品だが、「異なる部材同士をくっつける」という80年以上の歴史の中で培ってきた技術をテコに生き残ろうと次なる一手を繰り出している。
車1台に200点の部品が搭載
「当社は総合部品メーカーとして各産業を下から支える位置付けだが、視点を変えれば『エッセンシャル・コア・マニュファクチャリング(必要不可欠にして中心領域を担うモノづくり)』を行う当社が中心となって、業種の枠を超えた様々なニーズに対応し、自分たちの可能性を広げていける存在とも言える」─。NOK社長CEOの鶴正雄氏はこのように自社の立ち位置を話す。
NOKは1941年に神戸で創業した日本初のオイルシールメーカーだ。当時の社名は「日本ベアリング製造」。主力製品であるオイルシールとはオイル(油)をシール(封じる)するもので、機械部品の潤滑油や水、ガスなどの漏れや異物の混入を防ぐ。自動車のエンジンなどに使用されている。
他にも0リング(密封に使用される断面が円形の環型をした機械部品)などのシール製品でも圧倒的な競争力を持っており、自動車1台当たりの同社の製品数は平均約200点とも言われている。今では祖業のオイルシールは国内シェア7割、世界シェア5割とトップを走る。
また、スマートフォンやタブレット端末、ウェアラブル機器などの電子製品に使われ、薄く、軽く、自由に曲がるフレキシブルプリント基板も世界3位の売上高を誇る。薄くて折り曲げやすいため、あらゆる電子機器のデザインの多様化や小型・軽量化に貢献している。
鶴氏が「80年余の歴史の中でとにかく技術を磨き続け、顧客の要求に合わせてチューニングし、それを大量供給してきた」と語るように、同社には品質と技術力を磨いて成長してきた歴史がある。同社の部品は完成品に組み込まれるため、人々の目に触れることはない。それでもオイルシールでは国内で14ある全自動車メーカーと取引をしており、生産個数は1日当たり6000万個で約29トンに及ぶ。
しかも、このオイルシールは自動車のみならず、建設機械や農業機械、電子機器、事務機器、住設機器などでも使用されている。また、「昔から地産地消を基本としていた」(同)こともあって、海外展開は1960年代から開始。現在の海外販売・生産拠点数は58社にのぼる。地域別の売上高も日本(約2315億円)のほか、中国(約2913億円)やその他アジア(約1270億円)と分散している。
足元では「自動車の生産台数の回復に伴い、国内を中心に販売が増加」(同)したこともあり、業績は好調だ。2022年度の売上高は約7100億円。23年度の売上高見通しも約7317億円と3%の増収、営業利益では195億円と27%の増益を見込む。そして鶴氏はトップライン(売上高)を上げることを重視し、創業90年に当たる31年度に売上高1兆円を掲げる。
ただ、鶴氏には危機感がある。「CASE」と呼ばれる100年に一度と言われる自動車業界の変革期に直面しているからだ。「変わらなければ時代に置いていかれる。企業としての存続も危うい」と危惧する。実際、同社のオイルシールはエンジンやトランスミッション(変速機)などに使われるため、EVなどの電動化が進めば、そのほとんどの出番がなくなる。
EVでも応用できる技術とは?
しかし、鶴氏は次のように生き残り策を強調する。「当社の技術のコアは界面制御(コントロール)の技術。異なる部材同士を〝くっつける〟技術はEVで使われるモーターや電池など数多ある。しかも、当社の顧客は日系メーカーがほとんど。海外の新興EVなどが今後の新規開拓先になる」
界面とは、混じらずに接触している2つの物質の境界を指す。NOKはこの境界を分析したり、制御したりする技術を発展させてシール製品やフレキシブルプリント基板をつくってきた歴史を持つ。そのため、EVに搭載されるモーターやインバーター(逆変換装置)、電池などでは高い放熱性に対応したシール需要が見込める。
すでに同社はEV向けのシール開発を進めつつも、EVの車載電池用樹脂ガスケット(シール材)を手掛ける子会社のエストーの北米展開やEV電池の電圧監視用フレキシブルプリント基板のメキシコ拠点にも投資。EV関連の新製品や水素関連の研究開発投資も進める考えだ。
鶴氏は高度成長の初期に社長などを務め、日本自動車部品工業会会長も務めた中興の祖・鶴正吾氏の言葉を胸に秘める。「一本足では会社は潰れる」─。この危機感を抱いた正吾氏は当時、世界でも進んだ密封技術を持っていた西ドイツ(当時)のカール・フロイデンベルグ社と資本提携し、技術の向上を実現。そして、自動車のみならず、エレクトロニクスや原子力といった事業領域の拡大を進めた。
この思想を受け継ぎつつ、鶴氏は環境という側面からも自社製品の可能性を感じている。「主力のシール製品は環境汚染物質の漏出を防ぐという特性を持っているため、製品自体が環境保護に貢献できる」からだ。東海の工場では100%再生エネルギー化が進んでいる。
このほど同社は新企業ロゴを含めた新コーポレート・アイデンティティ(CI)を発表した。「様々なグループ会社が設立されたが、各社が独自のCIを使用している現状に課題を感じていた」(同)からだ。クリエイティブディレクター・佐藤可士和氏の支援を受けて刷新した新CIの下で、グループ内の技術を掛け合わせた新たな製品やソリューションを提供できるか。同社の技術力が試される。