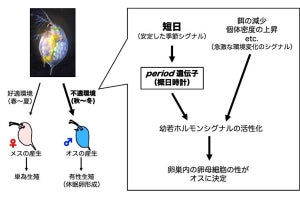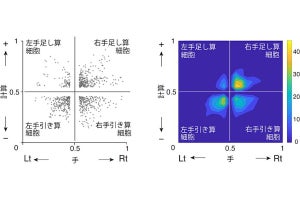信州大学(信大)は4月18日、日本列島の冷温帯落葉広葉樹林の優占樹種であるブナに強く依存した日本固有の昆虫である「ヒメオオクワガタ」の分布域を網羅する広域的な地域個体群を対象に、遺伝的分化などを解析した結果、同昆虫の遺伝的多様性は南西から北東にかけて低下する傾向が見られたと発表した。
また、同昆虫の日本海側と太平洋側の個体群間において、遺伝的分化が検出されたことも併せて発表された。
同成果は、信大 総合医理工学研究科の上木岳特別研究員(現・東京大学所属)、同・大学 学術研究院(理学系) 理学部 理学科 生物学コースの東城幸治教授/副学長らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本昆虫学会の刊行する公式欧文学術誌「Entomological Science」に掲載された。
ブナ林は、北海道南部から中部地方にかけての日本海側では、標高200~1400mにかけて広域かつ連続的に分布している。その一方で、中部地方の太平洋側から四国、九州では、その大半が標高1000m以上の山地に散在している。現在よりも寒冷かつ乾燥が厳しかったとされる氷期には、ブナ林はより南方の海岸沿いの「レフュジア」(生物が絶滅するような厳しい環境下で、局所的に生物が生き残った場所)に逃避し、日本海側と太平洋側に個体群が分断されたとされる。その後の間氷期には、東北日本の温暖化と湿潤化に伴いブナ林も北方へと分布を拡大した一方で、西南日本では高標高へと移動し、現在のような分布になったという。
ヒメオオクワガタは朽ちたブナ枯死木に卵が産み付けられ、幼虫はそれを食べて成長する。そのため、同昆虫の分布はブナ林の分布とよく合致することが知られている。そこで研究チームは今回、同昆虫の分布域を網羅する広域的な地域個体群を対象に、遺伝的分化や地理的な遺伝的変異パターン、および個体群動態を解析し、寄主であるブナの分布変遷が同昆虫の地理的な遺伝構造に及ぼした影響の解明に取り組むことにしたという。
-
ヒメオオクワガタの系統関係と地理的な遺伝構造。各分岐における値は支持率が、エラーバーは分年代推定の95%信頼区間が示されている。地図上の地点はサンプリング箇所が示されており、記号はSAMOVAに基づく遺伝構造の地理的まとまりを表し、系統樹右横の記号と合致する。系統解析の結果、クレードIでは中部地方太平洋側および四国西部の個体群からなるサブクレードI-aが検出された。SAMOVAの結果、クレードIIの九州北部および南部の個体群間で遺伝的分化が検出された。両クレード共に、日本海側と太平洋側の個体群間の遺伝的分化は約100万年前頃と推定された(出所:信大Webサイト)
ミトコンドリアDNA(mtDNA)の「COI」領域および「16S rRNA」領域の塩基配列に基づく系統解析の結果、ヒメオオクワガタは北海道、本州、四国の集団から成る系統(クレードI)と、九州の個体群のみで構成される系統(クレードII)の大きく2系統に分化していることが判明。九州の個体群を別亜種として扱う形態形質に基づく分類体系を支持する結果だった。
次に、系統解析および遺伝構造の地理的まとまりを検出する解析(SAMOVA)を実施すると、両系統共に日本海側と太平洋側の両個体群間で遺伝的な分化が認められ、ブナの系統分化と合致したとする。また、日本海側と太平洋側の両個体群は約100万年前に分化したと推定され、更新世の「氷期-間氷期」周期が4万年周期から10万年周期へと変化した時期と一致したという。これらの結果から、約100万年前以降の氷期にはブナ林がそれまでよりも長い期間、日本海側と太平洋側の沿岸部のレフュジアに分断され、ヒメオオクワガタの遺伝的分化も促進されたことが示唆されたとした。
さらに、ヒメオオクワガタのmtDNAのハプロタイプ多様度および塩基多様度は、西南日本から東北日本にかけて減少する地理的な傾向が認められ、ブナの地理的な遺伝的変異パターンとも合致。また、東北地方以北の個体群は共通ハプロタイプとそれから一塩基置換で派生する少数のハプロタイプで構成され、比較的短期間に個体群サイズが増加したことが示唆されたとする。
-
mtDNAのCOI領域に基づくヒメオオクワガタのハプロタイプネットワーク。各ハプロタイプのサイズはハプロタイプに含まれる個体数が、色は地域が示されている。東北地方以北では多くの個体群がハプロタイプH1を共有し、それから一塩基置換で派生する少数のハプロタイプから構成される。西南日本では地域固有のハプロタイプが検出されると共に、地理的なまとまりが示されている(出所:信大Webサイト)
また、個体群動態解析の結果からもクレードIの近年の個体群サイズの増加、特に中部地方以北の個体群における個体群拡大が支持された。つまり、最終氷期最寒冷期以後の東北日本の温暖化と湿潤化はブナ林の北方への急速な分布拡大を引き起こし、ヒメオオクワガタの北方個体群形成の際に「創始者効果」によって遺伝的多様性が低下したと思われる。
その一方で、比較的遺伝的多様性が高い西南日本においては、地域個体群ごとに固有のハプロタイプが検出されると共に、ハプロタイプ同士がループ構造を持つ地理的なまとまりが示され、長期間にわたり個体群サイズが安定維持されてきたことが予測されるという。この結果から、氷期において西南日本では、太平洋側を中心に複数のブナ林のレフュジアの存在が支持され、後氷期にはその多くが内陸の山地に移動するのみで北方への分布拡大は生じなかったと考えられるとした。
今回の研究成果は、将来危惧される気候変動に伴うブナ林の衰退が、そこに生息する生物種の遺伝的多様性に及ぼす影響を理解する上で重要な知見であるとする。研究チームは今後、ゲノムワイドな遺伝マーカーを用いることで個体群遺伝構造や個体群動態、環境適応について調査し、ブナ林とヒメオオクワガタの相互作用についてより詳細に評価する予定としている。