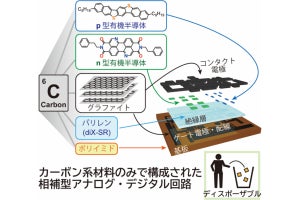理化学研究所(理研)は4月11日、全塗布プロセスによって、有機太陽電池(OPV)、有機発光ダイオード(OLED)、有機光検出器(OPD)に新しい3層デバイス構造を適用することで、3種類の有機光電子デバイスを集積することに成功し、ウェアラブルな自己給電式の「超薄型光脈波センサ」を実現したことを発表した。
同成果は、理研 開拓研究本部 染谷薄膜素子研究室の福田憲二郎専任研究員(理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 創発ソフトシステム研究チーム 専任研究員兼任)、同・染谷隆夫主任研究員(CEMS 創発ソフトシステム研究チーム チームリーダー兼任)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。
有機半導体材料を使って、OPV、OLED、OPDの3種類を同じ超薄型基板上に作製できれば、発電・発光・光検出を統合した超薄型の自己給電式光脈波センサを実現することが可能。また有機半導体材料は、塗布プロセスを使用できるため、生産効率を向上させやすい点も優れた点である。
しかし、上述の3種類のデバイスの発光層・受光層・発電層(以下機能層)は、それぞれ異なる有機半導体材料から成り、デバイスの種類によって電極と有機半導体層の間の正孔輸送層や電子輸送層も異なることから、同一基板上にそれらを塗布プロセスだけで作製することは困難だったという。また、塗布プロセスで作製された電極・輸送層・機能層に用いられる材料や界面は、水や酸素に対して不安定であるため、長期安定性にも課題を抱えていたとのこと。
研究チームではこれまで、OPVを超薄型の基板に作製することで人体への装着負荷を極限まで減らした自己給電型のセンサデバイスを開発してきた。そのOPVが、OPDやOLEDと素子の構造が似ていることに着目し、今回の研究では、これまで培ってきたそのプロセスをOPDやOLEDの作製にも適用し、さらに同一の超薄型基板上にそれら3種類の作製を試みることにしたとする。
そして、正孔輸送層・電子輸送層を含む従来の多層積層構造から、透明電極・不透明電極・機能層のみから成る3層構造へと構造を簡略化させることに成功。この3層構造はOPVやOPD、OLEDのすべてに適応でき、機能層を変えるだけで3種類のデバイスを同一基板上に作製可能となるという。また、全塗布プロセスでの作製手法も確立された。
この3層構造は、超薄型基板上に、透明電極、機能層となる有機半導体層、不透明電極の順に積層されている。超薄型基板上の透明電極は、高い仕事関数を持つ導電性高分子「PEDOT:PSS」を用いて、ブレードコート法により成膜された。また機能層上の不透明電極は、低い仕事関数を持つ液体金属である「共晶ガリウム-インジウム」(EGaIn)を用いて、スプレーコート法によって成膜された。どちらの電極も大気中で成膜可能であり、大面積性に優れた塗布プロセスに適しているという。また、透明電極と不透明電極との間の機能層(有機半導体層)は、ブレードコート法により成膜された。
今回の研究成果のポイントは、大気雰囲気中でのスプレーコート法によるEGaIn電極の作製法を確立したことだという。また今回の手法では溶液が互いに混ざり合わないので、上部層の塗布プロセス中に上部層に使用している溶媒に下部層が溶けることがなく、後プロセスによるダメージを受けないことも特徴としている。
-
さまざまな塗布手法および成膜環境でのEGaInの成膜状態。(A)窒素雰囲気中のドロップキャスト法。大きな液滴が形成され、濡れ広がらない。(B・D)窒素雰囲気中のスプレーコート法。いくつもの液滴の凝集体が観察され、不連続な膜となっている。(C・E)大気雰囲気中のスプレーコート法。連続的かつ平坦な膜が形成されている(出所:理研Webサイト)
全塗布プロセスで作製されたOPVは1000ルクス(lx)のLED光源下で39.4μW/cm2の発電能力を示し、蒸着電極を用いた素子の41.2μW/cm2とほぼ同等のエネルギー変換効率だった。駆動安定性については、全塗布OPVは、1000lxのLEDライトの下で1000分間最大電力点(MPP)を追跡した後でも、初期性能の80%以上を維持したという。これは、基準OPVの安定性(初期パフォーマンスの46%を維持)よりも著しく優れていたとする。また、OPD、OLEDも妥当な性能を有していることが確認された。
-
EGaIn液滴の挙動。(A)8000fpsの高速度カメラで観察された、EGaIn液滴の有機半導体層上への着滴の様子。窒素雰囲気中(上)では液滴が濡れ広がらず、噴霧した液滴の形状・サイズをほぼ着滴後も保持しているように見える。大気雰囲気中(下)では、液滴がつぶれて薄く濡れて広がっている。(B)それぞれの環境での液滴落下挙動のシミュレーション結果。(A)の結果が裏付けられている(出所:理研Webサイト)
そして、今回開発された全塗布プロセスの有機電子デバイスを用いて、超薄型光脈波センサが作られた。疑似太陽光による自己発電を用いて、脈拍が正常に計測できることが示されたとする。また、全塗布プロセスによる超薄型光脈波センサは、周囲空気に長期間(35日以上)暴露した後でも、脈波に関連する信号を維持することも確かめられたとした。
-
3層構造塗布プロセスによる超薄型光電子デバイスの性能。(上)OPV、OPD、OLEDすべての材料について、それぞれの溶液が混ざり合うことなく存在している。上部膜形成時に下部膜へダメージなくデバイスが作製可能。(左下)塗布OPVと、蒸着電極OPVの電流電圧特性の比較。200~1000lxの間で同程度の発電性能が示されている。(右下)塗布OPVと蒸着電極OPVの駆動安定性の比較。1000lxの光量下で駆動させた場合、塗布OPVの方が蒸着電極OPVよりも圧倒的に安定性に優れている(出所:理研Webサイト)
-
3層構造塗布プロセスによるウエアラブル超薄型光脈波センサ。(左)疑似太陽光下で駆動された超薄型光脈波センサの出力特性と周波数分析。72pbmの脈波に対応した信号が検出されている。(右)超薄型光脈波センサの大気安定性。センサは大気中の暗所で保管された後、脈波センサとしての性能が都度評価された(出所:理研Webサイト)
今回の研究成果による、3層構造を備えた全塗布プロセスによる有機光電子デバイスの優れた安定性により、超薄型光脈波センサによる脈拍の長期検出が可能になったという。また、今回の成果は、超薄型有機光電子デバイスの生産性の向上を実現するための有望な手段となることが期待できるとしている。