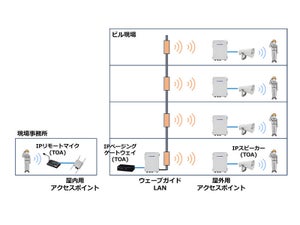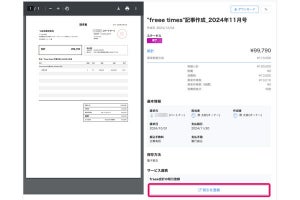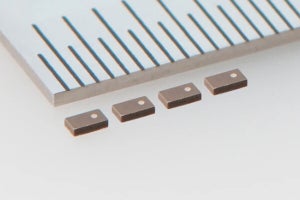「わたしの強みは無知でした」。専門の技術を持つ職人との対話の中で技術開発に打ち込む日々。その職人たちから学ぶことは多いと強調。「職人さんたちは、『白い紙は神に通じる』という精神性を背負っています。白い紙は不浄なものを浄化するという考え方です」。そういう中で堀木さんは「時代の役に立つには新しい要素も必要」と和紙の背景にある考え方、精神性、日本人の美学を取り入れ、和紙を進化させてきた。和紙のもつ魅力とは─。
銀行員から和紙と出会って
─ 堀木さんは和紙事業をメインに経営されていますが、まずは和紙との出会いを教えてくれませんか。
堀木 わたしは高校卒業後住友銀行に就職し、4年を経過した頃にお誘いをうけて、和紙の商品開発の会社に転職したんです。越前和紙の里にいろいろ行き来をしていましたら、職人さんたちが冬の寒い中で冷たい水を使って黙々と作業をしているのを見て、本当に素晴らしい営みだと思っていたところ、入社後2年で会社が閉鎖に追い込まれてしまいました。
手漉きで良いものを作れば作るほど、機械漉きで類似品が出てきます。そうすると、機械は安くて、手漉きは高いということで、手漉き和紙専門の会社は次々となくなっていってしまいました。その時に問題意識を感じて、手漉きの和紙と機械漉きの和紙の違いをしっかりと見出して、手漉き和紙が生きる道を進まなければいけないなと思ったんです。誰かがなんとかしなくてはと思って、24歳で起業しました。
職人さんたちの尊い営みをこのまま終わらせてはいけないと思ったことが一番の動機です。
─ 機械ではない手漉き和紙ということなんですね。
堀木 はい。長く使えば使うほど質感が増すことと、強度が衰えないのが手漉き和紙の特徴で、適した分野が建築インテリアだと考えました。
大きな和紙で、そして移ろいのある和紙を作りたいと思って、建築空間に向けて手漉き和紙を作る会社を興しました。
─ 建築に活かす場合、例えばどのように使うのですか。
堀木 光壁や光天井、オブジェにライトを仕込んだ光る彫刻のようなものにも使えます。
日本建築で代表的な障子をじっとみていると、そこには太陽光線が介在して、紅葉の時期には、なんとなく庭の赤い光が入ってくるとか、今日は満月だなというのが、そこはかとなく室内でわかるというのが和紙の効果です。つまり季節のうつろいや時間の経過が感じられるということが魅力です。それを現代建築でも表現できないかと考えました。
─ 技術的には難しい?
堀木 そうですね。職人さんたちの技術が必要です。大きな和紙を作りたかったので職人さんにお願いしましたが、すぐに「そんなものできへん」と3回ぐらいできないと言われました。そこで、できない理由を1つずつ潰していって、できることに変えていきました。
─ 新しさを付け加えて伝統を磨いたと。
堀木 はい。いくらきれいな和紙を作っても、結局子供がいて破られるとか、ペットに汚されるとか、消防法で燃えるものはビルに使用してはいけないといわれ、人の役に立たないものだと滅びていってしまいます。
そうすると、燃えない、汚れない、破れない、変色しない和紙、そして精度をあげるということに取り組まない限り、いくら美しい和紙を作っても、役に立たないものは使ってもらえません。そういった二次加工も含めていろいろな難点を克服する方法を模索してきました。
ですから私達は作家というよりも和紙の開発者です。美しい和紙を新しい技術を用いて作ることも大事ですが、結果的にはそれをどのように役にたてるかという二次的な加工が重要と考えています。
─ しかし、全然違う分野での起業でしたね。
堀木 はい。最初はみんなから反対されました。「堀木はデザインを勉強していない。アートの大学を出ていない。ビジネスも勉強していない。職人のところで修行もしていない。だからできるわけがない」というのが、反対している人全員の意見でした。
だから当時25歳のわたしは、本当にそうなのか? と縄文時代や弥生時代まで思考を戻してみました。そうすると今発掘されている土偶や埴輪は素晴らしい造形ですが、誰が作ったかというと、畑を耕して子供を育てて狩りにも行っていた一生活者でした。
当時は埴輪専門学校はなかったし、物を作る大学もなかったし、ピラミッドだって建築の大学がないときにできているし、その中のジュエリーだってジュエリー専門学校がないときに作っているわけです。だとすると、人間はみなクリエイターです。だったら私が専門の教育を受けていないからといってできない理由はないと、変な自信が湧いてきまして。
─ 確かにそうですね。
堀木 埴輪や土偶はなぜ作られたのかというと、大切な人が亡くなった時にあの世で困らないようにとか、来世で寂しくないように人の形や馬の形を作って一緒に埋めたわけです。自分が病気になったら人の形を土でこねて、身代わりに割って健康を祈っていたわけです。
こうしたことから、モノづくりの原点は自然に対する畏敬の念や、命に対する祈りの気持ちだということに気が付いたんです。
恐らく一般的に表現者というのは、自らのメッセージや想いを形にするためにものづくりをされている方が多いと思いますが、私の場合はそうではなくて、お客様の要望が先にあって、その要望に和紙の特性を活かした独自の方法で応えるという活動をしてきました。
その中で10mを1枚で漉き上げる技術や、糊や骨組みを一切使わずに立体的な和紙を作るなどの独自の技術が生まれてきました。
和紙に託されていた古来日本人の精神性
─ ある意味で常識を破りながら大きい和紙など新しい開拓をしていったんですね。
堀木 私の強みは無知であることだったんです。職人さんたちに何を言っても「できない」と言われるわけですが、わたしにはできることも、できないことも全くわからず、「なんで? こうしたらできるんじゃないの?」と、まず手を動かしてみて、職人さんに持っていくと「へたくそ貸してみろ」と解決に向かっていく。
それが新しい技術開発になり、日々のちょっとした挑戦が積み重なると、人がこれは革新だねと言ってくれるような技術になっていきました。
─ 職人さんは驚いたのではないですか。
堀木 はい。それよりも、職人さんからは、そんなものは伝統ではないと言われました。職人さんたちは、「白い紙は神に通じる」という精神性を背負っているんです。言い換えますと、白い紙は不浄なものを浄化するという考え方で、日本人が慣習としています。
私たちがいつもお祝いなどで使う白い和紙の祝儀袋にお金をいれて人に差し上げるのは、不浄とされているお金を浄化してから人に差し上げるという意味があります。
─ そういう意味があったんですね。
堀木 同じように、お歳暮などで熨斗を使うのも、品物にわざわざ白い掛け紙をして、その品物を浄化してから人に差し上げるということなんです。年末に大掃除するのも、単に障子を白い新しいものに変えるのではなくて、障子を新しくして部屋の空気を浄化して、新しい年神さまをお迎えする。お供え物を白い紙の上に置くのも同じです。
だから職人さんたちは1300年の間、より白くより不純物がないものを追い求めて来たわけです。ところが当時小娘だったわたしは、奇抜な色は入れるし、異物も漉き込んでいました。1300年職人さんたちが命がけで守ってこられた精神性があるなら、嫌われるのは当然だと思ったんですね。
だけど、やはり今の時代に白い紙だけでは限界がある。時代の役に立つためには新しい要素も入れなくてはいけないと思い、私が考えたのが、白い和紙の間にデザインを挟み込むという伝統を生かしながらの手法です。
日本の美学やおもてなしの根本は、人が人を想う気持ち。浄化した清らかなものを人に差し上げるということが、白い和紙に込められていたのです。
─ 日本のおもてなしの本質的な部分ですね。
堀木 ええ。わたしは、和紙を扱っていますが、和紙を作りながら、そういった和紙の背景にある考え方、精神性、日本人の美学というものを、次世代や世界に知らせていかないといけないと思っています。
だから単に作品を作るということではなく、単に技術開発をするということではなくて、古くから何を日本人が大事にしてきたのかということ、日本人独自の考え方をしっかりと受け継いでいかなくてはいけないと。
逆に技術は時代とともに変わってよいし、新素材が開発されて発展していくことも大切ですが、根底で変えてはいけないものがあると思うのです。それは、人が人を想う気持ちや自然に対する畏敬の念。命に対する祈り。これらは縄文時代から変わっていません。
意外なところからの注文
─ 堀木さんの和紙は建築以外のところにも使われている?
堀木 たくさんあります。サントリーウィスキーの響、山崎などのラベルにも使用されています。和菓子の「たねや」さんの箱にも使用されています。
インテリアの分野では、最近企業のエントランスや会議室も増えてきているんです。私が当初、和紙の仕事を始めた時には、公共空間や商業空間に使用されることが多かったんです。でも最近は企業や住宅の方が多いくらいです。
─ 和紙の魅力はなんだと考えますか。
堀木 和紙の表現には一つ一つ意味があるんですね。例えば、立涌柄という柄は宇宙の良い兆しが湧きあがるという意味合いがあります。この文様を私はG7伊勢志摩サミットの時に使いました。メッセージを伝統文様で伝えていくこともできるのです。
─ 今まで自分ではまったく予期しなかったところからの注文はどこからでしたか。
堀木 2000年のハノーバー国際博覧会で和紙の車を作った時ですね。坂茂さんが日本館を設計されて、その中に銅板画家の山本容子さんが和紙の車を発案して展示したいという依頼がありました。
山本さんからお電話がかかってきて「堀木さん、ちょっと万博のために車を造りたいのよ」というので、立体和紙の車のオブジェでもつくるのかと思ったら、最高時速125㎞で走る機能がある車で会場内をゆっくりと走ると。
それからもう1つの条件は2人乗りだと言われて。外装も内装もハンドルもシートもホイールキャップも、全部和紙で作りました。
─ 実際に走ったのですか。
堀木 はい。夜になるとその車が「次は愛知万博なので名古屋に来てください」というキャンペーンカーとしてゆっくり走るのです。
だから雨も降れば風もふくし、お尻や背中もこすれるし、手垢も付くという状況で、どうやって燃えない、汚れない、破れない、変色しないという精度を上げるかに取り組んで、1年で仕上げました。その1年が一番大変な仕事でしたし意外だった仕事ですね。
でもその制作に取り組んだことで、燃えない、汚れない和紙を開発できたことがそのあと建築にも活かせることになったんですね。建築で開発したことがラベルやパッケージなどの他の用途に使えるようになりますし、全部が循環しているように思います。
─ 1つ1つチャレンジだったんですね。堀木さんを突き動かすものは何ですか。
堀木 誰からも頼まれていない使命感です(笑)。誰もあなたに頼んでいないとみんなに言われますが。和紙を介して日本の精神、文化を残していくために、わたしは挑戦を続けています。