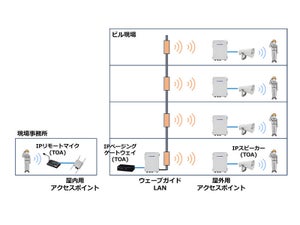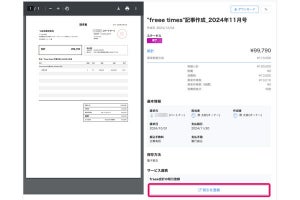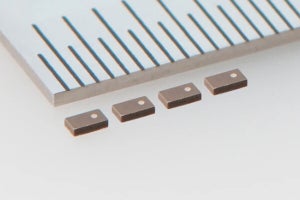「日本の強みである食産業は農業、漁業、一次加工、食品メーカー、物流、小売、外食など細分化されている。国家の戦略として食産業全般でとらえるという発想がこれまで少なかったのでは?」と指摘するのはZEROCO社長の楠本修二郎氏。この課題にメスを入れるのが、同社が開発した食材の長期保存が可能な保管庫。これにより市場拡大のための海外輸出がしやすくなるだけでなく、人手不足問題やフードロス削減など、あらゆる社会課題解決が可能になるという。これからは「冷凍でもない冷蔵でもない第三の道」だと語る楠本氏の描く、これからの食産業構想とは─。
IT業界から独立し飲食の道へ
─ 楠本さんは食材の長期保存を可能とするZEROCOで食産業革命に取り組まれています。リクルートコスモスから独立し飲食業で起業されていますね。まずそのお話からお願いします。
楠本 はい。コスモスに1988年に入社してからは広報室に入りCM担当などをしていたとき、あのリクルート事件が起きてわたしは池田友之さんの社長秘書になりました。
─ 大変なときでしたね。
楠本 はい。大学生の頃から、人が集まる場をつくることを自分の仕事にしたいと決めていました。バブルの真っ最中でしたが、このままただ安いものを買って高く売るという時代が続くわけがないと強い違和感として感じていました。
リクルートで、不動産業を学ぼうと思っていたら、リクルート事件が起こり、せっかく取得した宅建の免許もほぼ使用することがありませんでした。
事件のほとぼりが冷めて、1990年代頃、大前研一さんの下で3年ぐらい勉強させていただいていました。でもわたしはやはり人が集まるリアルな場、その風景をつくることがやりたいとの思いが強くなりまして。
─ 風景をつくるとは具体的にどういったことですか?
楠本 日本各地に多様性溢れる風景をつくりたかったのです。その地域に根ざした特異性みたいなものをポジティブに風景にしたときに、日本のクリエイティビティというか、もっとこういう生活をしていったらいいんじゃないかというライフスタイルが育っていきます。
そういったケーススタディを多数つくったほうがいいなと思い、大前さんが都知事選に出馬をするというタイミングで「すみません、僕、飲食店をやります」といって辞めました。大前さんは大変驚いていました(笑)。
─ 大前さんの下ではどんなことを学びましたか。
楠本 右脳思考で感性が強かったわたしが、論理的な思考や政策、それが社会のどのような貢献性につながるかを学びました。ただ単に「これがかっこいい、これがダサい」という話ではなく、全部一貫した話でないと駄目だということを勉強させていただきましたね。
─ 全体感のある視点で筋が通ったものですね。
楠本 はい。47都道府県全てに出向いていましたので、日本全国のおいしいものや風景の美しさ、人々の営みの多様性をありありと実感しまして、頭に思い浮かんだ概念が「コミュニティ」という言葉だったんです。
バブル崩壊後、明らかに大きなパラダイムの変換であると感じていたのですが、20代のわたしは、まだそれが次に何なのかが言葉にならずにモヤモヤしていました。
通り一遍のチェーン店をつくっていく時代は終わったのではないかと思ったので、逆に、人通りの少ない寂しいところに活気を促すには、アンカーになるような場所に非常に象徴的な、ちょっとお茶できるところ、ちょっと腰掛けられるところというものが出てくるだけで、街は変わるんじゃないか?というような発想からカフェを始めました。
ですからカフェという概念は、コーヒーショップというよりも「Community Access for Everyone」の略だといっているんですけれども、「Everyone」というのは「多種多様な方々」を指し、どこにおいてもその地域らしさが滲み出るような集い場としての適正なデザイン、スタイル、食、こういったものがあるのでは? というふうに思ったのです。
─ コミュニティづくりを場として具現化したいという思いがあったのですね。
楠本 はい。祖業のカフェ・カンパニーでは、コミュニティのありようというものは、時代、時代で求められることが変わることを前提にしています。
けれども、運営する店舗数が90店舗、100店舗になると、昔思っていた機動力を持った動きというのはなかなかできなくなってきます。
わたし自身、食の多様性に対してリスペクトが強く、日本全国にいろいろな食文化や地域性があることに対して、僕らはどういうコミュニティをつくったらいいんだろうということをずっと考えてました。
─ そういった中で実際つくってきた具体的なコミュニティづくりの例はありますか。
楠本 2011年に東日本大震災になり、オイシックスの髙島宏平さんと共に「東の食の会」を立ち上げました。
震災が起きた場所だからこそ、これからの日本の課題の縮図ともなる場所だとも思うので、だからこそ、この場所からヒーローを輩出し、ピンチから立ち上がっていく成功事例をつくっていこうと。今後、日本において災害などが起こった時でも、そのときに「東北はピンチの際にこういうことをやったよ」というケーススタディをつくろうという考えでした。
─ 未来に備えてのケーススタディですね。
楠本 はい。「東北からヒーローをつくろう」というキーワードで、実際に漁業や農業の方々と共に、収穫したものをそのまま卸すだけではなく、いわゆる六次産業化、つまり、自分たちでブランディングして自分で売る。そしてマーケットは東京だけでなく、いきなり世界だという視点を持とうと提案してやってきました。
結果的に、わたしは言うだけで、むしろ、東北の皆さんから教えてもらったことが多かった。彼らはそれを実践して、実際にウニの養殖でオーストラリアの州政府や大学機関などとも提携する北三陸ファクトリーなど、世界に打って出て大成功しているメンバーが現実にたくさん出てきているんですね。
こういった事例をわれわれも一緒につくっていく仕事をしていかなければいけない。これをコミュニティの概念で申し上げると、日本の食産業は農業、漁業、一次加工、食品メーカー、それから物流、流通小売、外食。外食もチェーン店からミシュラン店まで、全部縦割りになってしまっているんです。
主に2011年の震災以降、農水省や経済産業省の委員会にも参加し、食産業全般のことをいろいろ議論する機会が多いのですが、外食産業は外食産業の課題で終始してしまうことが多いんです。農業は農業問題。物流は物流と。
─ 全部分かれていると。
楠本 ええ。だから部分最適議論になってしまうんです。食産業のありとあらゆる人たちが集まってパネルディスカッションをしたときに、皆さんな素晴らしいことをおっしゃるんです。ただ、それぞれの立場からの意見に終始してしまうから結局「いいお話でしたね。頑張りましょう」で終わってしまうのではないか、これだと総合的な政策にならないのではとこの10年で強く感じていまして。
食産業のコミュニティ化で総合的な政策を
─ このことを訴えてみなさんの反応はどうですか。
楠本 結論、変わりました。ただ、みなさん聞いてはくださいますが、10年ほど前までは、どこかぼんやりしていて実感がなかったんです。それよりもアクションを先にいろいろやっていたのですが面で広がっていくような動きにならなかったので、5年ぐらい前からわたしも心を入れ替えまして、もっとこれから先の食産業全体、つまり食産業をコミュニティ化しようと思っています。これをマッキンゼーは「オーケストレーション」という言い方をしているんですけれども。
─ オーケストラの指揮者ということですね。
楠本 指揮者がいない食産業。だからそれは、例えば農業と一流のミシュランシェフ、そこによい保管技術、このかけ合わせでこんなことができると。小売りメーカーと漁業がタイアップしたらこういうことができるよねと。そういった動きが、もっと必要なのだと強く思っているのです。
このことを外食産業で講演をしたり、農家さんと直接対話をする機会をつくったりしてます。あるとき、「実は初めて農家さんと直接話をした」という経営者の方もいて驚いたこともあります。こんなに分断が起きてしまっているのかと。
ですから、食産業全般でとらえるなどというビッグピクチャーはこれまで誰一人として描くことがきなかったのかもしれません。
─ バラバラだったものを全体最適化を図るという発想がこれまでなかったのを、楠本さんが訴え続けているんですね。農協や商社もあるが、皆バラバラだと。
楠本 はい。行政や省庁の方々にも、目からうろこだと皆さんおっしゃっていただいて。わたしがもうひとつ申し上げたのは、今までは、例えば〝ファッション×食〟とか、〝住まい方×食〟とか、食はみんな後から掛けられていた方なんです。
そうではなくて、〝食×モビリティ〟とか、〝食×観光〟とか、〝食×ファッション〟、〝食×エンターテインメント〟にすると、それぞれの産業への波及効果がこちらのほうが高くなるんです。
本来、ハブにしなければいけないのですが、今までハブになっていないのです。サプライチェーンなんです。
─ これをハブにすると。
楠本 はい。そうすると、ライフスタイルとなっていくので、ホームエレクトロニクスから、モビリティから、観光から、地方創生から、ありとあらゆるところが食を中心とした、日本全体としてもリブランディングをするというようなことがやりやすくなるはずですよ、というお話です。
ただ、これを人に言うだけだと、「うん、わかった、わかった。面白いことを言うな。でも、どうやってやるの」みたいな話で止まってしまう。
そんな中コロナ禍が突然やってまいりました。もうこれは政府に提言しているだけではなく、いち早く民間で動くべきことなんだと思い、カフェ・カンパニーだけでなくて、全部で4つ、5つの会社を同時に走らせています。
ZEROCO、そして、ボードメンバーとして海外向けのフードコート事業、メルカート・メトロポリターノというものをやっています。
なぜかというと、日本人は海外にチャイナタウンのような「ゆりかご」を持っていませんよね。ですから、海外で事業展開しようと思ったときに、わたしもそうだったのですが、みな同じ間違いに陥ることが多いんです。
中国の方は、まずチャイナタウンに行けば、ラーメン屋をやろうとしていたけれど、現地の先輩から「ラーメンよりうどんがいいぞ」とか、「ロンドンでやろうと思っていたけれど」「いや、今、ロンドンは飽和状態だから、それよりバーミンガムのほうがいいぞ」とか、そんな「ゆりかご」があるわけです。
シリコンバレーだって、そこを設計されていて、当然シリコンバレーはサンフランシスコ、サンノゼが拠点ですが、いろいろな仲間たちが各国に飛んでいるのでチームとして海外でも機能しているのです。
でも日本は「ゆりかご」としてのジャパンタウンを持っていないので、孤軍奮闘になってしまう。
─ たしかにジャパンタウンはないですね。
楠本 はい。WBCで例えると、日本がワンチームとして海外で戦う場合は、巨人と阪神のメンバーも同じチームになりますが、海外に行っても巨人対阪神で戦っているような状態になってしまっているのです。だから、同業のラーメン屋同士が同じ出店場所で競っているとか、そんなふうになってしまうんですね。
これを、食をオールジャパンで、世界に出て各国で勝てるような産業にしたいと。
勝つためには、それぞれの地域性、それぞれの地域の生きた情報やビジネスパートナーや食材の調達も含めた、いろいろなビジネスサポートができるゆりかごがないといけない。
でも、今から少子高齢社会を迎える日本が各国にジャパンタウンをつくるのは難しい状況でもあります。
ですから海外のパートナーと組んで、例えばイタリアならイタリア食と日本食で世界の食に貢献しようということです。そういうことをやっています。
─ わかりました。この食産業に全部横串、縦串を刺すために具体的にいま進めていることは何ですか。
楠本 そこのキーになるのが今力を入れているZEROCOということなんです。
(次回につづく)