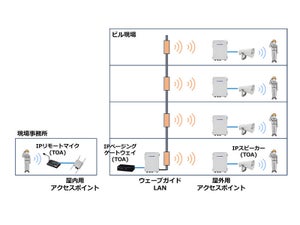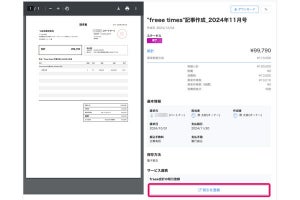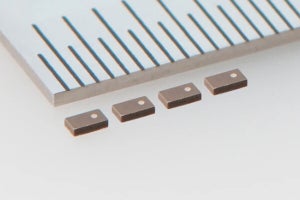経営者は自らの強みの本質を科学的、理論的に突き詰めているか?
題名からは昭和の日本「的」経営礼賛本? の印象を持つ人もいるかもしれないが、中身は真逆である。
新進の経営学者である著者は、日本企業に限らず世界共通の競争力の根源、すなわち「ヒト」の力、人的資本≒組織能力の重要性と、日本企業が特に強みとしていた組織能力を「カイゼン」というキーワードを中心に日本「式」経営として抽象化、普遍化し、さらには1990年代以降、その強みをなぜ日本企業は生かせなくなったのかに切り込む。
そこで経営者の問題、著者の師匠筋にあたる藤本隆宏・東大名誉教授の言葉を借りるならば「本社力」の問題に対峙せざるを得ない。
日本の経営者たちは、自らの強みの本質を科学的、理論的に突き詰めていたのか。好調時に漫然と「ヒトを大事にする日本的経営は素晴らしい」程度で分かった気になり、昭和の時代背景から派生したに過ぎない新卒一括採用や終身年功制、同質的で閉鎖的な組織とガバナンス構造に疑問を持たなかったのではないか。
本書では昨今流行の「両利きの経営」について、それが多くの要素を日本企業の経営から学んでいることを指摘しているが、「両利きの経営」の提唱者、スタンフォード大のオライリー教授の長年の盟友である私も同感である。古くはジェイムズ・アベグレン(こちらは私の元上司)の「日本の経営」から始まり、むしろ米国人が日本企業の成功要因を分析し、抽象化、普遍化して、時代と国境を越えて通有性を持つ経営方法論化してきた歴史がある。
現代はゲームチェンジングの時代、大変容の時代である。得意の「カイゼン」は、現場力の賜物であり、徹底的な具体化の突き詰めだ。逆に経営者はかかる現場組織能力の強みを抽象化した時に、自社はどこで戦えるのか、そのために組織制度や人的資源をどう変容すべきかを見極め、果敢に行動しなければならない。
この抽象化能力に関わるパラドックスを本書は鋭く問うている。