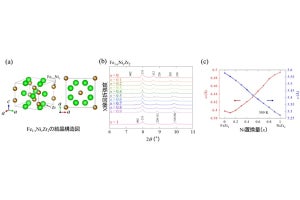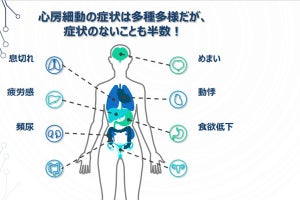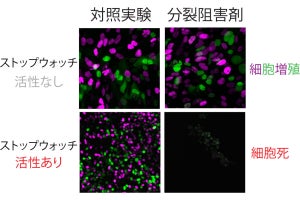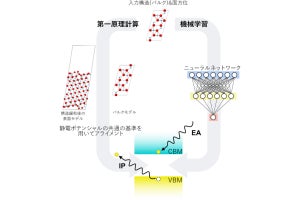筑波大学は4月2日、主に身体ではなく頭脳の活動であるeスポーツでは、疲労の自覚が遅れて認知疲労(判断力低下)と乖離してしまうことが判明し、その一方で瞳孔の収縮が認知疲労の指標となる可能性が示されたことを発表した。
同成果は、筑波大 体育系の松井崇助教、同・髙橋史穏大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、心理学の観点からコンピュータの使用を調査することに特化した学術誌「Computers in Human Behavior」に掲載された。
ビデオゲームを題材に、1対1、複数対複数、もしくはレースのように複数が参加して全員がライバルという形で勝敗を決めるeスポーツ。ゲームによってはコントローラやマウスなどを瞬間的かつ極めて精密に操作する必要もあるが、全身を使うような動作は必要ないため、基本的には将棋や囲碁などの頭脳戦に近いとされている。
eスポーツの適度なプレーは、ヒトの脳機能を高めることが明らかにされつつあるが、プレーが長時間になってしまうことも多く、座り過ぎ、睡眠不足、食事を抜く、部分的な身体部位の酷使などによる不調が課題となっている。また、特に若年層では、依存性に関連したインターネットゲーム障害の問題も指摘されている。
こうした過度な頭脳活動を防ぎ、パフォーマンスと健康を両立するための鍵は疲労感だという。疲労感は、心身の機能が低下していることを自覚する感覚であり、過労に対する主要な防御機構の1つと定義される。eスポーツは身体運動は部分的でしかないため、eスポーツでの疲労は、実際の運動のように身体が思うように動かなくなるといった、パフォーマンスの低下というわかりやすい形では現れにくい。それよりも楽しさや勝利へのモチベーションの方が強いため、長時間プレーをしても認知疲労を自覚しにくい可能性があるという。
そこで研究チームは今回、eスポーツの長時間プレーが、経験の多寡によらず、疲労感の発生よりも先に、脳活動の間接指標とされる瞳孔の収縮(脳活動の低下)と共に認知疲労を引き起こすという仮説を立て、それを確かめることにしたという。
今回の研究では、eスポーツとして、ダイナミックな身体活動を伴わないバーチャルサッカーゲームが用いられ、筑波大の学生および秋葉原のゲームコミュニティから募集した33名が実験に参加した。その内訳は、普段から同ゲームを好んでプレーするカジュアルプレイヤーが14名、大会で勝つために毎日同ゲームを長時間プレーするハードコアプレイヤーが19名(2名のトッププロプレイヤーを含む)である。
-
研究の実験プロトコル。プレー前と、約3時間にわたるプレーにおいて、1時間おきにストレスホルモンであるコルチゾルの量を測定するために唾液が採取され、質問紙による感覚(面白さと疲労感)の評価、およびフランカー課題による判断力の評価が行われた。なお、コルチゾル量にはプレー時間による大きな変化は見られず、プレー中に生じる認知疲労はストレスによるものではないと考えられるという(出所:筑波大プレスリリースPDF)
実験では、参加者の瞳孔径をアイトラッカーで常に測定しながら、サッカーゲームを合計3時間プレー。プレー前およびプレー開始から1時間ごとに、視覚的評価スケール(VAS)で感覚(面白さと疲労感)が測定され、判断力を測定するための「フランカー課題」の成績から判断速度と判断精度の評価を実施。部屋の中央および参加者の目元の照度は、常に250~300ルクスが維持された。
-
eスポーツのプレー時間ごとの主観的疲労と認知疲労。(A)カジュアルプレイヤーは、1時間のプレーでフランカー課題の干渉時間(判断速度)が有意に改善した一方で、2時間以上のプレーでは有意に悪化した。(B)ハードコアプレイヤーは、2時間以上のプレーでフランカー課題の正答率(判断精度)がプレー前から有意に悪化した。(C)長時間のプレーにより、カジュアルプレイヤーは3時間時点で疲労感が有意に増加したが、ハードコアプレイヤーでは変化は認められなかった。(D)長時間のプレーは、プレイヤーのレベルに関わらず主観的な面白さを高めるが、ハードコアプレイヤーの方がカジュアルプレイヤーよりもその影響が大きかった(出所:筑波大プレスリリースPDF)
その結果、プレー開始の1時間後には、感覚の改善と共に、カジュアルプレイヤーでは判断速度を高めることが初めて確認されたという。しかし、プレー開始の2時間後と3時間後には、カジュアルプレイヤーで判断速度が遅れ、ハードコアプレイヤーでは、元々高かった判断精度が低下したとする。これらの結果は、プレー経験に応じて、特徴的な認知疲労が表れることが明らかにされた初めての知見とした。
-
eスポーツの長時間プレー時における疲労感と認知疲労(A:判断速度、B:判断精度)の関係。長時間のプレーに伴う疲労感と認知疲労との間には、プレー経験によらず、関連性が認められなかったことから、長時間のプレーによる認知疲労は、疲労感の高まりからは自覚できないことが示された(出所:筑波大プレスリリースPDF)
一方、疲労感は、どちらのプレイヤーでも2時間後まではまったく変化せず、3時間後に微増し、面白さは常に高く維持されたという。疲労感と判断速度や判断精度との関連は、どちらのプレイヤーにおいても認められなかったことから、eスポーツプレー時の認知疲労を自覚するためには、疲労感は頼りにならないことが明らかにされた。
-
eスポーツ長時間プレー時の瞳孔収縮と認知疲労との関連。(A)瞳孔の拡大・縮小が脳の覚醒をもたらす脳内ノルアドレナリン神経を中心とした神経活動と関連することから、eスポーツプレー中の瞳孔動態と認知疲労との関連が検討された。(B)プレー1時間時点の瞳孔径に対する変化量は、プレー経験に関わらず、2時間以降に有意に減少した。(C)瞳孔径の縮小は、カジュアルプレイヤーにおけるフランカー課題の干渉時間(判断速度)と負の相関関係が示された。(D)瞳孔径の縮小は、ハードコアプレイヤーにおけるフランカー課題正答率(判断精度)と正の相関関係が示された(出所:筑波大プレスリリースPDF)
それに対し、瞳孔径はどちらのプレイヤーにおいても2時間後と3時間後に約0.1mm縮小し、その変化量が、カジュアルプレイヤーでは判断速度の低下と、ハードコアプレイヤーでは判断精度の低下と、それぞれ相関関係が示された。つまり、瞳孔の縮小が、認知疲労を精度良く検知するために有効な神経マーカーとなることが示されたのである。このことは、当初の仮説通り、長時間のeスポーツプレーが、経験の多寡によらず瞳孔径の縮小と関連して、疲労感の発生よりも先に認知疲労を引き起こすことを示唆しているとした。
研究チームは今後、今回の成果に基づき、認知疲労の健全な予防に向けたスポーツ・栄養戦略の構築や、ゲーミング・ITツールの開発研究に取り組むという。加えて、さまざまなジャンルのeスポーツについても、さまざまな参加者(年代、性別、障がいの有無など)や環境(賞品、観客、チーム、実際の大会など)を対象に同様の検証を進め、老若男女の活力と絆を育む、総合的な「eスポーツ科学」を展開していくとしている。