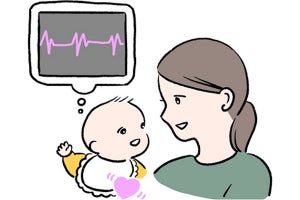大阪大学(阪大)は3月29日、ミニカーに乗ろうとしたり、人形の靴を履こうとしたりといった、幼児に特有の行動である「スケールエラー」が、発達のどの時期にどのくらい生起するのかを、大規模データを用いて明らかにしたことを発表した。
さらに、スケールエラーとの関連が指摘されていた言語発達について、動詞や形容詞の習得が特にスケールエラーの生起と密接に関わっている可能性を発見したことも併せて発表された。
同成果は、阪大大学院 人間科学研究科の萩原広道助教、江戸川大学 社会学部 人間心理学科の石橋美香子講師、京都大学大学院 文学研究科の森口佑介准教授、東京大学大学院 教育学研究科の新屋裕太特任助教らの研究チームによるもの。詳細は、科学的発達心理学と発達認知神経科学を扱う学術誌「Developmental Science」に掲載された。
スケールエラーは、ミニカーに乗ろうとしたり、人形の靴を履こうとしたりするなど、非常に小さな物体に自分の身体を当てはめようとする現象のことで、1~2歳ごろの幼児に見られることがある。2004年に報告され、研究としては比較的新しいものだが、発達心理学者を筆頭に、脳科学、さらには工学の研究者まで、複数の分野の研究者が関心を寄せているという。
これまでの研究から、スケールエラーはすべての幼児に見られるわけではなく、そのような行動を見せない子がいることも観察で確認されていた。さらに、観察の場が研究室なのか保育園なのかなどによっても、スケールエラーの生起頻度が異なっていることもわかっていた。そのため、スケールエラーの発達的変化については統一的な見解がなく、幼児期のどの時期にピークを迎えるのかも研究者によって主張が異なっているのが現状だとする。
そこで研究チームは今回、これまでの複数の研究において日本や海外で収集された528名分のスケールエラーデータを統合し、これに「ゼロ過剰ポアソンモデル」を当てはめることによって、スケールエラーの発達的変化をより適切に記述することを試みたという。なおゼロ過剰ポアソンモデルとは、統計モデルの一種で、観察時にゼロが多いデータの分析によく用いられるものだ。今回の研究の場合は、「そもそもスケールエラーをまったく示さない」ことによって生じるゼロと、「スケールエラーを示すが、観察時にたまたまスケールエラーを示さなかった」ことによって生じるゼロとを区別するため、同モデルが用いられた。
その結果、研究室での観察(通常5分程度で個別に実施)では生後18か月(1歳半)ごろに、保育園での観察(20~70分程度で他児もいる状況下で実施)では生後26か月(2歳過ぎ)ごろに、それぞれスケールエラーが最も観察されやすいことが明らかにされた。
さらに、全体のデータのうち語彙チェックリストの結果を含んだ197名分のデータを用いて、子どもの月齢の代わりに、名詞や動詞、形容詞の語彙数を発達の指標とし、スケールエラーの生起と関連する語彙指標が探られた。これまでの研究では、スケールエラーは言語発達の中でも名詞の習得と関連することが指摘されていたが、解析の結果、スケールエラーの発達的変化は名詞ではなく、より抽象的な単語である動詞や形容詞の発達とより密接に関わっている可能性が見出されたとする。
今回の研究により、スケールエラーが発達のどの時期に見られやすい現象なのかがより適切に推定された。発達時期の特定は、子どもがなぜスケールエラーという不思議な行動を示すのかを理解することに大きく貢献するという。
さらに、スケールエラーが、「靴」や「車」などの具体的な名詞の発達よりも、「履く」や「乗る」などの動詞や「小さい」や「大きい」などの形容詞といった、より抽象的な単語の発達に伴って生じる可能性が見出された点も、発達心理学にとって重要な意義があるとのこと。その理由は、スケールエラーという現象が、単なる「おかしな行動」なのではなく、子どもが抽象的な能力を発達させていく過程で生じる「発達的に意味のある行動」であることがわかったからだとする。研究チームは、スケールエラーという幼児に特有の行動をさらに探究していくことで、抽象的な認知能力の発達メカニズムの解明につながることが期待されるとしている。