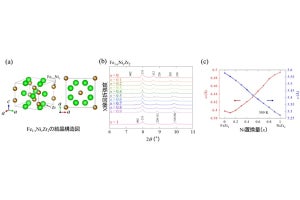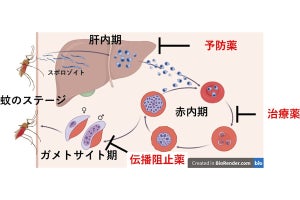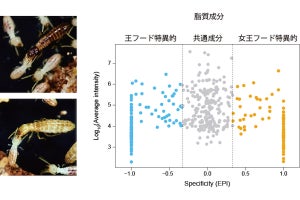岡山大学は2月22日、サツマイモの大害虫で特殊害虫に指定されている「イモゾウムシ」がサツマイモの植物苗のどの部分に滞在するか48時間調べたところ、昼間は雌雄とも節に滞在し、交尾が生じる夜間は、特にメスが苗から移動し離れる一方で、マウント(交尾を含む)行動は苗の節で見られ、卵を地際部の苗に産み付ける習性があることを初めて発見したと発表した。
同成果は、沖縄県 病害虫防除技術センターの浦崎貴美子班長、岡山大 学術研究院 環境生命自然科学学域の松村健太郎研究助教、同・宮竹貴久教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、応用昆虫学・応用動物学・農薬・害虫駆除などに関する全般を扱う学術誌「Applied Entomology and Zoology」に掲載された。
日本の農業を脅かし農作物に甚大な被害を与える病害虫は、その対象害虫やその寄主となる植物の移動を規制し、まん延を防止するため、国からの補助を受けて根絶防除事業が行われている。
甲虫の一種であるイモゾウムシは3.2~3.6mmほどの体長で、暗褐色の地に淡褐色の斑模様という外見をした、カリブ海島しょ域が原産の侵略的外来生物だ。その幼虫は、サツマイモなどのヒルガオ科植物の塊根(イモ)に寄生して食い進んでしまい、甚大な被害を与える農業害虫である。イモゾウムシは戦後間もない1947年に沖縄本島で発見されて以来(小笠原諸島でも確認されており、太平洋諸島経由で日本に侵入したと考えられている)、沖縄県と鹿児島県の奄美群島の全域に侵入して北侵を続けており、南西諸島では「不妊虫放飼法」による根絶事業が実施されている。
なお不妊虫放飼法とは、害虫のオスを大量に繁殖させてそれらを不妊化し、対象地域に放って野生メスと交尾させ、繁殖を阻害するという防除法のこと。不妊オスと交尾した野生メスの産んだ卵は孵化しないため、次世代の個体数が減り、それを続けることで根絶に至らしめることが可能な技術である(これまで、米国の畜産害虫ラセンウジバエ、日本の南西諸島でのウリミバエの根絶などの実績がある)。
しかし、この実績不妊虫放飼法を用いても、イモゾウムシがいったん定着した地域から根絶することは困難だとのこと。その理由の1つとされるのが、同害虫の行動や生態がほとんど未解明である点だ。不妊虫放飼法は、不妊化した虫を大量に放して野生メスとの交尾を介して害虫を根絶させる技術であるため、対象害虫の植物上での分布や繁殖システムの理解が不可欠である。しかしこれまでのところ、植物体での同害虫の分布や生態を明らかにできていなかったという。そこで研究チームは今回、サツマイモの苗を用いて、イモゾウムシがどの部分に分布するのかを調べたとする。
今回の研究では、イモゾウムシの成虫5匹を、雌雄別あるいは雌雄一緒にサツマイモの苗(8本での繰り返し実験)に放ち、4時間おきに48時間、苗のどの部分に分布するのか調べたとのこと。観察の結果、夜間は特にメスが移動して苗から離れること、昼間は雌雄とも節(植物の茎の枝分かれする部分など、節くれ立った部位。竹の場合はわかりやすい)に滞在し、夜間は節で交尾を含むマウント行動が見られ、卵は地際部(根元と地面の境界)の苗に産み付ける習性があることが初めて確認された。研究チームによると、夜行性の同害虫の繁殖生態を寄主植物上で詳しく観察した結果は、今回の研究が初めてだといい、植物の上での同害虫の分布や生態について明らかにできたとする。
今回の研究成果は、根絶を目的としながらも、農薬を使わずに環境への影響が優しい害虫根絶法である不妊化法を効率的に実施することにつながるとのこと。サツマイモは、日本が世界に向けて輸出品目として力を入れており、研究チームは今回の成果により、その栽培をより推奨できることにもつながるとしている。