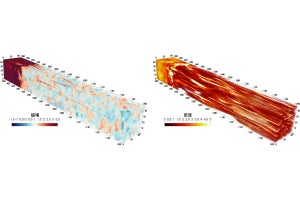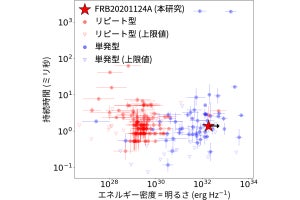京都大学(京大)と理化学研究所(理研)は2月15日、通常の若い中性子星の100~1000倍ほどになる10の10~11乗テスラという、宇宙最強の磁場を持つ天体であるマグネターの1つで、天の川銀河内にある「SGR 1935+2154」をX線で高頻度に観測した結果、2022年10月14日に発生した「高速電波バースト」(FRB)の前後に、中性子星の放射する電磁波のパルス周期が瞬時に短くなる(星の自転が急速に速くなる)現象である「グリッチ」が2回起きたことを突き止めたと発表した。
同成果は、台湾国立彰化師範大学のChin-Ping Hu准教授(元・京大 日本学術振興会 外国人特別研究員)、京大大学院 理学研究科 物理学第二教室の成田拓仁大学院生、同・榎戸輝揚准教授(理研 開拓研究本部 理研白眉研究チームリーダー兼務)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。
FRBは、1ミリ秒以下という極めて短時間に発生する電波帯(数百MHz~数GHz)の突発現象で、2007年が初報告の比較的新しい天文現象として知られている。これまでの多数の観測から、その大半は天の川銀河外で発生していることがわかっており、実際にFRBを起こした天体が含まれる銀河が特定された例もある。しかしFRBを起こす天体の正体や、その発生機構はまだわかっていない。
そうした中、2020年4月28日に今回のマグネター(SGR 1935+2154)がX線バースト現象を頻発し、そのバーストの1つとFRBが同時に検出された。その観測から、少なくともFRBの一部はマグネターが起源であることが突き止められたが、その発生機構についての観測は少なく、まだ謎に包まれたままだという。
さらに今回のマグネターは、2年後の2022年10月10日にも類似したX線バーストを頻発するようになり、研究チームはそれを捉えると、前回と同様にFRBが発生することを期待して、国際宇宙ステーション(ISS)に搭載されたNASAのX線望遠鏡「NICER」や、X線天文衛星「NuSTAR」に緊急観測を要請し、同月12日から4日間にわたるモニタリング観測を実施したという。そして観測開始から2日後の14日に期待されていたFRBが発生。しかし運の悪いことに地球の影になってしまい、FRBそのものの瞬間にX線観測を行えなかったが、FRBが発生した前後の2日間にわたる、かつてない高頻度なX線観測データを得ることができたとした。
マグネターを含めて中性子星は、その表面にホットスポット(高温領域)があり、そこからのX線が自転に伴ってパルス的に放射されている。その数ミリ秒から数秒ほどのX線パルスを観測することで、その星の自転周期を測定することが可能だという。中性子星の自転は、X線バーストを放射する活動期には複雑な時間変化を示すこともあるという。そこで研究チームは今回、そのX線パルスの到来時間を詳細に解析し、今回のFRBが起きた前後の時間で、今回のマグネターの自転がどのように変化したのかを調べることにしたとする。
解析の結果、今回のFRBが発生した約4時間前と4時間後に、急激に自転が速くなるグリッチ(スピンアップ・グリッチ)が起きていたことが発見された。このようなグリッチは、これまでにもいくつかの中性子星で観測されていたが、FRBと付随して観測されたのは今回が初となる(短期間にほぼ同強度のグリッチが2連続で観測されたのも初)。また今回の双子のグリッチは、これまでに観測された中でも最大級であることも判明した。
-
SGR 1935+2154のX線パルスの自転周波数の変化(上)と、それぞれの時刻での周波数の時間変化率の絶対値(下)。上図では上の方が自転が早いことを意味する。青いデータ点は観測値、オレンジの線はモデルが示されている。赤の点線はFRBが起きた時間(図の時刻原点)、紫の点線は2回のグリッチの時刻が示されている (出所:京大プレスリリースPDF)
さらに、2度のグリッチの間で自転が急減速していることも確認された。減速するには何らかの方法でエネルギーを外に排出する必要があることから、X線バーストのスペクトル解析も行われ、放射エネルギーが計算された。すると、放射で失われたエネルギーは10%程度とわかり、荷電粒子を含む星風など、放射エネルギー以外の理由で減速が起きた可能性が示唆されたという。
-
NICERとNuSTARの観測で得られた、SGR 1935+2154のグリッチ間のバースト放射スペクトルと定常放射(バースト以外の放射の)スペクトル。スペクトルはマグネターにおいて典型的な黒体放射成分とべき乗成分でフィットできたという。ここでは、バースト放射スペクトルに関しては、NICERとNuSTARの観測時期の違いが補正され、NuSTARのスペクトルが実際の約3倍にして表示されている (出所:京大プレスリリースPDF)
今回の研究により、FRBが起きる際にマグネターの自転が短時間で大きく変化していることが示され、同天体の活動がどのようにFRBを起こすかの機構の解明に一歩近づけたと研究チームでは説明している。
なお、FRBの発生源がすべてマグネターなのか、それともほかの天体も混ざっているのかはまだ不明だ。今回のような電波とX線を結びつけた多波長観測や、高頻度なマグネター観測などは、今後のFRBとマグネターの研究を大いに進展させる鍵となるだろうとしている。さらに、X線放射の長時間の時間変動を高頻度で調べることで、FRBが起きる際に、マグネターのどこで物理的な変化が起きているのかを解明できる可能性があるという。研究チームは今後も、今回のマグネターで起きたFRBとX線バーストの放射の関係について、より詳細な解析を行なっていく予定としている。