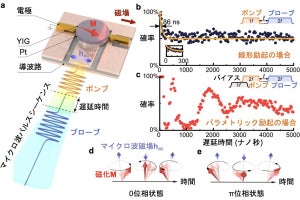東京大学(東大)は2月8日、高速道路上における「走行中ワイヤレス給電システム」の最適配置と経済性を検証し、充電を気にせず電気自動車(EV)で日本中を旅行できるモビリティ社会像を具体的に提示したことを発表した。
同成果は、東大 生産技術研究所(生研)の本間裕大准教授、同・大口敬教授、同・畑勝裕助教、同・長谷川 大輔特任助教(現・東大 不動産イノベーション研究センター 特任助教)らの研究チームによるもの。詳細は、インフラによって促進される経済活動の数学的・数値的研究を扱う学術誌「Networks and Spatial Economics」に掲載された。
再生可能エネルギーの割合をより多くするなど、発電でCO2を発生させない仕組みを作るのと同時に、現行のエンジン車をEVへとシフトさせていくことが、CO2削減に重要だとされている。しかし、EVは現在のリチウムイオン電池の性能による制約を受け、エンジン車と比較すると連続航続距離が短く、充電も時間を要するなど、大きな課題を抱えており普及への障害となっている。
そうした中、この2つの課題を同時に解決できるインフラ技術として提案されたのが、走行中ワイヤレス給電システム。同システムは、道路に埋め込まれたコイルから直接電力の供給をEVが受ける仕組みで、走行しながら充電を行えることから仮にバッテリの搭載量がそれほど多くなくても連続航続距離の短さを気にする必要がなくなり、また充電で待たされることもなくなるとされている。しかし、都市間高速道路に長距離に渡って敷設する場合、導入コストが多大になることが不安視されていた。そこで研究チームは今回、移動可能性と敷設コストの双方を適切に勘案し、日本の高速道路における走行中ワイヤレス給電システムコイルの最適配置を導出することにしたという。
研究では、新東名・名神および東北自動車道の実際のデータを用いて精緻に検証が行われ、その結果、EVインフラとして走行中ワイヤレス給電システムには経済性の観点からも十分に前向きなポテンシャルがあることが示されたとする。
たとえばEVのバッテリ容量を40kWhと想定した場合、新東名・名神(総延長約500km)、東北自動車道(総延長約1350km)どちらの場合でも、片道あたりわずか50kmを敷設するだけで95%以上の移動をカバーできる結果が得られたという。また、社会全体でのEVの普及率が30%程度になれば、十分に採算性が見込めることも同時に導き出された。これにより、EVがガソリン車と同等以上の使い勝手を持てるモビリティ社会像が提示されたとしている。
さらに、走行中ワイヤレス給電システムのコイルの最適配置にはさまざまなパターンがあり、配置の自由度が高いことも明らかにしたという。配置に自由度があることは、充電の時間的なタイミングや空間的な場所を柔軟に制御できることを意味するとしており、これは再生可能エネルギーなどを活用したスマートエネルギー戦略へも有効とする。日中に多くのEVが走行している場所にコイルを設置すれば、日中に太陽光発電によって余剰となっている電力を有効利用可能。また、風力発電などが設置されている地域にコイルを配置すれば電力供給の地産地消にも貢献できるとした。
走行中ワイヤレス給電システムと充電スタンドの併用を前提とした場合でも、同システムを導入することにより、スタンドの設置台数を節約することが期待できるという。大半の移動は走行中ワイヤレス給電システムで容易にカバーできるため、ごくわずかな超長距離移動のみを充電スタンドで補完すれば良いという未来が描けるとした。このようなEVインフラのベストミックス戦略を想定することによって、充電の心配なくEVで日本中を旅行できるモビリティ社会像が導かれるとしており、研究チームは今後、市街地での移動も含めた日本全国の道路網全体でのさらなる精緻な検証を予定しているとした。