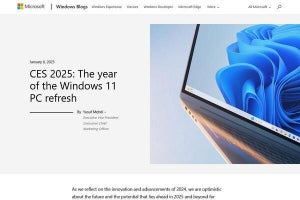アナログな建設現場に、いかにデジタル化の波を吹き込むか─。「建設24年問題」が目前に迫る中、2021年に建設DX銘柄として初めて東証マザーズ(現グロース)に上場したのがスパイダープラス。建設現場の進捗確認や指示だしなどを1台のタブレットでできるサービスは「事実上のデファクトスタンダードになっている」と創業者の伊藤謙自氏。同氏は熱絶縁工事会社を興し、建設現場のデジタル化の必要性を痛感。若者を惹きつける建設業へ進化させることができるか。
膨大な現場監督の業務量を削減
「(建設現場の納期や予算、安全、品質などを守り、設計図の構造物をリアルな形にするために現場全体のマネジメントをする)現場監督が、いつでも、どこでも、現場をリアルタイムで把握・管理することができれば、アナログな建設業の生産性向上に寄与することができる」
建築図面・現場施工を管理するクラウド型サービス「SPIDERPLUS」の開発・販売を行うスパイダープラス社長CEOの伊藤謙自氏は強調。同サービスは建設現場のデジタル化を推進する。
スマートフォンやタブレット端末があれば、建設現場の進捗管理や写真整理、報告書作成、図面を用いた打合せ、各種検査業務、遠隔での指示だし、点検業務などを一元管理できる。さらに、総合建築、空調衛生設備、電気設備など、建設工種別の検査に対応するオプション機能も設けていることが特徴だ。
現場監督の1日の作業は膨大だ。検査記録用の写真を撮影し、それらを整理し、まとめる。同時に、検査データもメモをし、書類に転記し、まとめなければならない。さらには現場の工程や人員、安全、資材など管理すべき業務は数限りない。しかも、それらは全て紙ベースだ。
加えて、現場では脚立などの工具もどこにあるか分からなくなりがちで、それを探すだけで時間と手間がかかる。年間の時間外労働時間に上限規制が課される「2024年問題」が叫ばれ、運送業界に注目が集まりがちだが、建設現場も例外ではなく、その対策が不可避。
21年度の建設業の雇用者数は393万人で、20年度比で約9万人減少しており、40年には300万人を割り込む見込みだ。一方で、建物の老朽化などを背景に、首都圏を中心に再開発プロジェクトや改修工事などは増えることはあっても減ることはない。いかに少ない人数で現場を回せるかどうかがカギになる。
伊藤氏は「建設現場で働く人たちの仕事を少しでも早く効率良くこなせるための縁の下の力持ちのような存在になりたい」と話すように、同社のサービスを使えば、現場で写真を撮影したり、情報を共有するための黒板を作らなくて済む。大量の紙図面を持ち歩く必要もなくなる。
前述の工具がどこにあるかといった課題も利用した人が記録として残せば、誰もが一目でどこにあるかが分かるようになる。実はこの利用シーンはスパイダープラスが想定したものではない。むしろ「現場の利用者が当社のサービスを創意工夫している」(伊藤氏)という。それだけ汎用性が高いことになる。複数の会社が導入すれば企業の垣根を超えて互いの工程管理を共有することも可能だ。そこが他のIT企業との違いでもある。
その結果、SPIDERPLUSは日本の建設現場における〝デファクトスタンダード〟になりつつある。昨今開業した「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」や福岡市天神エリアにおける都市再開発誘導事業〝天神ビッグバン〟の「福ビル」などの大型ビル、北海道の「エスコンフィールド」の建設現場など様々な大規模物件で使われる。
1日の削減時間は3時間以上
実際にSPIDERPLUSを導入した企業の1日の削減時間は平均3時間。1人当たりの月間導入効果は約20万円だ。大多数のユーザーが月に60時間以上の業務効率化を実現している。中には「1人で3人分の作業をこなせるようになった現場もある」(伊藤氏)ほどだ。
しかも、導入企業も大手ゼネコンとサブコンを含めて約1800社、6万人以上が利用。中でもゼネコンから空調衛生設備や電気設備の施工を請け負うサブコンでは「トップ100のうちの95%はSPIDERPLUSを導入している」(同)。
つまり、ゼネコンから空調衛生設備や電気設備の仕事を受けるサブコンにしてみれば、SPIDERPLUSを導入していない現場は避けたいということになる。人手不足が顕著となり、納期を間に合わすためにもサブコンの協力が必須なゼネコンも導入するようになるわけだ。
一方で、SPIDERPLUSと類似した製品をゼネコンが開発しようとすると、囲い込みの思想から、どうしても自社仕様・自社規格になってしまう。
伊藤謙自・スパイダープラス社長CEO
その点、スパイダープラスは、鴻池組や長谷工コーポレーション、きんでん、高砂熱学工業などの建設会社や専門工事会社と専門チームを組んで開発に当たっている。また、約13年にわたって「当社のエンジニアが建設現場に足を運び、現場で働く人のニーズを聞いて商品に落とし込み、機能を磨き上げてきた」と伊藤氏は語る。
同社は建設資材の商社で断熱材の販売に携わっていた伊藤氏が1997年に独立して創業。自ら建設現場で働いていたことで、建設業界のIT化の後れを感じ、業務の効率化を図るために、自分たちでITツールを作ることにした。2021年には建設DX銘柄として初めて東証マザーズ(現グロース)に上場。
23年12月期の売上高は33億円を見込み、利益面では先行投資で赤字を余儀なくされる中でも時価総額は約250億円。25年には通期黒字を目標に掲げる。伊藤氏は今後、数万社とも言われる地方の中小建設業者の獲得を目指し、「まずは契約者数とユーザー数を増やし、トップラインを上げていく」(同)方針だ。
3K(きつい、危険、汚い)のイメージが強かった建設業。デジタルな要素を組み込み、「スマートに仕事ができる世界をつくりたい」と話す伊藤氏の建設現場変革ビジネスである。