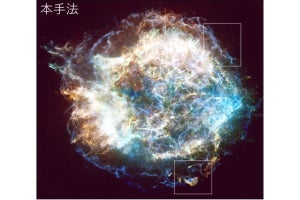東京大学(東大)、名古屋大学(名大)、夏目光学の3者は12月14日、2024年打ち上げ予定で、日米共同でのフレアの観測を目的とした太陽観測ロケット実験「FOXSI-4」に搭載されるX線望遠鏡用の高精度筒形ミラーを作製するための新技術を確立したと共同で発表した。
同成果は、東大 先端科学技術研究センターの三村秀和教授、同・山口豪太客員研究員、名大の三石郁之講師、同・作田皓基大学院生、同・安福千貴大学院生、同・藤井隆登大学院生、夏目光学 テクノロジーセンターの橋爪寛和取締役常務らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する科学機器・装置に関連する全般を扱う学術誌「Review of Scientific Instruments」に掲載された。
物理学的には、X線とガンマ線はエネルギーが同じなら区別がつかないようなどちらも波長の短い電磁波で、レントゲン撮影のように短時間なら有用な使い方もできるが、長時間の被ばくは身体に有害な放射線である。X線とガンマ線はその起源で区別されており、原子核内部起源であればガンマ線、そうでないものがX線となる。しかし天文学では扱いが異なり、観測波長のうちで紫外線よりもエネルギーの高い領域がX線であり、さらにその上がガンマ線となる。
宇宙には、膨大なエネルギーを放つ天体や天文現象などが数多く存在しており、X線を放つ天体は珍しくない。地球に届いた場合には大気が吸収してしまうため、我々が直接浴びる心配はないが、太陽も常にX線放っていて、そのほかにも、中性子星や超新星残骸なども放射源であり、ブラックホールの周囲で物質が光速に近い速度で回っている降着円盤やブラックホールから吹き出すジェットなどもX線を放つ。
天体からのX線を観測するには、当然ながらX線を捉えられる望遠鏡を用いる必要がある(それも大気圏外で)。しかし、可視光や赤外光などとは異なり、一般的なレンズやミラーなどの光学系では集光することが叶わない。そこでX線望遠鏡に用いるのが、筒型の内面が鏡面加工されたX線専用の「ウォルターミラー」で、この筒内の鏡面でX線を何度も反射させつつ、受光部まで導くのである。
宇宙X線望遠鏡の性能は、このウォルターミラーをどれだけ大型化できるか、そしてどれだけその筒内の鏡面加工を正確に作製できるかにある。しかし、鏡面加工にはナノメートルオーダーでの仕上げが求められるため、製作は容易ではないという。そうした中で研究チームは、めっき技術を応用した転写(レプリカ)手法の一種である「電鋳法」を用いたX線ミラー作製技術の開発に取り組んできたという。
電鋳法では、まずガラス製の型である「マンドレル」を作製。次に、電気めっきの原理でマンドレルの表面を覆うように厚さ0.5~2mmの「殻」を作る。この殻をマンドレルから引き抜くと、マンドレルの表面形状が殻の内側にコピーされ、円筒形のウォルターミラーが完成するという流れだ。なおマンドレルは繰り返し再利用できるため、たくさんのミラーを効率よく製作することが可能だとする。
殻を形成する際、副反応によりその表面に気泡が生じ、それが殻に穴欠陥を生じさせることでミラーの形状を歪めてしまう。ミラーが大きいほど穴欠陥の防止が難しくなるため、研究チームではこれまで、小指サイズの小さなミラーしか製作できなかったことが大きな課題だったという。しかし今回の研究では、日米共同でのフレア観測を目的とした太陽観測ロケット実験「FOXSI-4」のX線望遠鏡に用いられる、直径60mm×全長200mmという大型ウォルターミラーを、真空を利用した新しい気泡除去手法を用いて欠陥なしの高精度な作製を試みたとのことだ。
そしてミラー精度の指標の1つである「二乗平均平方根(RMS)形状誤差」を求めたところ、0.3μmという従来にない高い精度で作製されていることが確認できたとする。望遠鏡に搭載した場合の性能シミュレーションでは、約12秒角(約0.003度)の解像度を期待できることも判明。これは、欧米の研究チームの主導により開発されたX線望遠鏡の性能に比肩するものとする。さらに研究チームは、同一のマンドレルから3つのミラーを作製することにも成功し、開発された電鋳プロセスがミラー製造における有力な手法の1つであることが実証されたと結論付けている。
ウォルターミラーの精度向上は、X線望遠鏡の解像度向上に直結する。今回開発されたウォルターミラーはFOXSI-4への搭載が決定済みで、2024年の打ち上げを経て実観測が行われる予定だ。さらに、高効率な作製手法であるため、X線望遠鏡開発の低コスト化や、新しい観測技術のアイデアの実現に貢献できるとのこと。そして、次世代のX線望遠鏡ではさらに高い性能が求められるため、この高精度かつ高効率なミラー製造技術は、今後のX線天文学の発展にとってますます重要になるとしている。