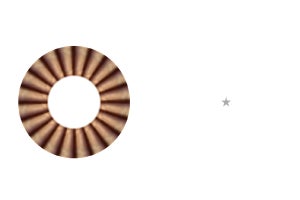基礎生物学研究所(NIBB)は12月5日、自分自身の身体や周囲の物体などの動きの知覚を引き起こす最小ユニットデザインが脳内に存在し、その足し合わせで動きを知覚しているとする「足し算則」仮説を検証するため、4色構成の「静止しているのに動いて見える錯視画像」を3色に分解し、被験者にさまざまな3色および4色デザインを提示して、それらが引き起こす知覚的な運動速度を計測した結果、3色デザインから得られたデータと仮説をもとにした数式によって、4色デザインの知覚速度を精度よく予測できることがわかり、足し算則による動きの情報統合が脳の普遍的な仕組みであることが示唆されたと発表した。
同成果は、NIBB 神経生理学研究室の小林汰輔特任助教(現・玉川大学 研究員)、同・渡辺英治准教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
静止画であるにもかかわらず動いて見える不思議な錯視画像は、1979年に海外の研究者によって初めて報告され、近年は錯視研究の第一人者として知られる立命館大学の北岡明佳教授による作品「蛇の回転錯視」などにより広く知られている。同作品は4色錯視にあたり、とても大きな動きの錯覚を生み出す点を特徴とする。“経験的に”多くの人は、3色錯視よりも4色錯視の方がより大きく動いて見えるといわれている。
-
立命館大学の北岡明佳教授の作品「蛇の回転錯視」。白青黒黄の4色デザインの錯視でとても大きな動きの錯覚が生み出される。4色の並び順(2つの3色デザインが組み合わされている)によって、右回転や左回転が決まり、また大きな動きの錯覚を生み出されている。(c)Akiyoshi Kitaoka(出所:NIBB Webサイト)
この現象の発生原因は、異なる明るさを見た時の神経細胞の応答の違いによるものと考えられているとのこと。この偽の動き情報の発生原因は、光を受け取る眼球や眼球に近い脳のより浅い部位に潜んでいるとされ、そこで検出された偽の動き情報がより脳の奥まで伝播されることで、実際に動いて見えると認識されるという。このとき脳の奥に進むほど、眼球上の各神経細胞で検出された光の情報が集約、そして統合されるが、この統合が脳の各領域でどのように行われているのかについては錯覚のみならず、視覚の研究分野全体においてもまだ詳細はわかっていない。そこで研究チームは今回、この錯視現象を通して、動き情報の統合メカニズムを調べる心理実験を行ったという。
-
錯視画像と知覚される動きの足し合わせのイメージ。3色で構成された画像(A)と(B)はそれぞれ異なる方向に動きが生じる。(C)の画像では、(B)の模様の向きを反転させて、(A)と組み合わせて動きの向きを同じにすることでより大きな動きを生じさせている。今回の研究では、(C)の知覚速度は(A)と(B)の知覚速度の足し合わせで簡単に求めることができるという仮説が検証された(出所:NIBB Webサイト)
足し算則が仮に成立するのであれば、3色錯視画像の知覚を測定することで、4色錯視画像の知覚は自動的に計算で予測できるはずだとする。その上で実際に4色錯視画像の知覚を測定し、予測と本当の知覚データとを比較することで、足し算則を検証することが可能だという。
今回の実験では、5名の被験者に対する心理実験が行われ、提示された錯視画像の知覚速度が計測された。刺激は3色および4色の錯視画像を提示した時に、左と右のどちらに回転して見えるかを被験者が回答。この時、画像は停止したまま提示させるのではなく、意図的に左か右にさまざまな速度で回転させており、今回の実験では、錯視の動きと実際に回転させる動きをキャンセルさせる条件を調べることで、錯視画像の知覚速度の計測が行われた。
-
(A)心理実験のイメージ。今回の錯覚現象は目の端で見た場合に生じるため、実験で被験者は画面中央の十字を見るよう指示された。そして、実験では1つの刺激に対し、さまざまな速度で回転させた状態で画像が提示された際に、どちらに回転しているかを回答。最終的に「左に回転した」と答えた確率を集計し、(B)のような心理曲線のグラフが作成された。左と答えた確率が50%の時が、錯視の動きをキャンセルさせる回転速度を示すが、人によっては「回答に困ったら右と答えよう」と考える人がいるなど、正しい速度が計算できない可能性もあるため、鏡対象の刺激も用意して実験で同時に2つの画像の心理曲線(Bの赤と青)が作成された。最終的には、この2つのグラフが離れている距離からキャンセルさせる速度を算出して、答えの偏りを打ち消すようにしている(出所:NIBB Webサイト)
そして研究チームは足し算則に基づいて、3色画像の知覚速度から4色画像の知覚速度を求めたとのこと。その結果、知覚速度をうまく予測できていることが判明した。なお、この錯視の知覚速度は個人差が大きく、今のところそれを説明することは難しいとするものの、今回の検証で示された足し算の情報統合は個人差のない普遍的な仕組みであることが確かめられたとしている。
-
実験結果。実験では被験者に提示された4色の刺激のうち、1つの色の輝度を変化させて、その時の知覚速度が計測された(赤線)。縦軸は知覚速度、横軸はその変化させた色の輝度。グラフは被験者別。実験結果に個人差はあるが、色の輝度の変化に相関して錯視の速度が変化している様子が見て取れる。黒線が3色の錯視画像の実験データから計算された予測値で、実測値である赤線とよく一致しており、足し算則が成立していることがわかる(出所:NIBB Webサイト)
動きの知覚能力は、交通事故を未然に防ぐなど危険予測をする上でとても重要な能力だ。しかし、この能力は現時点では視力検査のような単純な検査を行うのみで測ることは難しく、引き続き基礎的な研究によって脳の仕組みを解き明かしていく必要があるとしている。
また今回の実験は、人工ニューラルネットワークを視覚シミュレータとして用いて、事前に足し算則仮説の検証を実施したことがきっかけで立案されたという。これまでは錯視のような脳に関する研究は心理実験を行うしかなかったが、それには多くの労力が必要であり、より慎重に検証を進める必要もある。しかし今後は、人工ニューラルネットワークを利用することで、より円滑に研究が進展する場面も出てくるようになるだろうとしている。
また、人工ニューラルネットワークそのもので何が行われているかを調べる解析技術を開発することによって、ヒトでは直接調べることができない知見を見つけることも可能になるだろうとし、今回の心理実験のような実際にヒトに参加してもらう実験と、コンピュータシミュレーションの2つのアプローチの両輪によって、脳の仕組みの理解を深めることが期待されるとした。