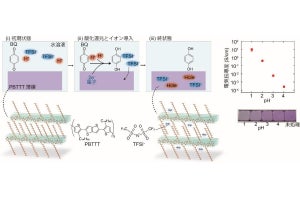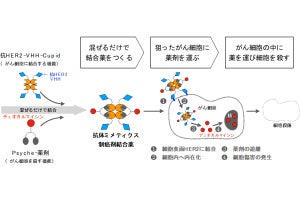東京大学(東大)は10月20日、宇宙誕生時の超高温時に実現していたと考えられている素粒子の大統一に迫ることを目的とした国際共同実験「MEG II」において、前身の実験「MEG」より大幅に性能を向上させた検出器と、スイス・ポールシェラー研究所(PSI)の強い強度のミュー粒子(ミューオンとも)ビームを用いて、同粒子の稀な現象「ミューイーガンマ(μ→eγ)崩壊」の探索を行い、今回は発見できなかったが、MEG実験の結果と合わせ同崩壊現象の起こる確率について、約3兆分の1の頻度という厳しい制限を与えたと発表した。
同成果は、東大 素粒子物理国際研究センター(ICEPP)の森俊則教授を中心とする、日本・スイス・イタリア・米国・英国などの研究者が参加したコラボレーションMEG IIによるもの。詳細は、国際ワークショップ「BRIDGE 2023」にて発表された。
ミュー粒子は、電子に次ぐ第二世代の荷電レプトン(軽粒子)だ。μ→eγ崩壊とは、ミュー粒子がガンマ線を放出して電子に崩壊する過程のことをいう。同崩壊は、エネルギー保存則などの通常の物理法則では禁止されていないが、素粒子の標準理論においては、荷電レプトン(電子、ミュー粒子、タウ粒子)は「フレーバー」(種類)が保存され、世代間の移り変わりは禁止されている。
-
3世代の素粒子の概要。クォークは小林・益川理論により、ニュートリノはニュートリノ振動により異なる世代間の移り変わりがある。それに対し、電子の仲間の荷電レプトンでは、世代間の移り変わりは標準理論では禁止されている。もし、μ→eγ崩壊が発見されれば、電子の仲間でも世代間の移り変わりがあることになり、大統一理論の証拠となると考えられている(出所:東大 ICEPP Webサイト)
1990年代後半に、μ→eγ崩壊が重力を除く3つの力を扱う「大統一理論」(未完成理論)によって引き起こされることが指摘された(μ→eγ崩壊の発見は大統一理論の証拠となるとされる)。しかしその確率は約1兆分の1であり、既存の検出器では発見は不可能と考えられていたという。
そうした中、前身のMEG実験ではその不可能が覆され、約2兆分の1の感度でμ→eγ崩壊探索が行われた。2016年に同崩壊は発見されなかったという最終結果が発表されたが、標準理論を超える「超対称大統一理論」などの可能性に関して、これまでにない厳しい制限が加えられたのである。
そこで今度は、検出器の性能を大きく向上させたMEG II実験が実施されることとなった。検出器が再設計され、またMEG実験では利用できなかった最新のセンサ技術が導入されるなどにより、粒子の測定精度および検出効率が大幅に改善。MEG実験の約10倍の感度でμ→eγ探索が行われた。
MEG II実験装置の主要な「ガンマ線検出器」は、MEG実験における液体キセノン検出器の光センサである光電子増倍管の一部が、新たに浜松ホトニクスと共同開発された新型半導体光センサ「VUV-MPPC」に置き換えられ、ガンマ線イメージングの解像度が大きく向上。「陽電子検出器」については、コンパクトな新型半導体光センサを用いた新型が導入され、時間測定性能を2倍以上改善。それと同時に、一体型の「円筒状ドリフトチェンバー飛跡検出器」が開発され、運動量測定性能が4倍、検出効率が2倍に改善された。その上、μ→eγ崩壊探索の主要な背景ガンマ線を抑制する完全新規の検出器も導入された。
MEG II実験装置は2021年に完成し、同年9月末より約7週間、最初のデータ取得が行われた(今回の発表はそのデータが使われている)。今回もμ→eγ崩壊は発見されなかったが、短期間のデータ取得にも関わらず、MEG実験の最終結果に迫る感度が達成された。さらに、今回の解析結果とMEG実験の結果を統合した解析も行われ、同崩壊について、約3兆分の1の頻度という、これまでで最も厳しい制限が与えられた。これにより、超対称大統一理論などの新物理の可能性がさらに厳しく検証されることとなった。
-
ミューオンを用いた研究による新物理探索の歴史。前実験より約30倍の探索感度を実現したMEG実験によって、超対称大統一理論など、標準理論を超える新物理理論を検証することが可能となった。アップグレード実験のMEG IIではさらに感度を10倍上げた探索が実現された(出所:東大 ICEPP Webサイト)
MEG II実験は2021年9月以降、毎年安定した長期データ取得を行って順調に探索データを蓄積中だという。2022年までのデータですでにMEG実験の探索感度を大きく上回っており、2023年度中にその探索結果を公表することを目指して解析が続けられている。
同じ実験エリアを使用予定のほかの実験プロジェクトの動向にも依存するが、今後MEG II実験は2026年までデータ取得が継続され、最終的にはMEG実験の約10倍の探索感度(17兆分の1の頻度)を達成する予定であり、μ→eγ崩壊の発見が大きく期待されるとした。
-
(左上)PSIビームラインに設置されたMEG II実験装置。(右上)液体キセノンガンマ線検出器。(左下)陽電子タイミングカウンター。(右下)陽電子ドリフトチェンバー飛跡検出器(出所:東大 ICEPP Webサイト)
現在、PSIのミュー粒子ビーム強度をさらに100倍増強する「HIMB計画」が進行中で、2027~2028年にその完成が予定されている。研究チームでは、この増強ビームを利用して、MEG II実験のさらに数10倍高い実験感度を持つ新たなμ→eγ探索実験の実現を目指した研究開発をスタートさせたという。この将来実験では、μ→eγ崩壊の発見をより確実なものにするのと同時に、同崩壊の角度分布などその詳細を測定することで、背後にある宇宙初期の新理論の正体を解明することを目指すとしている。