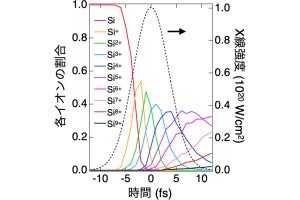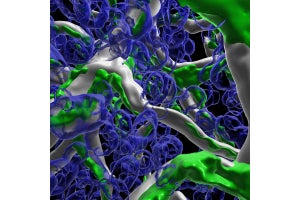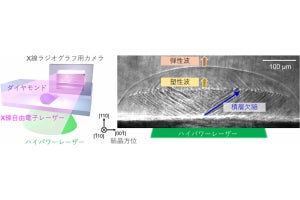名古屋大学(名大)は10月20日、手術前のデータを用いて、「慢性硬膜下血腫」患者における手術後の身体機能の状態を高精度に予測するAIモデルを開発したことを発表した。
同成果は、名大大学院 医学系研究科 脳神経外科学の齋藤竜太教授、同・永島吉孝病院助教、同・布施佑太郎大学院生、名大大学院 医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター 神経疾患病態統御部門の大野欽司教授、同・大学院 医学系研究科 附属医学教育研究支援センター 先端領域支援部門の西脇寛助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
慢性硬膜下血腫は頭部への外傷を引き金として、徐々に脳の表面を覆う硬膜と脳自体の間にゆっくりと血が溜まるという特徴を持ち、主に高齢者がかかる疾患だ。その結果、認知機能の低下や麻痺、さらには意識状態の悪化といった重篤な症状を引き起こしてしまうことが知られている。
慢性硬膜下血腫は、加齢により脳の体積が少しずつ縮小し、脳と硬膜の間に空間ができることが関与していると考えられており、わずかな外傷でも血腫ができるリスクが生じる。同疾患の初期段階での症状は軽微であることが多く、そのために気づきにくいことがあり、早期の診断と治療が重要とされている。
慢性硬膜下血腫の主な治療法は手術であり、認知機能や運動機能の改善が期待され、結果として命を救うと同時にQOLの維持、またはその向上が期待されるという。しかし日本の実情として、手術を受けた患者の約3分の1が手術後も十分な身体機能の回復が確認されず、術後早期からの自宅での生活が難しいという課題があった。
このような背景から、患者本人やその家族のため、診断を受けてからなるべく早い段階で術後の生活の展望を正確に把握することが重要とされている。術後の身体機能の正確な回復予測を行えれば、医療資源を効果的に活用し、患者や家族への適切な情報提供、さらにはサポート体制の最適化などが可能となり、社会全体の医療サービスの質向上にも寄与することができるとする。
これまでの研究により、手術後の身体機能の回復に関わるいくつかの要因が解明されている。それにも関わらず、これらの要因を基にした統計的な手法での予測は、まだ十分な精度を持っているとはいえないという。そのため、術後の身体機能を簡便かつ正確に予測する新しいモデルの開発が急務とされていた。
そこで研究チームは今回、名大関連病院で治療を受けた慢性硬膜下血腫患者に関する臨床情報を基に、AIモデルを用いて術後の身体機能の予後を予測するための手法を開発することにしたという。
今夏の研究においてAIモデルの訓練は、手術前に利用可能な血液検査や頭部画像検査、背景因子、身体所見などの臨床情報から抽出された52種類の因子を基に行われた。術後の身体機能の判定基準として、「修正Rankin Scale」(mRS)を用いて、術後の身体機能(mRS3-6)を予測させたとする。
4種類のAIモデルの訓練が行われ、予測指標0.906~0.925の範囲で高い予測能が示されたとした。次に、ほかの施設データを用いて、同じ4つのAIモデルの検証が行われ、再現性と信頼性が確認された。その際も、予測指標0.833~0.860の範囲で一貫した性能を維持していたという。4種類のうちで、最も良かったものの精度は91.9%だった。これは、同手法が異なる医療機関や地域でも有効である可能性が高いことを示唆しているとした。
今回のAIモデルの訓練に用いられた臨床情報因子の中で、特に年齢や入院時の意識状態、血漿タンパク質の内で約60%を占める重要な「アルブミン」の値などが、予測結果に強い影響を持つことが確認されたとする。これらの因子を重点的に評価することで、より治療の現場に即したツールになる可能性が示されたとした。
慢性硬膜下血腫の治療は、単に手術の実施だけでは十分ではない。周術期管理、特に手術後のリハビリテーションが不可欠であり、その最適化が求められている。今回開発された予測モデルにより、どのような患者に術後の身体機能の回復を目指したサポートや管理が必要なのかを把握できる可能性が示されたとする。研究チームは今後、多施設での共同研究を通じて、よりさまざまな患者のデータに基づいて最適化された治療プランの提供を目指すとした。この取り組みは、患者個人ごとの状態やニーズに合わせた治療の提供、そしてそれに伴う治療成果の向上をもたらすことを目標としているという。
また、今回のAIモデルの技術的な側面の展開も考慮中とする。同モデルの基盤となるアルゴリズムは、ほかの疾患や手術に関するアウトカムにも応用可能であり、さまざまな疾患における個別化医療の実現への一助となることが期待されるとした。