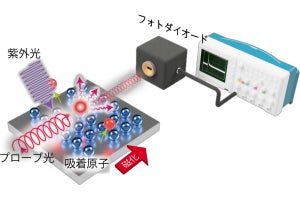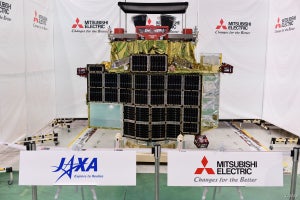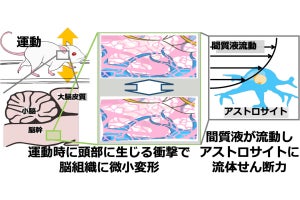東京農工大学(農工大)とティー・エイ・インスツルメント・ジャパンの両者は9月27日、流体界面の「大振幅振動せん断(LAOS)レオロジー測定」による結果を用いた物理現象の解明に成功したことを共同で発表した。
同成果は、農工大大学院 生物システム応用科学府 生物機能システム科学専攻の八木晴美大学院生、同・大学大学院 工学研究院応用化学部門の長津雄一郎教授、ティー・エイ・インスツルメント・ジャパンの髙野雅嘉氏、農工大大学院 グローバルイノベーション研究院の鈴木龍汰特任助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、レオロジー協会が刊行する物理や化学などの理論的および実験的問題を学際的にカバーする学術誌「Journal of Rheology」に掲載された。
レオロジーとは、物質の変形と流動を扱う学問分野のことで、流動学とも呼ばれ、物質の粘弾性の測定方法の代表的な1つに「動的粘弾性測定」がある。同測定は、物質に、正弦波状の「せん断歪み(ひずみ)」を与え、その時に物質に生じるせん断応力の挙動から、粘弾性を測定するというものだ。
そして、正弦波状の応力挙動が得られる十分小さい振幅で行われる測定は、「微小振幅せん断」(SAOS)測定と呼ばれ、大きな変形下での粘弾性挙動の予測には適さないことがしばしば指摘されていた。そこで2000年ごろに、正弦波状の応力挙動が得られない、大きな振幅で行われる測定である「大振幅せん断」(LAOS)測定が開発されたという経緯がある。
粘弾性測定は、物質そのものの粘弾性を測定する「バルク粘弾性測定」と、その別の物体との界面の粘弾性を測定する「界面粘弾性測定」の2通りがある。界面の粘弾性特性は、バルクのそれと異なることがあると指摘されるようになり、2000年ごろまでに新たに「界面レオロジー」という分野が定着した歴史がある。
これまで界面レオロジーの動的粘弾性測定は、マテリアル分野で採用されることが多くSAOS測定が用いられることが大半だったが、近年では界面SAOS測定が界面での相変化の検出に用いられるなど、その応用範囲が拡大中だ。それに対し、界面LAOS測定の事例は非常に少なく、その有用性や必要性は、懐疑的と考えられていたという。
そこで研究チームは今回、ヘレ・ショウセル内で、粘性の高い流体が粘性の低い流体に押しのけられる時に、2流体の界面が指状に成長する「粘性フィンガリング現象」を対象に、ゲル生成反応を伴う液体流動実験を行うことにしたとする。具体的には、高粘性液体に「キタンサンガム(XG)水溶液」を、低粘性液体にグリセリン20wt%を含む種々濃度の硝酸鉄水溶液を用いたという。(グリセリンは、後述する高精度な界面LAOS測定のため、2液体に十分な密度差を付与するために加えられた)。
-
高粘性液体を満たしたヘレ・ショウセル(非常に小さい距離(0.5mm)だけ離れて設置された2枚の平行なガラス板)に低粘性液体を一点より注入すると、それらの界面は流体力学的に不安定になり指状に広がる。実験では観察を容易にするため、高粘性溶液であるXG水溶液がインディゴカルミンで染色されている(出所:農工大プレスリリースPDF)
種々の硝酸鉄濃度と注入流量の条件で実験を行うと、粘性フィンガリングパターンと1点もしくは2、3点から低粘性液体が成長するような「フラクチャー」という、2種類のパターンに分けられることを発見。そして、この流動パターンの違いは、2液体の反応粘弾性界面のSAOS測定から得られる結果では説明できないことが判明し、流動条件と同様に大変形を与えることができる界面LAOS測定から得られる結果により説明できることが明らかにされた。
-
流動実験結果。硝酸鉄濃度が上から0M(非反応系)、0.01M、0.05M、0.10M、0.15Mで、注入流量が左から、基準の値(q0=4.2×10-9m3/s)の、1倍、1.25倍、1.50倍、2倍、3倍、5倍の時の結果(高粘性液体はすべて0.3wt%XG水溶液)。背景が薄い青の結果が粘性フィンガリングパターンが、薄い黄色の結果がフラクチャーパターンが示されている(出所:農工大プレスリリースPDF)
-
界面LAOS測定の装置模式図。二重円筒のような構造の装置の下に密度の大きなグリセリンを含む硝酸鉄水溶液が設置され、その上にセンサが設置されている。さらに、硝酸鉄水溶液とセンサの上にXG水溶液が設置され、界面で粘弾性物質生成反応が起こるようにする。設置されたセンサで界面LAOS測定が行われる。(出所:農工大プレスリリースPDF)
また、界面LAOS測定では「リサージュ曲線」を得るためその結果を解析、大変形下での界面弾性力と界面粘性力を算出し、それらの値と流動パターンとの関係を調べると、界面粘性力の大きさによらず、界面弾性力がある閾値を越える時に、粘性フィンガリングからフラクチャーにパターンが遷移することが明らかにされた。
-
界面LAOS測定の結果。硝酸鉄水溶液の濃度が(a)0M、(b)0.01M、(c)0.05M、(d)0.10M、(e)0.15Mの時の結果。各グラフの横軸は与えられた歪みの大きさが、縦軸はセンサが感知した応力の大きさが示されている。色の違いは、設定された最大の歪みの大きさが示されている。得られたパターンが円の場合は粘性的な性質が、直線的な場合は弾性的な性質が示されている。(a)では、円形に近く、非反応系では、界面が粘性的であることが示されている。一方(b~d)では、直線に近く、界面が弾性を有していることが示されている(出所:農工大プレスリリースPDF)
-
界面粘性力と界面弾性力によるパターン遷移。背景が青の領域では粘性フィンガリング(VF)パターンを示し、黄色の領域ではフラクチャーパターンが示されている。この図から、界面粘性力によらず、界面弾性力によってパターンが遷移していることがわかる(出所:農工大プレスリリースPDF)
今回の研究成果は、界面での反応で粘弾性物質が生成される流動では大変形下での粘弾性界面のレオロジーが決定的な役割を果たしていることを示すものだとする。このことは、反応界面LAOS測定が界面での反応で粘弾性物質が生成される流動の研究で有用であることが示されており、今後ほかの溶液・反応系での界面での反応で粘弾性物質が生成される流動に対しても、界面LAOS測定を用いた現象解明が可能なのか、また界面LAOS測定を用いた検討が有用であるかといった検証を進めたいとしている。