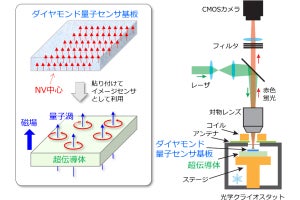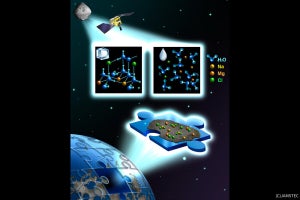東京大学(東大)、筑波大学、北里大学、理化学研究所(理研)の4者は9月21日、電子伝導性と大面積塗布の両側面を兼ね備えた新たな電子輸送性(n型)有機半導体の開発に成功したことを共同で発表した。
同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の岡本敏宏准教授(現・東京工業大学(東工大) 物質理工学院 応用化学系 教授)、同・ユー・クレイグ・ペイチ特任助教(研究当時)、同・熊谷翔平特任助教(現・東工大 物質理工学院 応用化学系 特任准教授)、同・竹谷純一教授、筑波大 数理物質系の石井宏幸准教授、北里大 理学部の渡辺豪准教授(現・北里大 未来工学部 教授)、理研 創発物性科学研究センターの橋爪大輔チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、物理・化学・医学・生命科学・工学などの基礎から応用までを扱う学際的なオープンアクセスジャーナル「Advanced Science」に掲載された。
弱くて可逆的な分子間力によりパイ電子系分子が結びついた有機半導体では、分子軌道の弱い重なりを介して電荷輸送が行われる。そのため、有機半導体では電荷移動度が1cm2V-1s-1を下回ることも多く、実際のデバイスに応用する際に大きな課題となっていた。
そうした中で、広範囲で分子が規則正しく整列した単結晶を用いて、有機半導体の移動度の高速化が実現され、近年は、有機半導体分子を溶かした溶液を塗ることで大面積の有機半導体単結晶を製成し、高性能な有機電界効果トランジスタ(OFET)を開発する研究が活発化している。
ただし、それらの研究では正孔を輸送するp型有機半導体が主役であり、塗布法への親和性から移動度に至るまで、n型有機半導体での開発はp型有機半導体に比べ大幅に後れを取っていた。高移動度かつ有機溶媒への溶解性を両立するn型有機半導体の開発が強く望まれていたのである。
そこで研究チームが着目したのが、以前に開発した高性能なn型有機半導体「PhC2-BQQDI」だった。同有機半導体の結晶構造では、2つのフェネチル基が重要な役割を担う。今回の研究では、一方をより柔軟なアルキル基に置き換えることで、結晶構造制御を担うフェネチル基と溶解性の向上を担うアルキル基とが協同的に機能し、大面積塗布法に対する適性と優れたOFET特性を兼ね備えた有機半導体を開発するという考察が行われた。そして、異なる置換基を持つ非対称な分子を合成するため、フェネチル基とアルキル基を逐次的に導入する新規合成法を考案することにしたという。
この手法により、フェネチル基および長さの異なるアルキル基が導入され、その結晶構造の解析が行われた。すると、炭素数5の「PhC2-BQQDI-C5」において、炭素数5のアルキル基は対岸のフェネチル基の一部を模倣したコンホメーションとなることがわかった。なおコンホメーションとは、アルキル鎖などで見られる、単結合周囲の回転によって取り得る原子の特定の配置のことをいう。
このことはつまり、結晶中で、PhC2-BQQDI-C5分子はPhC2-BQQDIを分子模倣した形で存在しており、そのため、結晶構造全体でよく似た規則構造を形成することが判明したのである。これは、フェネチル基と同程度の長さを持つアルキル基を導入することではじめて発見された現象だ。
さらに、溶解性の向上に加え、規則正しい結晶構造を実現できたことで、PhC2-BQQDI-C5を用いることで塗布法による大面積単結晶の製膜が可能となったという。現時点では、数mmからcm級の大きさの単結晶を製膜することに成功しており、OFETを作製し評価することで、大気下で1cm2V-1s-1を超える移動度が計測されたとする。さらに、柔軟なアルキル基を導入したにも関わらず、PhC2-BQQDI-C5から成るOFETはPhC2-BQQDIと同様に優れた大気安定性や熱ストレス耐性も示すことが確認された。
これらのことから、分子模倣を上手く取り入れることで、本来柔軟なものを堅牢にすることが可能であり、実用性に優れた有機半導体材料に有用であることが解明されたとした。
今回の分子模倣のコンセプトにより、電子伝導性と塗布プロセス性とのいいとこ取りを叶える、さらに高性能な有機半導体材料の開発が期待されるという。また、塗布法による大面積単結晶の作製が進展することで、プリンテッドエレクトロニクスと大面積エレクトロニクスとの懸け橋となり、さまざまなハイエンドデバイスや、未利用エネルギーを活用するエネルギーハーベストなど、有機エレクトロニクス分野の研究開発を加速することが期待されるとした。