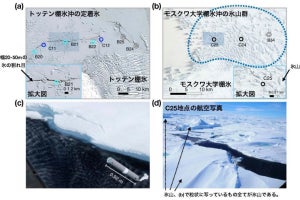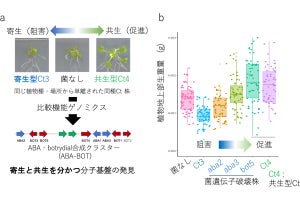北海道大学(北大)は9月14日、クマノミ類において孵化海域での仔魚の滞留が単純な地形条件では決まらず、海流の強さが大きく影響することを明らかにしたと発表した。
同成果は、北大 北方生物圏フィールド科学センターの仲岡雅裕教授、同・大学大学院 環境科学院の佐藤允昭大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、陸水学と海洋学に関する全般を扱う学術誌「Limnology and Oceanography」に掲載された。
多くの海洋動物は卵から孵化して数時間から数十日の間は浮遊生活を送り、その期間中に生まれた場所から新たな生息場に浮遊分散していく。浮遊分散は着底後の個体数に大きく影響するため、海洋生物の保全や水産種の資源管理においても重要な生活史のステージだといえるという。
イソギンチャクに棲むクマノミ類は水中で発見しやすいことから、これまでDNAを用いた親子鑑定により仔魚の分散が調べられてきた。仔魚の分散には地形や海流が影響すると考えられ、外洋と限られた水路だけでつながる閉鎖性の湾では仔魚が滞留しやすく、一方、開放性海岸では強い海流により仔魚が遠くまで運ばれることが予想されているが、実際には仔魚の分散・滞留に対する地形や海流の影響の詳細は不明だった。
そこで今回の研究では、クマノミ類の「ハマクマノミ」と「ハナビラクマノミ」を対象に、フィリピンのミンドロ島プエルトガレラの半閉鎖性湾と、ミンダナオ島ラギィンディンガンの開放性海岸という対照的な2海域において、DNAを用いた親子鑑定により実際の仔魚の分散を把握。さらに、海水流動モデルを用いた分散シミュレーションにより、同様の仔魚の分散パターンが再現できるのかという検証を行うことにしたという。
-
(左)クマノミ類の浮遊分散における調査地内に滞留する仔魚と、外部から移入する仔魚の模式図。(右)DNAの親子鑑定により推定された、半閉鎖性湾と開放性海岸における外部から移入したハマクマノミの稚魚の個体数(青字)と、調査地生まれの稚魚(滞留稚魚)の個体数(赤字)および調査前の予想と実際の結果。地図中の小点はサンプルが採集されたイソギンチャクの位置(出所:北大プレスリリースPDF)
潜水調査によりイソギンチャクに棲むクマノミ類の繁殖個体と稚魚個体のサンプルが集められ、両者の間でマイクロサテライトDNAの親子鑑定が行われた。マイクロサテライトDNAとは、核DNA中に多く含まれる2~4塩基程度の長さの配列が複数回反復している部分のことで、その反復回数が個体ごとに異なることから個体識別や親子鑑定、集団識別に利用されている。
クマノミ類は成長に伴い性転換し、1つのイソギンチャクに棲む集団内で最も大きな個体が雌、次に大きな個体が雄として繁殖するので、両個体が繁殖個体3cm以下の小さな個体が稚魚個体とされた。雌雄以外の個体は繁殖の順番待ちをしている状態で、同じイソギンチャクに親子が一緒に暮らすことは無いという。今回の親子鑑定で親子と判断されると、この稚魚は親がいるイソギンチャクで産まれて、採集された場所まで浮遊分散したのだとわかるとする。また、海域内の繁殖個体と親子関係が無いと判断されると外部から移入してきたと考えられるという。
両海域の地形、潮汐、風、水温、塩分などを加味した海水流動モデルが構築され、モデル上で調査地とその外の周囲からクマノミ類の仔魚に見立てた粒子を放出し、どのように分散するのかがシミュレーションされた。
親子鑑定の結果、半閉鎖性湾では採集した稚魚個体のすべてが繁殖個体と関係が無く(ハマクマノミ:48稚魚中0稚魚、ハナビラクマノミ:17稚魚中0稚魚)、すべてが外部から移入していたことが判明。一方、開放性海岸では14~15%ほどの稚魚が調査地の繁殖個体と親子関係にあり(ハマクマノミ:125稚魚中19稚魚、ハナビラクマノミ:324稚魚中46稚魚)、調査地で産まれた仔魚が加入していることがわかった。
-
(左)海水流動モデル上での沖方向への海水の流速平均。(中)クマノミ類の仔魚に見立てた粒子の挙動のシミュレーションを基にした、調査海域への加入粒子のうち、滞留粒子の割合。(右)調査海域での放出粒子のうち、滞留粒子の割合の半閉鎖性湾(湾)と開放性海岸(海岸)の比較(出所:北大プレスリリースPDF)
海水流動モデルによるシミュレーションの結果では、沖合方向への海流の強さは半閉鎖性湾で開放性海岸よりも強く、調査海域に加入した粒子のうちの滞留粒子の割合と、調査海域で放出した粒子のうち滞留するものの割合ともに半閉鎖性湾で低いことが明らかにされた。この傾向は親子鑑定の結果と一致しているという。半閉鎖性湾の方が沖合方向への海流が強く仔魚が沖合に流され、孵化海域での滞留が減ることがシミュレーションでも示されたとした。
海洋生物の保全や水産重要種の管理を目的として、国内外の海域で海洋保護区(禁漁区)が設置されており、近年では海洋生物の浮遊分散によるつながりを高めるように保護区を設定することの重要性が認識されつつあるという。海流を計測し、その影響を加味して仔魚分散によるつながを高めるように、海洋保護区の大きさや保護区間の距離を設定することが重要と考えられるとしている。