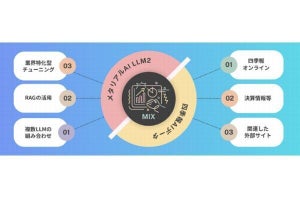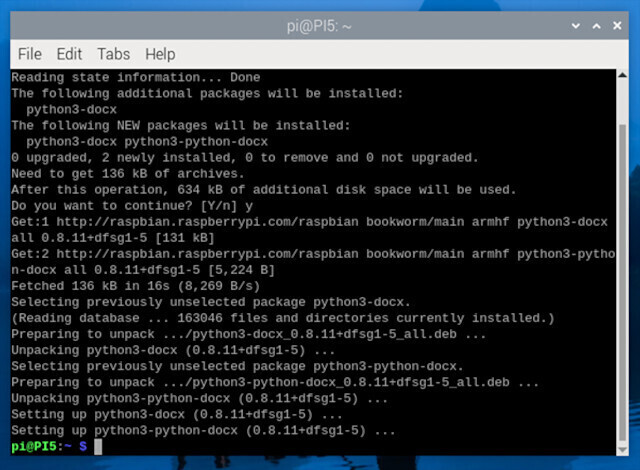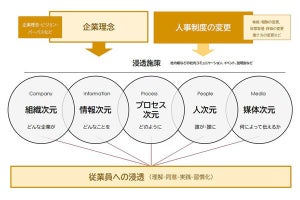パーソル総合研究所が9月12日に発表した「ワーケーションに関する定量調査」の結果によると、4人に3人が無自覚にワーケーションを経験しており、隠れワーケーションは14.1%に上ったことが分かった。
同調査は同社が6月5日~13日にかけて、まず全国における勤務先の従業員が10人以上の20~69歳男女従業員10万9034人に対してスクリーニング調査を実施し、本調査として直近半年未満のワーケーション経験者3500人およびワーケーション未経験者1000人を対象に、調査会社モニターを用いたインターネット定量調査として実施したもの。
ワーケーションを類型化したところ、個人単位で行うワーケーション(個人ワーケーション)5タイプと、グループ単位で行うワーケーション(グループ・ワーケーション)3タイプとなった。
職場や自宅とは異なる常生活圏外の場所で仕事と自分の時間を過ごした経験を尋ねると、17.4%が経験ありと回答した。そのタイプを見たところ、個人ワーケーションが67.6%を占める。
個人ワーケーションのタイプでは、家族旅行中に仕事をした「他社奉仕タイプ」が41.7%と最も多い。
日常生活圏外の場所で仕事と自分の時間を過ごした経験者にワーケーションの経験有無を質問したところ、「経験した」との回答は25.9%に過ぎず、経験者の4人に3人ほどは自分がワーケーションしたと自覚していない。
無自覚を含むワーケーション経験者のうち、14.1%が他のメンバーに隠れてワーケーション(隠れワーケーション)を行っている。
特に、「息抜き集中」「仕事浸食」「動機低め」タイプは、5人に1人が隠れワーケーションを行っている傾向にある。
ワーケーションを容認している企業(と認知されている割合)はおよそ半数であり、残りの半数はワーケーションの方針が出ていないか、禁止されている中でワーケーションを行っている。
隠れワーケーションは、チームワークの悪い組織や私的コミュニケーションが少ないチームで発生しやすい傾向が見られた。
ワーケーションでの滞在期間中に有給休暇を充てた割合は、個人/グループ・ワーケーションのいずれも約約44%だった。
就業者の主観的生産性を見たところ、ワーケーション期間中は普段の仕事の出来と比べて6~7割程度の生産性しか発揮できていない。
ワーケーション中に感じたメリットを尋ねると、職務効力感は4割前後と観光群よりも20ポイントほど高い一方で、健康回復は観光群よりも20ポイントほど低い。
ワーケーション後に仕事における意識・行動の変化や成果につながった割合は4~5割程度で、観光群よりも30ポイントほど高かった。
同社は回答者の勤務先についてチーム・バーチャリティ(チーム内でPCやインターネットなどのテクノロジーを利用したコミュニケーションを取りながら、メンバー同士が対面せず地理的に離れた場所で活動すること)の度合いにより、「分散型組織」「ハイブリット型組織」「対面型組織」の3つに分類した。
分散型組織の割合はワーケーション経験者の約4割を占め、ワーケーション後の組織コミットメントを確認したところ、分散型組織におけるグループ・ワーケーションのスコアが最も高かった。
ワーケーション後の変化・成果、ワーク・エンゲージメントにおいても、分散型組織におけるグループ・ワーケーションが最も高い。
ワーケーション後の効果を高める要因としては、ワーケーション後の効果を高める上で、ワーケーション中に感じる職務効力感を高めることがポイントとなると同社は分析する。
職務効力感を高める要素として同社は、ワーケーション中の非日常感、体験の多さ、現地交流の体験、偶発的な体験を挙げる。また、体験の多さ、現地交流の体験、偶発的な体験は、非日常感に対してもプラスの影響を与えているという。
ワーケーション後の効果を促進する組織的要因を確認すると、特にチームワークの高い組織や私的コミュニケーションの多いチームほど、ワーケーション後の効果が高い傾向にある。
調査結果を受け、同社研究員の中俣良太氏は、「ワーケーション制度の整備は、人的資本経営の実現やウェルビーイングの向上を目指すための取り組みの一環であると同時に、企業にとってのネガティブな側面を抑制する点においても必要な取り組みだ」と述べている。
また、「ワーケーションする目的の内容に応じて容認可否を判断するなど、企業と従業員の双方にとって意味のあるワーケーション制度の導入が必要だろう」「個人だけでなく、チームにとっても有効な非日常体験のデザインが重要だ」と提言している。