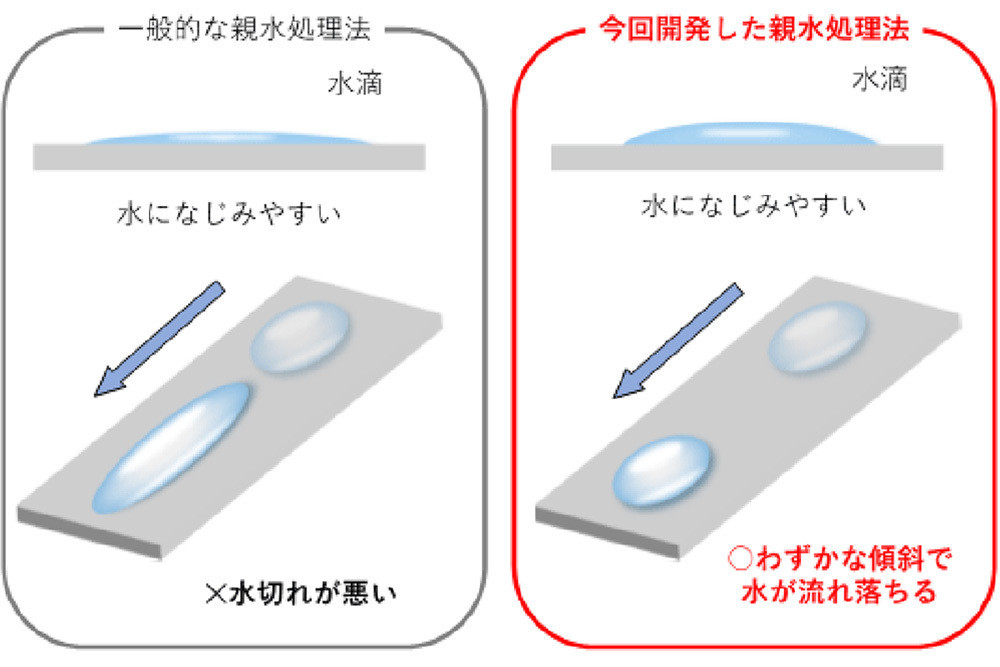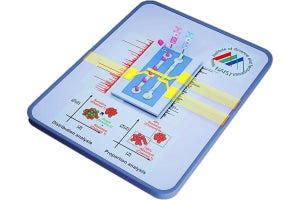東京理科大学(理科大)は8月31日、リンゴ果実に着生したカビにより産出されるカビ毒の1つ「パツリン」の毒性に耐えて生きることができる微生物を自然界から分離することに成功し、その微生物がAcremonium属のカビであることを明らかにしたと発表した。
同成果は、理科大 創域理工学部 生命科学科の古谷俊樹准教授、理科大大学院 創域理工学研究科 生命生物科学専攻の三田芽実大学院生(研究当時)、同・佐藤梨奈大学院生(研究当時)、同・柿沼美穂大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、国際学術雑誌「MicrobiologyOpen」に掲載された。
ある種のカビ(糸状菌)は、カビ毒と呼ばれる毒性物質を産生することが知られている。これらのカビは、カビ毒を利用して栄養豊富な植物に侵入したり、競争相手の微生物を攻撃したりすることで、環境中で有利に生存していると考えられている。
ヒトがこうしたカビ毒に汚染された農作物を食べてしまうと、健康に悪影響が及ぶため、代表的なカビ毒については食品中の最大基準値が設定されているという。
代表的なカビ毒の1つであるパツリンは、リンゴ果実に着生したPenicillium expansumというカビによって産生される。ジュースなどの加工品でも見られることがある同物質は、相手の細胞内で抗酸化物質のグルタチオンに結合し、その濃度の低下を引き起こすことで、有害な活性酸素種を蓄積しやすくさせるといい、この活性酸素種がDNAなどにダメージを与えて、細胞機能を損なわせる。
このような作用機序から、パツリンはヒトや動物だけでなく微生物にも毒性を示すため、多くの微生物はパツリン存在下で増殖することができない。Rhodosporidium属の酵母やGluconobacter属の細菌といったカビ以外の微生物では、パツリンをほかの化合物に分解することで毒性を低下させる種が報告されていたものの、カビに分類される微生物については、パツリンを分解できる株の存在や分解機構について未だ解明されていなかったとする。
そこで研究チームは今回、日本各地から510もの土壌サンプルを採取し、パツリンを含む液体培地に接種することで、その環境下で生育可能な微生物を選択したとのこと。その結果、16株の微生物が取得されたという。
次に、培養液内のパツリン含有量を高速液体クロマトグラフィ(HPLC)により測定。これにより、2株の微生物でパツリン含有が低下していることが分かったとする。その後この2株についてITS1領域のDNA配列をもとに系統解析を行ったところ、どちらもカビ(真菌類)であることが判明し、1株はAcremonium属真菌、もう1株はFusarium属真菌だと同定された。
そして研究チームは、パツリン含有量を著しく低下させた「Acremonium sp. TUS-MM1」株について、詳細な解析を実施した。同株の菌体をパツリンと反応させたところ、HPLC分析によりパツリンの減少と変換産物に相当するピークが検出され、この変換産物を核磁気共鳴(NMR)により分析したところ、パツリンよりも毒性が低いことが知られる「デソキシパツリン酸」であることが分かったとする。
また一方で、菌体が対外に放出する成分をパツリンと反応させた場合にも、パツリンの減少、およびデソキシパツリン酸とは別の変換産物に相当する複数のピークがHPLC分析により検出されたといい、この変換産物もパツリンより低い毒性を示したとのこと。また菌体外成分には分子量2万以下の熱に強い化合物が含まれており、この化合物がパツリン分解に関わっていることや、菌体外成分がデソキシパツリン酸も分解できることを明らかにした。
今回研究チームは、パツリンの毒性に耐えて生きることができるカビを、自然界から分離することに成功した。そして取得されたTUS-MM1株は、その菌体によってパツリンをデソキシパツリン酸に変換すると同時に、菌体が体外に放出する成分もパツリン分解活性を示すことから、これらが協調的に作用してパツリンを効率的に分解できることが明らかとなったとする。このことから研究チームは、TUS-MM1株やパツリン分解に関わる成分が、カビ毒の防除に応用できる可能性があるとしている。