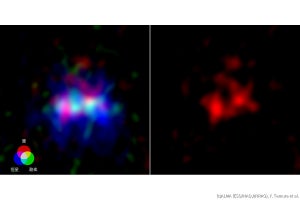アルマ望遠鏡は8月14日、67GHz~84GHzの周波数帯域での観測が可能な新型「バンド2」受信機を開発して、その初期量産機を試験的にアルマ望遠鏡の複数のアンテナに搭載し、同望遠鏡の建設当初からの計画である67GHz~116GHzの周波数帯域(2.6mm~4.5mmの波長域)での初観測を実施したことを発表した。
同成果は、欧州南天天文台(ESO)が主導し、国立天文台やチリ大学、複数のヨーロッパの研究機関や企業などの研究者や技術者も参加した国際共同研究開発チームによるもの。
大小2種類のアンテナ合計66台で構成されるアルマ望遠鏡は、ミリ波/サブミリ波領域を扱う電波望遠鏡だ。アンテナ1つ1つには非常に高感度な10帯域の受信機が搭載されており、各受信機はそれぞれ決まった周波数帯域を受け持つ。それらの受信機は全体で、35GHz~950GHz(0.3mm~8.6mm、バンド1~10に対応)の周波数帯域をカバーしている。
そうした中で今回は、新たに開発されたバンド2受信機により、これまでアルマ望遠鏡では観測できていなかった新しい周波数帯域である67GHz~84GHzでの観測が実現された。また同受信機は、現在運用中のバンド3受信機によってカバーされている84GHz~116GHzの周波数帯域も観測することが可能だとする。
アルマ望遠鏡の開発においては、量産初期に数台の装置を製造し、実装の上で検証し、性能などを確認したのちに本格量産を実施するといい、このことを初期量産と呼ぶ。今回のバンド2受信機の場合は、初期量産として計6台が製造された。その初期量産受信機の1台目は、2023年初頭に製造され、アルマ望遠鏡のアンテナに実際に搭載したのちに試験を実施し、成功したという。
-
アルマ望遠鏡バンド2受信機 冷却カートリッジ・アセンブリ。(c)NOVA/ESO(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)
-
アルマ望遠鏡バンド2受信機 常温カートリッジ・アセンブリ。(c)NOVA/ESO(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)
そして今回は、2台目および3台目の受信機が、さらに別の2つのアンテナに搭載され、干渉計としての観測、つまり複数のアンテナでの観測を行うことで、明るい天体からの複数の信号の相関から得られる干渉パターンを測定することが可能となった。
研究開発チームによると、この「ファーストフリンジ(最初の干渉縞)」は、バンド2受信機として初めて複数のアンテナからの信号を組み合わせることが可能になったことを示し、重要なマイルストーンを達成したことを意味するという。そして今後、さらに多くのアンテナへとバンド2受信機の搭載が進むにつれ、観測の詳細さと感度レベルが向上するとしている。
バンド2の周波数帯の観測で実現されるのが、星間空間に存在する、星形成の材料となる塵と分子ガスの混合物である“冷たい星間物質”の測定だ。またアルマ望遠鏡では、原始惑星系円盤から遠方銀河までを対象として、塵や分子の性質を、これまでは決して達成できなかった詳細なレベルで研究できるようになるとする。
それらに加え、バンド2受信機を用いることにより、地球近傍の銀河における複雑な有機分子の観測も可能となり、生命誕生の条件がどのようにして作られるのかという謎に迫る鍵を得られるようになると推測される。そのうえバンド2の周波数帯は、原始惑星系円盤の中心星から遠く離れた一酸化炭素の「スノーライン」(約-205℃以下となり、一酸化炭素が固体となる境界線)を調べることもでき、惑星がどのようにして形成されるのかの理解を深めるのにも役立つとのことだ。
今回の初期量産は、ESO主導のもと、オランダの天文学研究組織「NOVA」、スウェーデンのチャルマース工科大学オンサラ天文台の先端受信機開発グループ「GARD」、イタリア国立天体物理学研究所「INAF」からなるコンソーシアムが冷却カートリッジ・アセンブリ、常温カートリッジ・アセンブリの製造評価を、国立天文台がレンズをはじめとする光学系部品の製造評価を担当することで、共同開発された。
なお研究開発チームは現在、初期量産受信機における性能の最適化に取り組もうとしており、その後に、66台すべてのアンテナへの搭載に向けて受信機の本格量産を行う。バンド2受信機の搭載と、現システムの補完的に2030年代に向けて計画されているアルマ望遠鏡のアップグレードとを合わせると、一度に観測できる周波数帯域を現在のアルマ受信機の4倍以上へと拡大できるようになるため、観測スピードを劇的に上げることができるとしている。