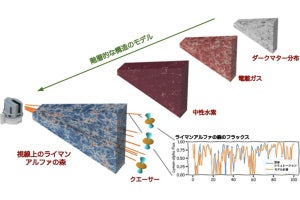国立天文台 ハワイ観測所は5月31日(現地時間)、すばる望遠鏡と、同じくハワイ・マウナケア山頂にあるケック望遠鏡を用いて110億年前の遠方宇宙にある巨大銀河を観測し、巨大銀河が星の輪廻転生を通して成長する様子を捉えることに成功したと発表した。
-
星屑を再利用しながら成長し続ける巨大銀河のイメージ。超新星爆発やブラックホールの活動によって銀河の外へ放出された星の残骸が再び銀河内部へ送り返されることで、爆発的な星形成が絶えず維持され、より大きな銀河へ成長することを手助けする。背景は、マウナケア山頂域に並ぶ、すばる望遠鏡とケック望遠鏡。(c)精華大学/NAOJ(出所:すばる望遠鏡Webサイト)
同成果は、中国・清華大学のツァイ・ジェン准教授、早稲田大学(早大)の嶋川里澄准教授に加え、独・マックス・プランク宇宙物理学研究所の研究者らが参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。
星を作るガスや塵は銀河の中にも多数存在するが、それはごく一部であり、その大半は銀河間に存在する。銀河間ガスは、網目状の宇宙の大規模構造に沿って淡く分布しており、銀河に落ちていくことで新しい星を形成するための材料となる。星が超新星爆発を起こすと、その莫大なエネルギーにより、ガスは銀河の強い重力を振り切って外に排出されることがある。しかし、銀河外にガスが放出され続ければ、銀河で星が誕生できなくなってしまう。つまり、星が誕生し続けるためには、銀河に降り注ぐ何らかのガスの供給が絶えず必要ということになる。
太古の宇宙においてはこれまで、成長途中の銀河が数多く発見されてきたが、銀河の持続成長の原動力が宇宙誕生時の原始的なガスの供給によるものなのか、それとも超新星爆発の残骸を多く再利用しているのかは、明らかではなかったという。そこで研究チームは今回、110億年前の宇宙にある巨大銀河を観測したとする。
ビッグバンからおよそ38万年が経過して宇宙の温度が十分下がった時、1個の陽子が1個の電子を獲得し、水素が誕生した。そのため、宇宙誕生時の原始的なガスのほとんどは水素で構成され、わずかにヘリウムが含まれている。一方、超新星爆発の結果として再利用されるガスは、星の核融合によって生成された鉄までの重い元素なども含まれる。
今回の研究では、すばる望遠鏡とケック望遠鏡の観測データが解析された(すばる望遠鏡では、多天体近赤外撮像分光装置「MOIRCS(モアックス)」が活用された)。その結果、この銀河周辺の30万光年にも及ぶ広い範囲で、水素、ヘリウム、炭素が検出され、さらにこれらの元素の比率は、太陽で見られるものと同等であることが確認されたという。
110億年前の太古の銀河を囲むガスと、およそ46億年前に誕生した太陽では、超新星爆発によって撒き散らされた重元素の量が大きく異なるはずだが、これらのまったく時代の異なる両者において元素比率が同等という事実について、研究チームでは驚くべきことだとしている。
さらにこの銀河を取り巻くガスの動きをシミュレーションと比較したところ、1年間に太陽700個分に相当するガスが銀河に還流していることが明らかにされた。これは、この銀河で観測された星形成の速度(1年間に太陽80個分ほどの星が生まれる)をはるかに上回るもので、ガスの再利用だけで銀河の成長を促すことができることを示すとする。
なお、ガスを構成する水素のような通常物質は、銀河内の星が生まれる分子雲などの星間ガスのイメージが強いが、実は大半は銀河間にあるという。そして、銀河間ガスは量は多いがとても希薄であるため、直接観測することが極めて困難だという。そうした中で今回の観測では、ガス中の重元素を特定しただけでなく、運動状態をも捉えることにも成功したことから、早大の嶋川准教授は、「銀河の形成理解に向けて大きく前進したといえるでしょう」とのコメントを残している。