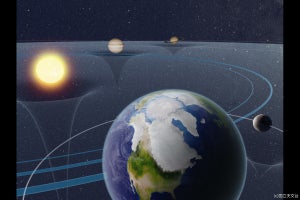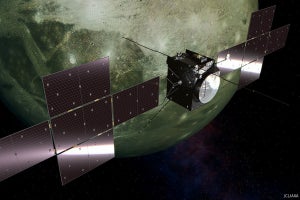神戸大学は5月19日、最新の木星探査観測などの知見とデータ科学的解析を基に、木星表面で広く観測されてきた気象の数年変動が深部の磁気的な波動に起因する可能性があることを示したことを発表した。
同成果は、神戸大 大学院 システム情報学研究科の堀久美子助教を中心とする、英・リーズ大学のクリス・A・ジョーンズ教授、レスター大学のリー・N・フレッチャー教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。
木星表面の鮮やかな縞模様は、その色や明るさが、時とともに変化することが知られている。時には急激な嵐が起こり、それらが木星表面全体に広がっていくような現象「global upheavals(全球蜂起)」も観測されている。しかし、このような変化が規則的なものなのか、もしくは、突発的なものなのかは、長らく不明だったという。
そうした中、近年、数十年にわたる木星赤外線画像のデータセットが系統的に解析され、南緯41度から北緯33度までの広範囲で、周期4~9年の規則的変動が起こっていたことが判明。これらは、木星での一日の長さ(約10時間)に比べて長いことから、木星の「気候変動」と呼ばれることもあるという。
しかし、その特徴が観測から明らかになってくる一方で、成因については諸説が入り乱れる状況となっていたという。その多くが、地球の気象学における知見を基にした説であり、広緯度にわたる数年周期性を定量的に説明できるものは皆無であったことから、研究チームは今回、観測的な特徴を定量的に説明する説の構築に挑むことにしたとする。
研究チームが注目したのは、木星が巨大ガス惑星であり、地球のように「地面」が存在しないという点。木星表面はその惑星深部からシームレスにつながっているため、木星大気で観測される現象も、木星深部の現象に起因する可能性があるとする。実際、過去の理論・数値シミュレーション研究により、深部の磁場形成領域(ダイナモ)では、数年以上の周期で磁気的な波(ねじれ振動)が励起されうること、その振動は木星表面近くの熱流を広い緯度帯で変動させうること、などが示唆されていたという。そこで今回の研究では、その理論を根拠として、木星赤外線観測で見つかった特徴をどの程度説明できるかを調べることにしたとする。
具体的には、現在運用中のNASAの木星探査機「ジュノー」による磁場観測結果、ハッブル宇宙望遠鏡による風観測結果、そして深部密度の理論モデルから、各緯度におけるねじれ振動の周期が理論的に算出された。その算出値は3~8年であり、赤外線観測で見つかった周期性を、誤差の範囲内で定量的に説明できることが確かめられたという。
-
赤外画像で捉えられた木星大気の長期変動。(a)2011年12月撮像、(b)2001年5月撮像。青い点線は北赤道縞(北緯7~21度)を示す。明るさ(赤外放射の強さ)が変化したことがわかる。補正前の画像であることに注意 (画像はフレッチャー教授ら研究グループの論文より転載されたもの) (出所:神戸大Webサイト)
また、この理論値を基に、近年開発されたデータ科学的解析法の1つである「動的モード分解法」を用いることで、赤外線画像の時空間データセットから、深部ねじれ振動が期待される周波数域に、微小なシグナルを抽出することにも成功したとするほか、そうして抽出されたシグナルは、期待された波長および伝播速度と矛盾ないものだったともしており、これらの結果から深部ねじれ振動の基本的特性(周期・波長・伝播速度)を大気の観測データに確認することができたと研究チームでは説明している。
-
木星深部のねじれ振動。(a)木星を貫く磁場。青線と赤線は磁力線を表し、その色で磁場の強さが表されている。NASAの探査機ジュノーの磁場観測を基に作成されたもの。(b・c)ねじれ振動の概念図。ねじれ振動は自転軸を中心とした円柱状の振動で(b)、自転軸と垂直な方向に伝播する(c)。東西向きの流れのゆらぎ(黒線)によって磁力線(赤線)がゆがみ、そのゆがみが磁力線のバネ効果によって引き戻されて、逆向きに流れのゆらぎが生じる。これが繰り返されることで、振動が起こり、その振動が磁力線に沿って波動として伝播していく (画像はNature Astronomy掲載論文が一部改変されたもの) (出所:神戸大Webサイト)
-
木星赤外線画像データセットから抽出された深部ねじれ振動のシグナル。赤外線画像の明るさが東西方向に平均化され、動的モード分解法を用いて抽出された。色と等高線は、明るさの平均値からのずれを表す。横軸は西暦、縦軸は自転軸からの距離。黒の点線は、ねじれ振動の伝わる速さを示す。ねじれ振動の速さで、赤外線画像における時空間変動パターンを説明できることがわかる (画像はNature Astronomy掲載論文が一部改変されたもの) (出所:神戸大Webサイト)
従来の描像は、岩石惑星である地球での知見を基として他惑星に拡張したもので、大気現象と深部現象との相互作用はほぼ議論されておらず、今回の研究で提唱された説は、そうした従来の惑星大気研究における描像とは異なるものであると研究チームでは述べており、この成果は、木星に代表される巨大ガス惑星を理解するためには、両方の議論、特にその統合的な理解が重要であることを示唆するものであるとしているほか、地球に代表される岩石惑星とは本質的に異なるものであり、今回の研究を進めることは、地球環境の特徴を改めて浮き彫りにし、再認識することにもつながるともしている。
加えて、地球以外の天体において深部の磁気的な振動・波の存在が示唆されたことは、磁場の形成メカニズムを解明するために極めて重要だとも指摘している。磁場形成問題の難点の1つは、磁場が形成されている「現場」を直接調べることができず、理論を制約するための実測的な情報が欠落している点だとしているが、ねじれ振動は、その深部領域の物理的状態を強く反映するため、これを逆手にとることで、観測された振動の特性から磁場形成領域内部を「スキャン」することも可能になるとのことで、このような情報は、理論モデルの取捨選択に役立つほか、理論的な問題点を明確にもする可能性があるとしており、今後、今回の研究成果を活用していくことで、天体磁場形成問題の解決のための新たな可能性が開かれ、大きく展開していくことが期待されるという。