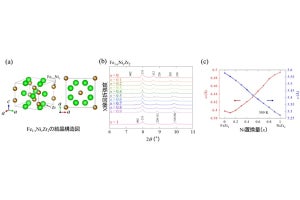千葉大学は5月9日、アレルギーハイリスク出生コホート研究において、妊婦および児(臍帯血・1歳)の血液と母乳中のカロテノイド濃度を測定し、カロテノイド濃度の低さが、1歳時のアトピー性皮膚炎(AD)の発症と関連することを明らかにしたと発表した。
同成果は、千葉大大学院 医学研究院の井上祐三朗特任准教授、同・大学 予防医学センターの下条直樹特任教授、カゴメの共同研究チームによるもの。詳細は、欧州アレルギー臨床免疫学会が刊行するアレルギーおよび免疫学の全般を扱う学術誌「Allergy」に掲載された。
乳児期のADは、皮膚についた異物に対してアレルギーをおこす「経皮感作」のリスクとなり、その後のアレルギー性疾患の発症と関連することが明らかにされている。これまで、乳児期の経皮感作を予防することを目的に、スキンケアを始めとしたさまざまな介入研究が行われてきた。しかし、現時点ではその効果は限定的だという。今後、乳児期ADの発症メカニズムを解明することは、将来のアレルギー疾患の発症を予防するためにも、非常に重要であると考えられている。
アレルギーにおいては、ADを持つ子どもが健康な子どもと比べて、血清中のカロテノイド濃度が著しく低いことが知られている。カロテノイドは、細菌や菌類、植物、動物など多くの生物が生合成する黄色または赤色の天然色素で、トマトやニンジンなどの食材に多く含まれることで知られる。またカロテノイドには、全般に高い抗酸化力があることが知られている。β-カロテンなどの一部のカロテノイドはプロビタミンA活性も有し、健康に有益な効果があることがわかっているが、ヒトなどの哺乳類は、カロテノイドを生合成できないため、野菜や果物などから摂取する必要がある。
一方で、食物摂取頻度調査票を用いた、妊娠中の母親の野菜摂取量と子どもの湿疹との関連を評価した先行研究では、一貫性のない結果が示されていた。研究チームはその要因として、これらの研究では、母および子どもの血液および母乳中の個々のカロテノイド濃度を測定していないため、母および子どもの野菜摂取が、子どものADの予防につながるかは明らかではなかったとする。
そこで今回の研究では、アレルギーの家族歴を持つ(アレルギーハイリスク)267名の新生児とその母親が参加した、出生コホート研究(CHIBA study)において、妊婦(36週)および児(臍帯血・1歳)の血液と母乳(初乳・1か月・6か月)中の、個々のカロテノイド・レチノール・α-トコフェロールの濃度を測定し、医師診断により1歳時のADとの関連を検討したという。
そして分析の結果、血液と母乳中の複数種類のカロテノイド濃度と総カロテノイド濃度の低さが、1歳時のAD発症と関連していることが判明したとする。
カロテノイド以外の因子の影響を考慮するために、性別や出生体重などの背景因子や、皮膚黄色ブドウ球菌保菌などの環境因子を含めて、多変量解析が行われた。その結果、生後6か月までに湿疹があること、母体血ルテイン濃度の低さ、1歳時の子どもの血中リコピン濃度の低さが、1歳時のAD発症と関連していることがわかった。また多変量解析では、母乳中のカロテノイド濃度と1歳時のAD発症に関連は認められなかったという。
研究チームは今回の研究の特色として、母と子ども双方のカロテノイド濃度が測定されている点が挙げられるとする。妊娠中の母の血中カロテノイド濃度と、出生時の子どもの血(臍帯血)中カロテノイド濃度には明らかな相関があり、妊娠中の母の野菜・果物からのカロテノイド摂取が、子どもに影響していることが示唆されるとしている。
また母体血中の、ルテイン・ゼアキサンチン・α-カロテン・β-カロテン・リコピンの濃度には強い相関が見られ、これらのカロテノイドを含む食品(野菜や果物など)に対する嗜好性に偏りがあることが予想されたという。
今回の研究により、妊娠中のカロテノイド摂取量が少ない母親の子どもは、乳児期ADの発症リスクが高く、アレルギー予防のための早期介入の理想的なターゲットであることが明らかにされた。研究チームは今後、妊娠中/授乳中の母や離乳後の乳児に、野菜・果物からのカロテノイドを補給することが、乳児期のAD発症を抑制できるかどうかを検討するために、介入試験を含めたさらなる研究が必要であると考えているとしている。