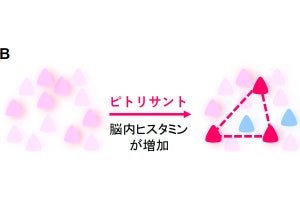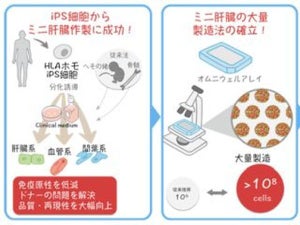東京大学(東大)とリコーは3月23日、転写因子を用いてヒトiPS細胞を生体外で人工的に作製した神経細胞「ヒトiPSC由来神経細胞」が機能的に成熟し、樹状突起スパインの形成とシナプス可塑性を担うメカニズムの発現を迅速に達成することを明らかにしたと発表した。
同成果は、東大大学院農学生命科学研究科の關野祐子 特任教授とリコーのリコーフューチャーズBU バイオメディカル事業センター バイオメディカル研究開発室の林和花リーダーらの研究グループによるもの。詳細は、学術雑誌「iScience」に掲載された。
ヒトiPSC由来神経細胞は、認知症や自閉症といった中枢神経系疾患などの研究に役立つことが期待されており、中でも神経ネットワークの情報伝達を司るシナプスの構造と機能を再現することは重要であると考えられているものの、ヒトiPSC由来神経細胞を用いたシナプス形成には時間がかかり、特に興奮性シナプス後部の棘構造(スパイン)形成が困難とされていた。
その一方、さまざまな種類の神経細胞を効率よく作製する分化誘導技術の開発が近年、積極的に進められてきており、今回の研究では、転写因子を使って分化誘導されたヒトiPSC由来神経細胞の、成熟過程における経時的な特徴を明らかにし、スパイン形成を評価することにしたという。
具体的には、分化誘導技術を用いて作製したヒトiPSC由来神経細胞を最大3か月間培養し、経時的にデータの収集を実施。トランスクリプトーム解析の結果、これらの細胞は培養10日で神経細胞に分化し、その後2~3か月の成熟の過程を経てヒトの大脳皮質神経細胞の遺伝子発現パターンに近づくことが判明したとする。
また、スパインが形成されるまでの発現パターンの変化は、ヒトの脳発達データ(BrainSpan)と相関し、成熟に伴うシナプス関連因子の発現上昇と脳型ドレブリンアイソフォームへの変換などが確認されたほか、高密度多点電極アレイ(HD-MEA)を用いた電気生理学的評価から、発火頻度の上昇とシナプス活動を介した神経伝達ネットワークの形成が確認されたとする。
さらに、共焦点定量イメージサイトメーター(CQ1)を用いた免疫細胞染色にて細胞形態および神経特異的タンパク質発現の評価を行ったところ、神経細胞の樹状突起の成長に伴い、ドレブリンの局在変化が起こり、2~3か月という期間で樹状突起上にスパインが無数に形成されることも確認したほか、スパインの機能性を示すために、グルタミン酸刺激への応答性が評価されたところ、スパインに集積しているドレブリンがグルタミン酸刺激により樹状突起内に移動する現象(ドレブリンエクソダス)を観察することにも成功したとする。
NMDA型グルタミン酸受容体の活動を介するドレブリンエクソダスは、げっ歯類の初代培養神経細胞により明らかにされてきた樹状突起スパインの形態的可塑性メカニズムであり、研究チームでは、この現象の再現に成功したことにより、シナプスが分子機能レベルで成熟していることが示されたと説明する。
なお、研究チームでは、ヒト神経細胞でドレブリンエクソダスが観察されたことの意義は大きく、ヒトの神経シナプスの成熟過程の研究や、記憶学習メカニズムの研究が促進され、中枢神経系疾患の病態解明や認知機能障害などを標的とした治療薬開発への活用が期待できるとしているほか、転写因子誘導されたヒトiPSC由来神経細胞でスパイン形成までの期間が従来手法比で3分の1に短縮されたことで、実験コストの削減も期待できるようになるとしている。