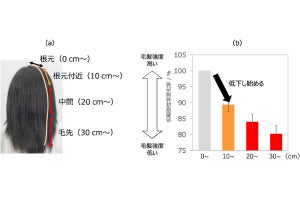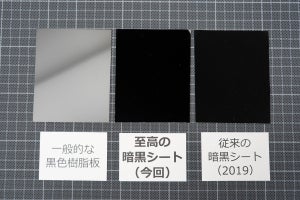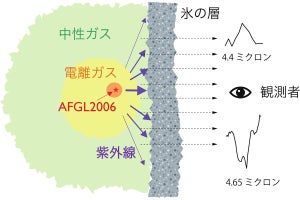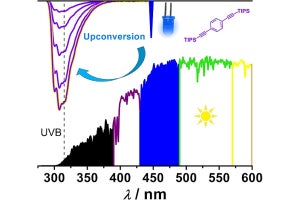名古屋市立大学(名市大)は3月3日、紫外線殺菌技術において従来の定説を覆す効果を発見したことを発表した。
同成果は、名市大大学院 芸術工学研究科の松本貴裕教授、同・大学 医学研究科 細菌学分野の立野一郎講師、同・長谷川忠男教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
さまざまな病原性ウイルスやバクテリアの殺菌する紫外線殺菌の基本原理として、照射線量(照射強度×照射時間)が同じであれば、殺菌量は同じであるとこれまで考えられてきた。要するに、強い強度で短時間照射した場合と、弱い強度で長時間照射した場合の殺菌率は同じになるというものだ。
しかし近年、カナダやイスラエルなどの研究機関によって、その定説を覆す紫外線殺菌結果が相次いで報告されたという。しかし、その殺菌メカニズムは謎に包まれていたとする。そこで研究チームは今回、大腸菌を用いた紫外線殺菌実験を行い、その定説が正しいのかを確かめることにしたという。
そして照射線量が一定の条件下で、紫外線照射強度を大きく変えて大腸菌の殺菌率を精密に評価したところ、紫外線強度が弱くて長時間殺菌した場合の方が、紫外線強度が強くて短時間殺菌した場合よりも、殺菌効率が大きいことが確認されたといい、これまでの定説が成立しないことが実証されたとしている。
具体的には、紫外線強度10mW/cm2で1秒間照射した場合、紫外線照射によって大腸菌数が6000個から550個に減少し、90%の殺菌率だったのに対し、0.1mW/cm2で100秒間照射した場合、同数の大腸菌が60個にまで減少し、99%の殺菌率をもたらすという結果が示されたという。
-
照射線量を10mJ/cm2(照射波長は265nm)で一定にした場合の、大腸菌殺菌効果の紫外線強度依存性。(a)強度10mW/cm2で1秒の場合の大腸菌数(90%の殺菌率)。(b)線強度0.1mW/cm2で100秒の場合の大腸菌数(99%の殺菌率)。(c)紫外線殺菌する前の大腸菌数は約6000個に対する、(a)と(b)のプレートで計測された大腸菌数。(a)は約550個、(b)は60個(出所:名市大プレスリリースPDF)
次に、数学の最先端手法である確率微分方程式を用いて、実験結果の解析が行われた。すると、従来考えられていた紫外線殺菌のメカニズム(紫外線によるウイルス・細菌のDNA破壊)に加えて、新たな紫外線殺菌メカニズムの存在が判明した。
この新たな紫外線殺菌メカニズムは、現在のところ、紫外線照射によりウイルスや細菌内で活性酸素が生成され、この活性酸素がウイルスや細菌のDNAや脂質層を破壊して殺菌するものと考えられるという。なお、この活性酸素は不安定で、活性酸素同士が出会うとすぐに活性の無い酸素に変化してしまうとする。このような理由により、強い強度の紫外線をウイルスや細菌に照射すると、大量に活性酸素が生成されるが、活性酸素同士が結合して活性が無くなるため、紫外線の殺菌効果が薄れるとしている。
今までの定説では、紫外線照射によりDNAやRNAの構造が破壊されるために、ウイルスや細菌の殺菌が行われると考えられてきた。しかし今回の研究により、紫外線殺菌にはその効果として、「DNAやRNAの破壊」と「活性酸素によるウイルスや細菌の死滅効果」の2つが共存していることが明らかにされた。そして2つの効果が共存する場合、紫外線強度が強い場合と弱い場合を比較すると、(2)の効果が薄れるため、殺菌効率が低くなるとする。
-
(左)紫外線殺菌によるウイルス・細菌のDNA損傷を示すモデル。紫外線照射により、2重螺旋中の水素結合が壊れ、相隣接したピリミジン塩基間にピリミジンダイマーと呼ばれる新たな結合が形成されDNAの損傷を起こす。(右)紫外線照射により、ウイルスや細菌内で活性酸素が生成され、この活性酸素がウイルスや細菌のDNAおよび脂質層を破壊して殺菌することを示すモデル。紫外線殺菌には(1)DNAおよびRNAの破壊、および(2)活性酸素によるウイルスや細菌の死滅、の2つのメカニズムが存在する(出所:名市大プレスリリースPDF)
研究チームによると、従来の定説を覆すこの新たな紫外線殺菌の基本原理は、大腸菌に限らず、種々の細菌で同様に成立することが確かめられており、普遍的に成り立つ法則であると考えられるとした。
同じ照射線量でも低強度の紫外線を長時間照射することで大きな殺菌効果を引き出せるという今回の知見は、紫外線殺菌時に人体への紫外線照射線量を低減できるため(1日に人体に浴びて良い紫外線照射線量は法律で規定されている)、今後の紫外線を用いた居住空間および病室の紫外線殺菌技術、あるいは装置開発に大きく貢献できるものと考えているとしている。