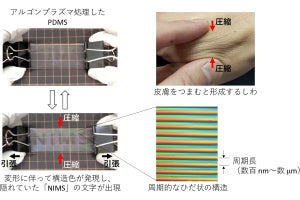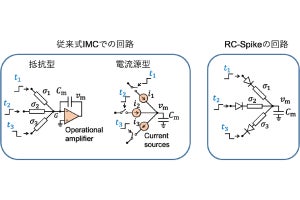東京理科大学(理科大)は11月30日、トポロジーとAIと自由エネルギーを融合した理論を設計し、顕微鏡画像データの自動的な解釈と、デバイスの逆設計に成功したことを発表した。
同成果は、理科大の國井創大郎大学院生(研究当時)、同・増澤賢大学院生、同・Alexandre Lira Foggiatto研究員、同・三俣千春客員教授、同・小嗣真人教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
ナノスケールの磁性体はデバイスのナノ構造と複雑な相互作用を示すため、微細な磁気の変化がどのようにデバイスの機能につながるのか、適切に解釈することは困難だという。これまでは人間が目視で解析を行ってきたため、顕微鏡などの画像データの解釈は定性的で属人性が高いことが、機能設計における深刻な課題だった。そのため基礎的なメカニズムの理解が不十分となり、応用上ではデバイス機能の向上を困難にさせていたとする。
そこで研究チームは今回、トポロジーと情報科学と自由エネルギーを融合させて、「拡張型ランダウ自由エネルギーモデル」を設計し、画像データの自動的な解釈を試みることにしたという。別の言い方をすれば、複雑な磁化反転現象の裏側にある物理的な原因と、それが働いている場所を特定可能な機能解析モデルの創成に取り組むことにしたとしている。
古典的には、磁化と磁場から磁化反転現象を説明するランダウ自由エネルギーモデルが知られていた。しかし、ランダウ自由エネルギーモデルは単結晶にしか適用できないことから、ナノ構造を持つ実材料の磁化反転現象を説明することは不可能だったという。そこで今回の研究では、このランダウ自由エネルギーモデルにトポロジーとデータサイエンスを組み合わせることで、実材料を解析可能なモデルとして構築することにしたとする。
具体的には、まずトポロジーの概念である「パーシステントホモロジー」が用いられ、複雑な磁区構造が特徴量として抽出された。次に、解釈性の高い機械学習が用いられ、情報空間上に新たなエネルギーランドスケープが描画され、拡張型ランダウ自由エネルギーモデルが作成された。
同モデルは、物理に根ざした特徴量を用いて磁化反転過程を解析するのが特徴だ。単純な変数変換と微分によって、磁区構造変化とエネルギー障壁の関係性を構築することができる。これによって、ミクロな磁区構造とマクロな磁化反転現象の双方向接続を、階層を超えて行うことができ、さらには起源となる物理的相互作用を定量的に解析できることを意味しているという。
同モデルを用いて、ナノ磁性体の情報記録の過程について解析を行った結果、反磁界効果が支配していることが明らかになったとする。また、磁区構造変化を妨げるエネルギー障壁の空間的な集中を可視化することにも成功したという。これは、これまで目視で解析困難だったメカニズムの理解や、顕微鏡画像のわずかな変化を可視化できていることを意味するという。またこれにより、同モデルを活用することで、肉眼では判断できずに捨てられていた顕微鏡データが「宝の山」になる可能性があるとする。
さらに、同モデルに基づき、エネルギー消費の少ないナノ構造の提案にも成功したという。これは、デバイスの逆設計にも応用可能であることを強く示唆する結果とした。同モデルは、複雑なメカニズムで駆動するさまざまな材料に利用でき、量子情報技術や電気自動車のモーターや自律分散システムなど、幅広いものづくりに貢献するとした。