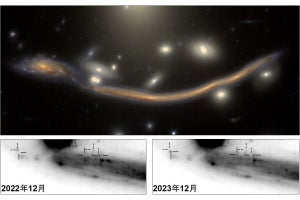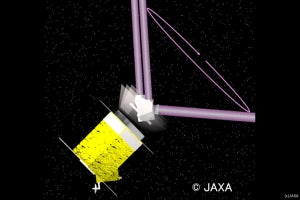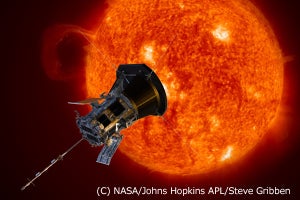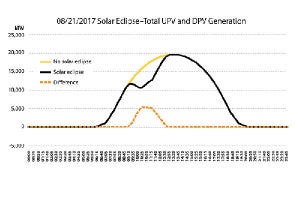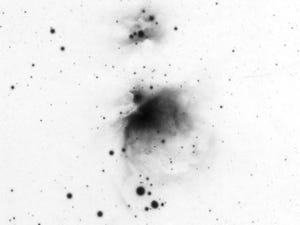名古屋大学(名大)と筑波大学は9月15日、西暦4~7世紀を対象に、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の皆既日食記録を探索・検討し、それらを用いて当時の地球の自転速度を計算し、4~7世紀の自転速度変化の拘束条件を増加させることに成功したと発表した。
同成果は、名大 高等研究院の早川尚志特任助教(名大 宇宙地球環境研究所兼任)、筑波大 図書館情報メディア系の村田光司助教らの研究チームによるもの。詳細は、太平洋天文学会が刊行する天文学と天体物理学を扱う学術誌「Publications of the Astronomical Society of the Pacific」に掲載された。
人類が数多くの記録を残してきた天文現象の1つに、皆既日食がある。皆既日食や、月が惑星や恒星を隠す掩蔽(えんぺい)などの天文現象は、地球の自転速度に応じて、見える場所が変化することから、歴史的な天文記録をもとにすることで、太陽と地球の連関、太陽活動の変動、過去の編年などに加え、地球の自転速度も復元することが可能となるという。
地球の自転速度は、およそ46億年前に誕生した頃は5~6時間だったとされ、その後、海洋ができて以降は月と太陽による潮汐摩擦のせいで、徐々に遅くなっていることが知られている。
現在では、1日の長さが100年あたりで約0.002秒のペースで遅くなっていることがわかっているが、この変化の割合はどの時代もずっと一定だったわけではない。そのため、世界各地に残されている、さまざまな天文現象記録などを用いて、研究者たちは自転速度の変化についての研究を行ってきたという。
しかし当然ながら、歴史的記録は時代が古くなるほど、観測地の偏り、分量の減少、信憑性の低下などが生じてしまう。つまり、過去の地球の自転速度を導き出すには、時代を遡れば遡るほど不定性が増大するという課題を抱えていたという。
また、地球の自転速度の変化は、ΔT(地球時から世界時を引いた差)という数値を用いて表現されるが、その精度を上げるために欠かせないのが、過去の皆既日食などの記録だという。
そうした中で西暦4~7世紀に関しては、当時、高度な文明を有していた東地中海沿岸の東ローマ帝国において、皆既日食の記録が取られていたことがわかっている。しかしそれらの記録は、幾重もの引用や翻訳などを経て伝わっており、信頼性の評価が難しく、これまで地球の自転速度変化の研究にはあまり用いられてこなかったという。
それでも研究チームは今回、西暦4~7世紀を対象に、東ローマ帝国の皆既日食記録を探索・検討し、それらを用いて地球自転速度を計算することにしたという。そして新たな情報が得られ、4~7世紀の自転速度変化の拘束条件を増加させることに成功したとする。