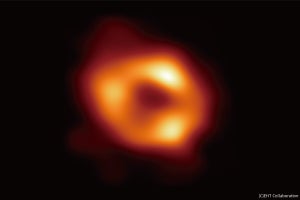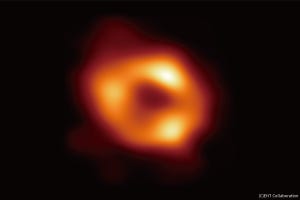総合研究大学院大学(総研大)と国立天文台(NAOJ)は5月27日、約100億年以上前に星形成活動を終えた銀河のサンプルを多波長で解析することによって、これらの銀河の中心には一般的に超大質量ブラックホールが存在することを明らかにしたと発表した。
同成果は、総研大の伊藤慧大学院生(研究当時)を中心とする研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。
現在の宇宙には、実にさまざまな銀河が存在しており、そうした銀河の一生の中でどのように星が生まれてきたのかを理解することは、銀河の進化を理解する上で重要とされている。
一般的には銀河には常に周囲からガスが降り積もってきていると考えられており、それらが時間をかけてゆっくりと冷えて固まっていき、やがて星の誕生に至る。こうした過程は「星形成活動」と呼ばれている。
銀河の星形成活動が止まってしまうことは、銀河の成長が止まることを意味する。銀河では星が生まれているのが自然な姿だが、長い間星が生まれていない「楕円銀河」のような不思議な銀河も存在していることも知られており、そうした楕円銀河が成長を止めてしまった理由は銀河研究において解明されていない謎の1つとなっている。
この謎を解き明かす鍵の1つは遠方宇宙にあるという。星が生まれなくなってしまった頃の銀河の性質を詳細に調べれば、その理由のヒントが見つかる可能性があるからだ。
宇宙初期、とりわけ100億年以上前の宇宙では、ほとんどの銀河で活発に星が生まれていたと考えられている。しかし、すばる望遠鏡などによる近年の可視光と赤外線の観測から、少ないながらも、すでに星形成を終えた銀河が存在していることもわかってきた。これらは現在の楕円銀河の祖先であることが期待されるという。
この特徴的な銀河種族の星形成活動がどうやって終わったのか、宇宙の歴史の中での平均的な描像を捉えるには、多くの銀河のサンプルが必要だったとする。そこで研究チームは今回、多波長サーベイCOSMOS(Cosmic Evolution Survey)の探査領域において、星形成活動を終えた95億年以上前の銀河、約5000個をさまざまな波長の光でくまなく調べることにしたという。