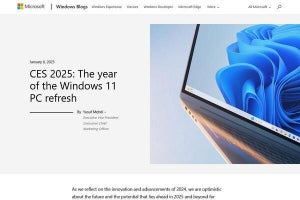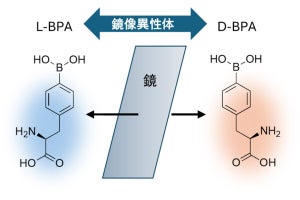太陽系最遠の惑星である海王星の気温が奇妙な変動を見せていることが分かった、と英レスター大学を中心とする、日本を含む国際研究グループが発表した。南半球が夏に入ってから著しく低下したのに続き、南極域で急上昇したという。原因は不明で、神秘的な青い巨大惑星の謎が深まる展開となった。
海王星は太陽から地球までの距離の30倍の位置にあり、直径は地球のほぼ4倍。主に水やアンモニア、メタンの氷でできた巨大氷惑星で、大気は水素やヘリウムからなる。公転周期は約165年と長く、人類が1846年に発見してから、まだ海王星の“1年相当”が経ったばかりだ。自転軸が公転面に対して約28度傾いており、地球と同様に季節が移ろう。1989年には米探査機「ボイジャー2号」が接近し、鮮やかな青い姿を撮影した。
研究グループは、海王星の約20年の観測で得られた全ての中間赤外線画像を解析した。その結果、成層圏の平均温度が、海王星の南半球の初夏である2003年から、18年までに約8度も低下したことが判明した。
レスター大学の資料によると、研究グループを率いた同大のマイケル・ローマン博士研究員は「この変化は予想外だ。南半球が初夏の時期に観測しており、気温はゆっくり上昇し、低下はしないものと見込んでいた」と説明。NASAの研究者は「われわれが捉えた期間は海王星の一つの季節の半分にも満たない。大規模で急速な変化は誰も予想できなかった」という。
ところが、その後の2018~20年には、南極域の成層圏の温度が逆に11度も上昇し、それまでの低下の傾向を逆転させたことも分かった。ローマン氏は「気温の変動は、大気の化学的な性質の季節変化のせいかもしれない。気象の不規則な変動や、太陽の11年の活動周期が影響している可能性もある」と指摘する。
研究グループは、気温や雲について追跡観測が必要だとしている。昨年12月に打ち上げ、本格観測に向け準備が進む史上最大の「ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡」が今年後半、天王星とあわせて観測する計画だという。
研究グループは英レスター大学、米航空宇宙局(NASA)、米サウスウエスト研究所、東北大学、国立天文台などで構成。成果は惑星科学誌「プラネタリー・サイエンス・ジャーナル」に11日付で掲載された。2020年の南極域の観測には、日本のすばる望遠鏡(米ハワイ州)が貢献している。
|
関連記事 |