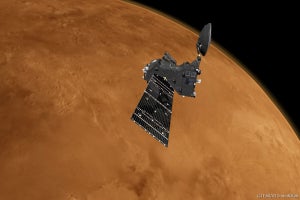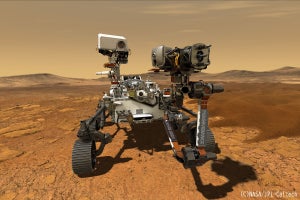東京大学(東大)は2月4日、火星のコアを構成している可能性が高い「鉄-硫黄-水素合金」の高圧高温下での液体の存在状態を明らかにし、火星における磁場の形成と消失のメカニズムを解明したと発表した。
同成果は、東大大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻の横尾舜平大学院生、同・廣瀬敬教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
火星のコアについては、これまで火星隕石の研究から、大量の硫黄を含んでいることが推測されてきたが、近年、米国航空宇宙局(NASA)が火星へと送り込んだ火星内部探査機「インサイト」による研究から、火星には液体のコアが存在するものの、その密度は従来の予測よりも小さく、硫黄以外の軽元素もコアに含まれている可能性が指摘されるようになった。
しかし、実験の難しさから火星コアを模擬した鉄-硫黄-水素合金の状態図を調べる実験はほとんど行われてこなかったという。
そこで研究チームは今回、数十万気圧という地球や火星内部に相当するような高い圧力下において、鉄を溶かすほどの高温を発生させることも可能なレーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル(LH-DAC)を用いた超高圧高温発生技術、SPring-8のX線回折による大気圧下では測定できない鉄中における水素濃度の高圧下での測定、集束イオンビームによる微細加工を用いた、実験後に回収された試料の構造の詳細な観察などを試みたところ、融解実験後に、大気圧環境下に回収された試料断面観察から、火星コア中心部に相当する40万気圧という高い圧力において、絶対温度3000Kを超えるような温度に加熱された試料では、硫黄と水素がともに均質に分布した一相の液体が存在していることを確認したとする。
また、それよりも低い温度であった試料では、液体が2つの異なる組成に分かれており、硫黄と水素がそれぞれ異なる側に濃集するという形跡も確認したことから、液体鉄-硫黄-水素合金は高圧下において、温度の低下に伴い、硫黄に富む液体と水素に富む液体に分離するということが示されたという。
異なる圧力と温度に対する同様の実験も行われた結果、現在の火星コアとして見積もられている圧力(約20~40万気圧)と温度(約2000~2500K)は、この液体合金が分離する条件と重なると結論づけられたとする。
-
現在の火星コアの温度・圧力(赤、オレンジ)と初期の火星コアの温度・圧力(ピンク)。黒い線より高温では液体鉄-硫黄-水素合金は1相の均質な液体となり、黒い線の温度を下回ると2相の液体に分離する (出所:東大Webサイト)
火星形成直後の火星コアは、現在よりも高温であったと考えられ、そうした高温下で均質な一相の液体であった火星コアは冷え始めると徐々に2つの液体に分離、底付近に重い液体が溜まっていく一方、軽い液体は、浮き上がって火星コアの対流を促進することとなり、これが火星に磁場を発生させた要因となったとする。
また、さらに時間が経って冷却が十分に進んで、コアの大部分が二相に分離すると、重力的に安定な成層構造(重いものほど下にある)ができ、これが今度はコアの対流を抑制し火星磁場を消失させる効果として働いたと考えられるともし、こうした変化が、火星における磁場の発生と消失のメカニズムとなったとしている。
磁場が失われた火星では、太陽風によって大気が徐々に剥ぎ取られていったと考えられている。長期間にわたって剥ぎ取られ続けた結果、今ではおよそ6hPaという、薄い気圧の大気しかなくなってしまい、また大気の大部分が失われたことで液体の水は維持できなくなり蒸発。さらに水分子は酸素と水素に分解され、軽い水素は宇宙へと逃げていき、海も失われたと考えられるという。
なお、研究チームでは、このシナリオは、火星コアに硫黄に加えて水素が大量に含まれていることを前提としたもので、火星は地球よりも太陽から遠い場所にあるため、地球よりも多くの水が運ばれてきたことが考えられ、そのような大量の水が、火星コアの水素のもととなった可能性が十分にあるとしており、今後、火星コアに水素が含まれているのか、密度成層構造(重い液体が深い部分にある)が現在でも存在するのか、といったことを確認できれば今回の研究のシナリオを検証することが可能だとする。また、火星コアの詳細な構造を、今回の研究成果を用いて解釈することにより、火星を作った材料物質や惑星形成プロセスが明らかになっていくことも期待されるとしている。