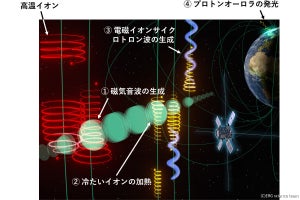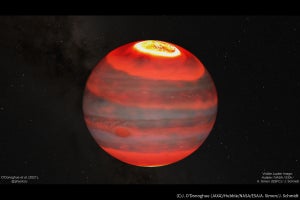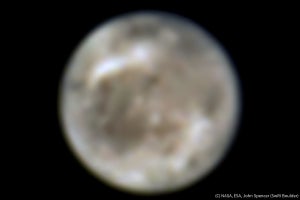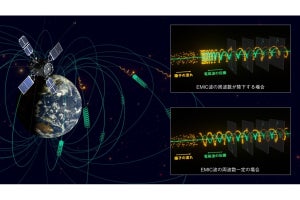名古屋大学(名大)は12月20日、過去4世紀で最大の太陽活動の際(1957~1958年)に日本で観測された一連のオーロラについて、アマチュア天文家が残したスケッチなども含めた歴史的資料を精査し、その低緯度境界が日本の上空まで広がり、また通常の低緯度オーロラと異なる色を見せていたことを明らかにしたと発表した。
同成果は、名大大学院 高等研究院/宇宙地球環境研究所の早川尚志特任助教、京都大学(京大)生存圏研究所の海老原祐輔准教授、東京大学 木曽観測所の畑英利氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、幅広い地球科学分野を扱う学術誌「Geoscience Data Journal」に掲載される予定だ。
太陽活動を示す太陽黒点の観測は、1610年から4世紀にわたって続けられてきている。太陽活動が活発になってくると、太陽表面での爆発現象(フレア)が生じやすくなり、その発生時には電荷を帯びた素粒子などを高速で宇宙空間に放つ「コロナ質量放出」(CME)が起こる。この宇宙空間に撒き散らされた高速の荷電粒子が地球圏を直撃すると、磁気嵐が発生し、その規模が大きいと、オーロラが通常よりも低緯度側に出現するようになることが知られている。
-
1610年~2019年の太陽活動。1957~1958年に太陽黒点相対数(Clette and Lefèvre, 2016)や太陽黒点群数(Svalgaard and Schatten, 2016)が過去4世紀で最大規模に発展していたことがわかる(Silverman and Hayakawa, 2021) (出所:名大プレスリリースPDF)
観測史上最大のフレアとして1859年に発生した「キャリントンフレア」が知られているが、太陽の活動としては、1957~1958年に極大を迎えた第19周期が観測史上最大とされている。このときは、巨大なフレアや磁気嵐が何度も引き起こされたと考えられている。
1957年は、当時の東西両陣営をまたいで「国際地球観測年(IGY)」が企画された年(1957年7月~1958年12月)でもあり、その観測協力対象にはオーロラも含まれ、日本も参加していたほか、磁気嵐の規模を表す「Dst指数」が公式に算出されるようになったのも1957年以降であり、同年9月には史上3番目の、翌1958年2月には4番目の巨大磁気嵐が観測されており、後者の発生時、オーロラが日本でも広範囲で肉眼で観測された記録が残っているほどだが、当時の観測記録の全貌は必ずしも明らかではなかった。
こうした背景を踏まえ研究チームは今回、気象庁、国立天文台、東大木曽観測所のデータを駆使して、1957~58年に発生した激甚磁気嵐によるオーロラ活動の様子を明らかにすることを試みることにしたという。
1958年2月11日の磁気嵐の際のオーロラについて、当時の気象庁による刊行記録の精査が行われたほか、新潟地方気象台においてこれまで忘れられていたオーロラのスケッチの発掘に成功。オーロラ低緯度境界の画定の決め手となったほか、東大木曽観測所に保管されていた観測記録のコピーから、北海道の静内で撮影された国内最古と思われるオーロラのカラー写真の存在や、その当時山口県の小郡や広島県の福山で見えていたオーロラの様子なども明らかにされた。その結果から、この磁気嵐(min.Dst=-426nT)の際のオーロラは、従来考えていたよりも、かなり赤道側に広がっていたことが判明したという。
-
(左上)1958年2月11日に新潟市船江町で記録されたオーロラスケッチ (c)新潟地方気象台提供。(右上)同日、北海道静内で長谷川節也氏によって撮影された国内最古と思われるオーロラ写真 (c)東京大学木曽観測所。(左下)山口県小群町の岡村勲氏によるスケッチ (c)東京大学木曽観測所。(右下)広島県福山市の三村由夫氏によるスケッチ (c)東京大学木曽観測所 (出所:名大プレスリリースPDF)
また今回の研究では、これまで不明な点が多かった1957年9月13日の磁気嵐(min.Dst=-427nT)についても、多数のオーロラ記録の検討を行えたとする。このオーロラについては、北海道の網走や稚内で極めて詳細なスケッチが残されており、さらに北海道の森町の記録などから、オーロラ自体がかなり南まで広がっていたことが判明した。今回は、これらの記録に基づいて、日本で見えたオーロラの範囲も復元された。
また、同日の天気図の検討も行ったところ、本州東部や道東の天気が悪く、オーロラを眼視することが困難であったことも判明したという。この磁気嵐の際のオーロラの報告事例が少なく、かつ、このオーロラがこれまであまり注目されてこなかった理由の一端はこの悪天候にあると考えられるとしている。
さらに、このような日本のオーロラ観測記録と、当時の地磁気変動との比較が行われたところ、いずれも激甚磁気嵐のクライマックス(磁気嵐主相から回復相初期)で起きていたことが判明したという。
当時のオーロラ観測記録の中には、日本で見えるような低緯度オーロラで期待される赤(と緑~白)だけでなく、黄色、オレンジ、ピンク、紫など、多様な色彩が捉えられていたとする。激甚磁気嵐では、通常の磁気嵐よりもエネルギーの高い電子も、日本上空に降り込んでいたことを示唆する貴重な実例と考えられるとしている。
なお、今回のような詳細研究を可能としたのが、60年以上前から現代に至るまで、研究者のみならず、一般市民を含めた多くの協力があったためで、1957~1958年に日本各地で行われたオーロラ観測では、国立天文台の古畑正秋氏の指揮下、国内の観測所のみならず、アマチュア天文家を含む多くの市民が観測に協力したことが、体系的なオーロラ観測を成功させることにつながったとしており、そうした活動は一時期停滞したものの、天体写真の社会還元を目指した東京大学木曽観測所のカラー撮影プロジェクトで再度復活。このプロジェクトがなかったならば、国際地球観測年の資料保存はできなかったと考えられるという。
-
当時の地磁気変動(Dst指数:京大大学院 理学研究科 附属地磁気世界資料解析センター提供)と、今回の研究で明らかにされたオーロラ観測の時間的発展の比較(Hayakawa et al.,2021)。左列が1957年9月の、右列が1958年2月のもの。なお、Dst指数は負の値が大きいほど規模が大きい (出所:名大プレスリリースPDF)
デジタル機器のない時代のアナログの観測データはかさばって場所を取るため、しばしば廃棄されがちだというが、近年では、そうした過去のデータをいかに保存・整備するかについての議論が国際的にもなされるようになってきており、今後もそうした画像データがさらなる宇宙天気研究に貢献することも期待されるという。
現在、太陽は2019年12月から第25周期が始まっており、活動は上昇基調にあり、2025年ごろには極大を迎えるよ予想されており、その前後数年間はオーロラを日本でも見られる可能性があるという。研究チームの名大・早川特任助教らも、もしオーロラを目撃した場合、ぜひ観測時刻やオーロラの高度(星などと対比)、色彩などの情報を記録してみてほしいと呼びかけており、そうした2020年代の市民による観測が数十年後の将来、科学研究に大きなヒントを残すことになるかもしれないとしている。