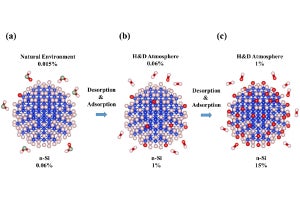大阪大学(阪大)は10月14日、同大学 レーザー科学研究所(ILE)の「激光XIIレーザー」で生成した高温なプラズマに強磁場を加えるとプラズマが変形するという、新しい機構を実験によって観測し、理論・シミュレーションを活用することで、この現象の詳細を明らかにしたと発表した。
同成果は、阪大大学院 理学研究科 物理専攻の松尾一輝大学院生(研究当時)、阪大ILEの佐野孝好助教、同・長友英夫准教授、同・藤岡慎介教授らの研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。
高出力レーザーを用いて、重水素と三重水素の混合物を高密度に圧縮すると同時に、高温に加熱することで核融合反応を起こし、エネルギーを得る手法である「レーザー核融合」方式は、米国や日本、フランス、中国、ロシアなどで研究が行われている。
レーザー核融合に限らず、どの方式においても、核融合実現の課題の1つが、核融合でエネルギーを発生させるには、1億度という超高温のプラズマを閉じ込める必要があるという点であるという。磁場はプラズマを閉じ込める作用を持っており、フランスで建設中の国際熱核融合炉(ITER)や、核融合科学研究所の大型ヘリカル装置「LHD」、量子科学研究機構の超伝導トカマク装置「JT-60SA」で採用されている「磁場閉じ込め核融合装置」は、この磁場によるプラズマの閉じ込めを利用している。
コンピュータシミュレーションによれば、100T程度の強磁場をレーザー核融合プラズマに加えることで、核融合反応数が上昇することが予測されている一方、強磁場下では、プラズマの変形が増大し、均一な高密度プラズマコアの形成を阻害することも予測されており、その実験による検証が待たれていたという。しかし、実験による検証に必要な磁場の強度は数百から数千Tと大きく、これまでは実現困難であったために、従来、これらの効果は理論およびシミュレーション上で議論されるのみだったという。
藤岡教授らは2013年、国内最大級のレーザー装置である激光XII号レーザーを「キャパシター・コイル・ターゲット」と呼ばれる磁場発生装置に当てることで、微小な空間と短い時間内に1000Tを越える磁場を発生できることを報告しており、今回の実験では、この強磁場発生法を用いて、実験室内で200Tの磁場を発生させ、その強磁場下でのレーザー核融合プラズマの挙動を調べることにしたという。
その結果、200Tの磁場の印加により、高温プラズマから周囲への熱エネルギーの損失が抑制されることでプラズマの温度が上昇することが判明したほか、温度上昇に伴ってプラズマの変形が大きくなるという負の側面も確認されてという。ただし、この流体力学的不安定性の成長が増大する効果が発現する条件が、主にプラズマの温度とサイズ、そして磁場の強度によって決定されることも突き止めたとしており、これらを活用することで、磁場とレーザー核融合方式を組み合わせた新しい核融合方式の発展が期待されるとしている。
また、宇宙において観測可能な物質の99%はプラズマとされ、それら宇宙プラズマにおいても、磁場とプラズマの相互作用が重要であることから、今回発見された現象についても、超新星爆発によって広がる衝撃波と星雲の衝突過程と密接に関連していることが指摘されているとしており、今後、そうした宇宙プラズマの流体力学的挙動やその素過程を調べる手法につながることが期待されるともしている。